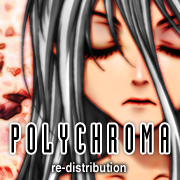軍人には向かない職業:GateOdyssey:novels|創作小説集団CRAFTWORX(クラフトワークス)
軍人には向かない職業
Do your best the director
「あれぇ……リュシィ?」
寝ぼけた声。
その声は間違いなく歳相応の子供の声で──それとともに、圧迫感は痕跡も残さず霧散した。
子供達は立ち上がり、服の埃をぱたぱたはたく。
俺は途惑いつつも……子供達を観察した。
見た目は血統書付きの猫のように整ってる。
が、それが異様さを醸し出すのは──七人の余りにも似通った造作のせいだった。
勿論個体差はある。髪や瞳の色、髪型の違い、など。
ただ、それを除くと──子供達は全く同じ、と言っていいくらいそっくりで──七つ子といっても差し支えないくらいだ。多胎児が少ない昨今、珍しい。
「どうしたの、いらっしゃい」
ぼーっとその場に立ちっぱなしだった子供達は、彼女の言葉で近くへ寄ってくる。
時々、ちらちらとこちらを見る気配を感じる。
ああ、すぐ彼女の許に寄ってこないのは初めて見る人間がそばにいるからか。
「あの人間、誰」
……お兄さんでもなくおじさんでもなく、『人間』ときたか。
「『人間』、じゃないでしょ。明日から、私じゃなくてこのお兄さんがこの部屋に来るの」
「えー」
あぁ抗議の声が。そりゃ子供にしてみれば、むさいお兄さんより綺麗なお姉さんのほうがいいに決まってる。
「ごめんね。でもお兄さんも優しい人だから」
おいおい。会ったばかりでそういうことを言いますか、ミラーさん。
「えーと……シーヴァーズさん……お名前」
「マティアス、です。マットでいいですよ」
「マティアス。いいお名前ですね」
そういうと、ミラーさんは再び子供達のほうへ向き直り、俺を紹介してくれる。
「マット、よ。覚えてね」
「……よろしくな」
「マット」
「マット」
子供達が口々に俺の名前を呼んで、俺を見る。
「……分かった」
そう返事をすると、子供達はまた別々の方向へ散ろうとする。……おーい。
無関心にも程があるだろ。
「待てぇぇぇ!」
ぴたっと止まって俺を振り返る子供達。
沈黙が場を支配する。
俺はそれに耐えかねて、思わず大声で叫んだ。
「前に集合!」
──途端にこちらに走ってくる子供達。無関心な割に、えらい従順だな。
「整列!」
言葉がわかるかな、と思ったけど子供達は素直に真横に並ぶ。
「……右から順番に名前教えてくれるかな」
子供達は互いに顔を見合すと、順番に名前を並べ始めた。
「ミント」
「シナモン」
「セージ」
「マロウ……」
「タイム」
「ジンジャーです」
「……ローレル」
……全部ハーブの名前なのか。覚えやすそうな、区別つかなさそうな。
「……もういい?」
じーっと子供達を覚えるために観察していると、端っこの子供が言った。
「ん……あぁ。じゃぁ明日からよろしくな」
俺がそういうと、子供達はそれぞれ散らばってゆき……適当な場所へ移動してそのままうずくまった。
……あのー?
どうやら子供達はまだ眠かったようで……睡眠を再開したみたいだった。
「じゃ、顔合わせが終わったところで行きましょう」
「はぁ……」
寝息を立てる子供達をあとに、俺達は部屋に鍵をかけ廊下へと出た。
俺は案内されるにまかせ、館内のロビーらしき場所へ連れて行かれた。
「おかけ下さい」
勧められるままに椅子に腰掛けると、続いて彼女も席につく。
「もし、お時間に問題がないなら面談をさせていただきたいのですけど……シーヴァーズさんも質問したいことなどもあるでしょうし」
「……マットでいいです。何か落着きません」
姓のほうだと、学校の先生に呼ばれている気がしてしまう。背筋伸ばして『はいっ』って返事してしまいそうな。
「あら」
そう言って彼女が微笑む。
「では私のこともリュシュカとお呼びください。──面談といっても形式的なことですのでそんなに堅苦しくなさらなくても結構ですわ」
「はぁ……」
俺が肯定とも否定とも言いがたい返事をすると、彼女は机に書類を広げた。
そのまま身分確認が始まる。
質問は多岐に及んだが、大体は『はい』か『いいえ』で終わる内容だった。
「……で、勤務形態についてですけど」
彼女がよろしいですか? と視線で訊ねる。
俺が頷くと、彼女は言葉を続けた。
「勤務時間は夜間です。23時から7時。ID登録が完了するまでは私を呼び出してもらう形になりますので、15分前には私に電話していただけると助かります」
……夜間? 子供の面倒を見るのに?
「夜……ですか」
「えぇ」
彼女が肯定する。
「あの子達は夜行性なんです。一方私達の活動時間帯は基本的に日中ですから、夜間はどうしても人員が足りなくて……」
夜行性って。野生動物でもあるまいし。
「子供は夜寝て大きくなるもんでしょう」
「いえ……私達はあの子達に昼間いろいろ付き合ってもらってますから。あの子達の本来の性質を曲げてもらってるのですから、それ以外のところではなるべく彼らの自然のままにしておきたいのです」
──意味不明。
「……まぁ、私達の基本方針だと考えていただければそれで結構です」
彼女は苦笑いして言う。
「それと、業務についてなのですが……8時間あの部屋にいてください」
予想外の言葉に俺は驚く。
確か……保育業務、って言ってなかったか?
「いてくださいって……『いるだけ』、ですか?」
「えぇ。あぁ、日誌を書くという義務は発生しますけどそれも形式的なものですし」
余計訳がわからなかった。そんなことに、わざわざ外部の人間を雇う必要があるものなのか。
俺はそれについてはあえてここでは問わなかった。代わりに。
「……リュシュカさんは俺の前任として、その仕事をやってたんですよね」
「? ──えぇ」
それが何か? と彼女が視線で問う。
「なぜあなたはその任を離れることになったのですか」
「それは随分プライベートに関わった質問ですのね」
……しまった。失礼なことを聞いてしまったのかな。
俺が困惑していると、彼女はくすっと微笑って言った。
「まぁいいですわ。──理由は、『あの子達が可愛くなってきてしまったから』、です」
そういうと、彼女は席を立ち上がった。
それは、『それ以上この件については訊ねるな』、という彼女の意思表示なのだろう。
「すいません──俺」
「いえ。あなたに悪意がないのはわかりますから」
彼女が広げた書類をまとめながら応える。そして。
「勤務開始日時は明日23時からです。それまでに私に電話を下さい。電話番号はこれです」
彼女が胸ポケットからカードケースを取り出し、中から一枚抜き取って俺に渡してくれる。
研究者らしい、堅いイメージの名刺。
「有難うございます……俺名刺持ってないんでお返しできませんけども」
「構いませんわ」
彼女は笑顔を崩さない。
──俺は不意に、彼女の笑顔は『防衛』なのだと悟った。
「……ふぅ」
自宅に帰ると、ばたんとベッドへ倒れこむ。
俺が住んでいるのは寮みたいな単身者向けの建物の一室で、あるのは申し訳程度の台所と寝床とテーブルが一つ。
……いつ死ぬかわからないのに、余分なもの置いといたってどうにもならないだろう。死んだあとに遺品漁られるのも勘弁、だしな。
しばらく天井と見つめ合いをして──のそのそと起き上がり、台所の棚から酒を持ってくる。
グラスに氷を手づかみで入れると、そのまま琥珀色の液体を注いだ。
……戦場で瀕死の重傷を負ったのは二年前のことだ。
気がついたら俺は病院のベッドの上にいて、左手はうまく動かなかったし、右足に至っては膝から下が失くなっていた。
俺の実家はいわゆる貧民街にあり、成人ですら真っ当な仕事に就くのは難しい。俺は形ばかりの義務教育を終えると士官学校へ進み──ノンキャリアなりの軍隊生活を送る予定だった。
しかし俺は数年の勤務の中で、自ら選んだ道に疑問を覚えるようになる。
それは、戦場での軍の在り方。
戦争は殺し合いだ。綺麗事じゃすまないことは分かっている。だが、戦意をそもそも持っていない女子供を皆殺しにすることに意味はあるのか。
無論、そんなことは世論も軍規も許しはしない。しかしそれは戦場という閉鎖された世界では往々にして行われ、そういう状況における最悪の極みを何度も見せつけられた。
覚悟はしていたはずだった。けれど、それは……結局のところ『つもり』に過ぎなかったのだ。
他の道も考えた。しかし俺が持っているもの──それは戦争の技術だけ。
数年の軍人生活を過ごしたあと俺はその身分を捨て、フリーランス──つまりは傭兵となる道を選んだ。
そんな最中での瀕死の重傷。
絶望的な状況の中、それでも手は差し伸べられた。もっともその手を取った瞬間、離せなくなる性質のものではあったが。
復帰したのちに何年かの行動を拘束することを条件に、俺は義足の手術とリハビリ、その期間の生活費を得ることができた。
だから、本当は廻ってくる仕事に注文をつける、なんて真似はできはしない。
俺はポケットからリュシュカ──彼女にもらった名刺を取り出した。
Dritte Kategorie lebendes Sachelabor
(第三種生物研究所)
Leiter der Mannschaft E(チームE 主任)
Ruschka Miller(リュシュカ ミラー)
BT XX-XXXXX-XXXXXXX
住所などは一切入っていない。
研究所名も場所を特定できそうなものではない。
書かれている電話番号は、彼女の携帯電話のものだろう。
……まぁ、リハビリかねての仕事にはちょうどいいだろう。怪我することもないだろうし、それで金が稼げるのなら。
俺はそのあと何杯か酒をあおり──数時間後、呼ばれるまま睡眠に落ちていった。
寝ぼけた声。
その声は間違いなく歳相応の子供の声で──それとともに、圧迫感は痕跡も残さず霧散した。
子供達は立ち上がり、服の埃をぱたぱたはたく。
俺は途惑いつつも……子供達を観察した。
見た目は血統書付きの猫のように整ってる。
が、それが異様さを醸し出すのは──七人の余りにも似通った造作のせいだった。
勿論個体差はある。髪や瞳の色、髪型の違い、など。
ただ、それを除くと──子供達は全く同じ、と言っていいくらいそっくりで──七つ子といっても差し支えないくらいだ。多胎児が少ない昨今、珍しい。
「どうしたの、いらっしゃい」
ぼーっとその場に立ちっぱなしだった子供達は、彼女の言葉で近くへ寄ってくる。
時々、ちらちらとこちらを見る気配を感じる。
ああ、すぐ彼女の許に寄ってこないのは初めて見る人間がそばにいるからか。
「あの人間、誰」
……お兄さんでもなくおじさんでもなく、『人間』ときたか。
「『人間』、じゃないでしょ。明日から、私じゃなくてこのお兄さんがこの部屋に来るの」
「えー」
あぁ抗議の声が。そりゃ子供にしてみれば、むさいお兄さんより綺麗なお姉さんのほうがいいに決まってる。
「ごめんね。でもお兄さんも優しい人だから」
おいおい。会ったばかりでそういうことを言いますか、ミラーさん。
「えーと……シーヴァーズさん……お名前」
「マティアス、です。マットでいいですよ」
「マティアス。いいお名前ですね」
そういうと、ミラーさんは再び子供達のほうへ向き直り、俺を紹介してくれる。
「マット、よ。覚えてね」
「……よろしくな」
「マット」
「マット」
子供達が口々に俺の名前を呼んで、俺を見る。
「……分かった」
そう返事をすると、子供達はまた別々の方向へ散ろうとする。……おーい。
無関心にも程があるだろ。
「待てぇぇぇ!」
ぴたっと止まって俺を振り返る子供達。
沈黙が場を支配する。
俺はそれに耐えかねて、思わず大声で叫んだ。
「前に集合!」
──途端にこちらに走ってくる子供達。無関心な割に、えらい従順だな。
「整列!」
言葉がわかるかな、と思ったけど子供達は素直に真横に並ぶ。
「……右から順番に名前教えてくれるかな」
子供達は互いに顔を見合すと、順番に名前を並べ始めた。
「ミント」
「シナモン」
「セージ」
「マロウ……」
「タイム」
「ジンジャーです」
「……ローレル」
……全部ハーブの名前なのか。覚えやすそうな、区別つかなさそうな。
「……もういい?」
じーっと子供達を覚えるために観察していると、端っこの子供が言った。
「ん……あぁ。じゃぁ明日からよろしくな」
俺がそういうと、子供達はそれぞれ散らばってゆき……適当な場所へ移動してそのままうずくまった。
……あのー?
どうやら子供達はまだ眠かったようで……睡眠を再開したみたいだった。
「じゃ、顔合わせが終わったところで行きましょう」
「はぁ……」
寝息を立てる子供達をあとに、俺達は部屋に鍵をかけ廊下へと出た。
†
俺は案内されるにまかせ、館内のロビーらしき場所へ連れて行かれた。
「おかけ下さい」
勧められるままに椅子に腰掛けると、続いて彼女も席につく。
「もし、お時間に問題がないなら面談をさせていただきたいのですけど……シーヴァーズさんも質問したいことなどもあるでしょうし」
「……マットでいいです。何か落着きません」
姓のほうだと、学校の先生に呼ばれている気がしてしまう。背筋伸ばして『はいっ』って返事してしまいそうな。
「あら」
そう言って彼女が微笑む。
「では私のこともリュシュカとお呼びください。──面談といっても形式的なことですのでそんなに堅苦しくなさらなくても結構ですわ」
「はぁ……」
俺が肯定とも否定とも言いがたい返事をすると、彼女は机に書類を広げた。
そのまま身分確認が始まる。
質問は多岐に及んだが、大体は『はい』か『いいえ』で終わる内容だった。
「……で、勤務形態についてですけど」
彼女がよろしいですか? と視線で訊ねる。
俺が頷くと、彼女は言葉を続けた。
「勤務時間は夜間です。23時から7時。ID登録が完了するまでは私を呼び出してもらう形になりますので、15分前には私に電話していただけると助かります」
……夜間? 子供の面倒を見るのに?
「夜……ですか」
「えぇ」
彼女が肯定する。
「あの子達は夜行性なんです。一方私達の活動時間帯は基本的に日中ですから、夜間はどうしても人員が足りなくて……」
夜行性って。野生動物でもあるまいし。
「子供は夜寝て大きくなるもんでしょう」
「いえ……私達はあの子達に昼間いろいろ付き合ってもらってますから。あの子達の本来の性質を曲げてもらってるのですから、それ以外のところではなるべく彼らの自然のままにしておきたいのです」
──意味不明。
「……まぁ、私達の基本方針だと考えていただければそれで結構です」
彼女は苦笑いして言う。
「それと、業務についてなのですが……8時間あの部屋にいてください」
予想外の言葉に俺は驚く。
確か……保育業務、って言ってなかったか?
「いてくださいって……『いるだけ』、ですか?」
「えぇ。あぁ、日誌を書くという義務は発生しますけどそれも形式的なものですし」
余計訳がわからなかった。そんなことに、わざわざ外部の人間を雇う必要があるものなのか。
俺はそれについてはあえてここでは問わなかった。代わりに。
「……リュシュカさんは俺の前任として、その仕事をやってたんですよね」
「? ──えぇ」
それが何か? と彼女が視線で問う。
「なぜあなたはその任を離れることになったのですか」
「それは随分プライベートに関わった質問ですのね」
……しまった。失礼なことを聞いてしまったのかな。
俺が困惑していると、彼女はくすっと微笑って言った。
「まぁいいですわ。──理由は、『あの子達が可愛くなってきてしまったから』、です」
そういうと、彼女は席を立ち上がった。
それは、『それ以上この件については訊ねるな』、という彼女の意思表示なのだろう。
「すいません──俺」
「いえ。あなたに悪意がないのはわかりますから」
彼女が広げた書類をまとめながら応える。そして。
「勤務開始日時は明日23時からです。それまでに私に電話を下さい。電話番号はこれです」
彼女が胸ポケットからカードケースを取り出し、中から一枚抜き取って俺に渡してくれる。
研究者らしい、堅いイメージの名刺。
「有難うございます……俺名刺持ってないんでお返しできませんけども」
「構いませんわ」
彼女は笑顔を崩さない。
──俺は不意に、彼女の笑顔は『防衛』なのだと悟った。
†
「……ふぅ」
自宅に帰ると、ばたんとベッドへ倒れこむ。
俺が住んでいるのは寮みたいな単身者向けの建物の一室で、あるのは申し訳程度の台所と寝床とテーブルが一つ。
……いつ死ぬかわからないのに、余分なもの置いといたってどうにもならないだろう。死んだあとに遺品漁られるのも勘弁、だしな。
しばらく天井と見つめ合いをして──のそのそと起き上がり、台所の棚から酒を持ってくる。
グラスに氷を手づかみで入れると、そのまま琥珀色の液体を注いだ。
……戦場で瀕死の重傷を負ったのは二年前のことだ。
気がついたら俺は病院のベッドの上にいて、左手はうまく動かなかったし、右足に至っては膝から下が失くなっていた。
俺の実家はいわゆる貧民街にあり、成人ですら真っ当な仕事に就くのは難しい。俺は形ばかりの義務教育を終えると士官学校へ進み──ノンキャリアなりの軍隊生活を送る予定だった。
しかし俺は数年の勤務の中で、自ら選んだ道に疑問を覚えるようになる。
それは、戦場での軍の在り方。
戦争は殺し合いだ。綺麗事じゃすまないことは分かっている。だが、戦意をそもそも持っていない女子供を皆殺しにすることに意味はあるのか。
無論、そんなことは世論も軍規も許しはしない。しかしそれは戦場という閉鎖された世界では往々にして行われ、そういう状況における最悪の極みを何度も見せつけられた。
覚悟はしていたはずだった。けれど、それは……結局のところ『つもり』に過ぎなかったのだ。
他の道も考えた。しかし俺が持っているもの──それは戦争の技術だけ。
数年の軍人生活を過ごしたあと俺はその身分を捨て、フリーランス──つまりは傭兵となる道を選んだ。
そんな最中での瀕死の重傷。
絶望的な状況の中、それでも手は差し伸べられた。もっともその手を取った瞬間、離せなくなる性質のものではあったが。
復帰したのちに何年かの行動を拘束することを条件に、俺は義足の手術とリハビリ、その期間の生活費を得ることができた。
だから、本当は廻ってくる仕事に注文をつける、なんて真似はできはしない。
俺はポケットからリュシュカ──彼女にもらった名刺を取り出した。
Dritte Kategorie lebendes Sachelabor
(第三種生物研究所)
Leiter der Mannschaft E(チームE 主任)
Ruschka Miller(リュシュカ ミラー)
BT XX-XXXXX-XXXXXXX
住所などは一切入っていない。
研究所名も場所を特定できそうなものではない。
書かれている電話番号は、彼女の携帯電話のものだろう。
……まぁ、リハビリかねての仕事にはちょうどいいだろう。怪我することもないだろうし、それで金が稼げるのなら。
俺はそのあと何杯か酒をあおり──数時間後、呼ばれるまま睡眠に落ちていった。