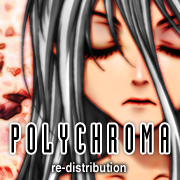飼い猫:GateOdyssey:novels|創作小説集団CRAFTWORX(クラフトワークス)
飼い猫
Inside in cage
余り心地が良いとはいえない目覚めだった。
けれど、既に窓の外の景色は橙色に染まっており……これ以上寝っ転がっていたら時間ぎりぎりになることは必至だった。
……ので、のっそりと起き上がる。
頭の中で指折り数える。今から汗流して、晩飯買いだして食って、持ってきて下さいと頼まれた書類を揃えて、身支度も整えて……と。そうしたらだいたいちょうどいい時間になるだろう。
今きている服を脱ぎクリーニング用の袋に突っ込み、新しいシャツを漁る。別にTシャツにデニムでも文句言わないだろう。
シャワーを浴びた後、用意した服に着替え──少し考えて、長袖のTシャツの上に半袖のカッターシャツを羽織り、家を出た。
22時40分。施設に到着。
俺は軽く緊張していた。
単に見ているだけでいいとは言われたものの、相手は子供だ。うっかり泣かせてしまったらどうしよう、とか……いろんな心配事が頭をよぎる。
それに……いや、今は言うまい。
仕事なんだから。
俺は吐息をついて、ポケットから携帯電話を取り出した。
彼女の名刺を見ながら、注意深くボタンを押す。
一回。二回。……
七回目のコール音の途中で、受話ボタンを押した音がした。
「シーヴァーズですが」
「はい、こちらミラーです……きゃぁぁぁぁぁっっっ」
彼女の声が突然甲高い悲鳴になる。
「ど、どうしました?」
くぁんくぁん鳴る頭を押さえて、俺は訊ねた。
その向こうには走り回る軽い足音。……あいつらか?
返事は数十秒後に返ってきた。
「す、すいません、シーヴァーズさん……到着されたんですよね、ただいま向かいますっ」
心なしか涙声で一方的に彼女は告げると、そのまま携帯電話は切れた。
そのままその場で待つこと一分程。
がちゃり、と扉が開いた。
「お待たせしました。入ってください」
俺はその言葉に従って中に入り込んだ。
「ごめんなさい……電話口で叫んだりして」
彼女は瞳を潤ませて鼻にかかった声で溜息まじりに言った。
「電話取った途端、ちょっと騒ぎが起きちゃって……」
そういいながら、まなじりを細い指先で軽く抑えている。
何だか自分が彼女を泣かせたような気まずさを感じて、反対側の斜め上を見上げた。
彼女が、個室の鍵を開ける。
中に入ると──子供達は部屋の中央に固まるように座り込んでいた。
俺達に気付いたのか、一人の子供がこちらを向く。
「リュシィ?」
子供はそのまま後ろ手に宝物を隠すようにしてとてとてと走ってきた。
「見て、俺が仕留めたんだぜー」
得意げにニコニコしながら、その子供は宝物を彼女の前で披露する。
──彼女が硬直する。そのまま、その場に崩れ落ちた。
「リュシュカさん?」
俺は軽く彼女を揺さぶった。……彼女は無意識の中に完全に逃亡を決め込んでいた。
「……リュシィ?」
子供が不思議そうに彼女を見ている。
……手のひらに乗っている大事な宝物は、ほとんど瀕死の白いねずみさんだった。
彼女が目を覚ましたのは、十数分後だった。
「気がつきましたか?」
俺は声をかけ、淹れたてのコーヒーをすすった。
いいコーヒー使ってるな。戦場の配給のやつより原価は遥かに高そうだ。
「あの……私……」
携帯電話以外に彼女に関する連絡先を知らない俺は、仕方なく子供達のベッドに彼女を寝かせてあった。
「『あれ』はもう俺が取り上げて処分しました。掃除もしましたから安心してください」
……気絶直前の出来事を思い出したのだろう。彼女は情けなさそうな顔をしていた。
「すいません、ご面倒かけました……」
「いえいえ。苦手なものはしょうがないですよ」
俺だって、極限状況でもなければ瀕死のねずみなんて触りたくない。
「この部屋を事前に確認に来る前、実験使用前のマウスを逃がしてしまった、というのは聞いてたんです。どうやらそれが通風孔を伝ってこの部屋へ入り込んでしまったみたいで……」
彼女は身体を起こし、そのままベッドに腰掛け……深く息を吐いた。
「研究者なのに、情けないですよね……普段、滅菌室でマウスを扱うときは覚悟を決めてるから大丈夫なんですけど……」
必死に言い訳をする彼女を見ながら、自然と口の端が持ち上がる。少なくとも笑顔を防御に利用していた昨日の姿より、断然魅力的に思えたからだろう。
「……笑わないで下さい」
そういわれて、慌てて表情をまじめに整えた。
「すいません」
「いえ……あの……ごめんなさい……その」
言い淀みながら彼女が立ち上がる。
「……他のメンバーには……できれば、話さないで下さい……」
「……?……」
「科学者って……特にこういった大きいラボに所属している人というのは……言葉遣いこそ丁寧なんですけど、結構キツい人が多いんです」
……慇懃無礼ってヤツか。嫌だな、そういうのは。
「言われたからと言っていちいち取り合ったりはしませんけど……ね」
強気に呟く声。
けれど、少なからずそのことに傷ついたことはあるのだろう。
俺は飲み終わったコーヒーのカップを机に置いて言った。
「……分かりました。喋りません」
彼女は微笑んで……それでは私、帰りますので、と断ってこの部屋を出て行った。
ぱたん……と扉が閉まる。
──俺は、ずっと感じていた非難の視線をどうしようか考えていた。
彼らにとって宝物であろうと、実験用の飼われていたものであろうと、ねずみの死骸ってのは非衛生的としか思えない。だから俺は子供からそいつを無理やり取り上げた訳なんだが……
怒ってる。すげー怒ってる。第一印象最悪か。こりゃ。
しかし俺もここで引く訳にはいかない。
「……俺の獲物……」
「だめつったらだめ」
「だって俺が仕留めたんだぞ」
「うん、すごい。すごいけど人の嫌がることをするのは良くない」
「けど、リュシィ自分で獲物捕まえることできないじゃん。だからあげようと思ったのに……」
……は? 意味不明。
意味不明だけど……だめなものはだめだ。
「リュシィは別にそんなのはいらないんだ」
「マットはいるのか?」
「へ?」
「とりあげたじゃん」
「俺だっていらないよ」
「じゃ、返してよー」
「汚いから、だめ」
「えー」
「だめったらだめ」
そこまで言うと。埒があかないと思ったのか、子供はぷーとふくれて彼らの輪の中に戻っていった。
……だめったらだめ、か。
自分が子供の頃を思い出す。お袋がそう言ったらもう絶対だめ、で──納得できない、って俺も拗ねたよなぁ。
けれど、いざ自分が大人になると……あっさり使っちまうもんなんだな。
俺は、部屋の片隅に申し訳程度に置いてある椅子に腰掛けると……遊んでいる子供達を遠目に眺めた。
端から見ると、子供達は面白いくらい個人主義で……2人でずっと遊んでても、片方が飽きるとあっさり別のことに切り換えてしまう。置いてかれるほうも全く気にしてないみたいだ。
さっきの、『俺』って言ってたのはシナモン、だったっけ。
シナモンの隣で一緒に遊んでるんだか口喧嘩してるんだかよくわからないのがマロウ。
一人で遊んでるのがジンジャー。
ジャングルジムに登って遊んでるのがミントとセージ。
あと、仲良く本を読んでるのが……ローレルとタイム……あ、あれは違うかな。一人で本を読んでるローレルに、一方的に構ってるのがタイム、か。初等学校にもいたよな、一人でいる奴を構って何とか周りに溶け込まそうとする奴ってのが。
この分だと、すぐって言ったら無理だけど、数日もすれば区別がつくようになるだろう。
……しっかし、暇だな。俺も雑誌なり本なり持ってこないと時間つぶせないかもしれない。でも、私物の持込は許可を取らなきゃいけないって契約書には書いてあったし……毎日許可をもらうのも面倒だしなぁ。
……どた。
落下物の音がして、俺はぎょっと顔を上げる。
ジャングルジムの下で子供が倒れていた。
「お……おい」
慌てて俺はそばに駆け寄る。
小さい身体を抱きかかえると──寝て……る?
「……あ。マットも驚いた」
ミント、だっけか。子供にしては随分と冷静な声で言う。
「……も?」
「リュシィも最初、驚いた。でも、セージ、寝てるだけだから」
そういうとミントも、あーふ、と大きいあくびをした。
「今日、昼間、仕事だったからちょっと眠たいんだ……仕事っていっても、線つないだりとかだけど」
……仕事? 線?
頭は疑問符だらけだが、とりあえずただ眠ってるだけ、というのは理解できた。呼吸も規則的だし。
しょうがないな。こいつも運んでやるか。
抱えていた身体をそのまま持ち上げ、ベッドまで運ぶ。
うわ、軽いし柔らかい。……まるでぬいぐるみみたいだ。違うのは温かいということくらいか。子供は基礎体温が高いって言うからな。
ひとまず、仰向けに寝かせてシーツをかけてやると、すぐにごろんと横向きになって、すーすーと寝息を立てていた。
改めて先程まで座っていた椅子に戻り……ぐるりと部屋の全景を見回す。
窓のない、閉鎖された空間。
おもちゃこそたくさん置いてあるけど……駆け回れる広さもあるけれど。
ここのイメージは……『檻』、だ。
……俺は、ここにいられなくなった、と言った彼女の気持ちが……わかったような気がした。
「リュシュカ」
モニターだらけの小さな部屋。
頬杖ついて、子供達の部屋の様子を見ていた女性が、ゆっくりと振り返る。
「彼、どう?」
「特に……何も教えてないから、ごく普通に見えるわね」
それだけ答えて、彼女はもう一度モニターに視線を戻す。
「そう」
声をかけた女性も、彼女の後ろから屈んで同じモニターを覗き込んだ。
「それにしちゃ、やたら未練たっぷりな後姿だったわよ。……本当は、あの子達から離れるの、嫌だったんじゃない?」
「まさか」
苦さを含ませて、彼女は笑う。
「あまりあの子達に関わり過ぎるのは──科学者として、よくないわ。いざというとき、思いきることができなくなるもの」
「そうね」
「そうよ」
彼女は、返事と共にモニターを切って──席を立ち上がる。
「さて、本当に帰るわ。うちの子も待ってるし」
「お疲れ様」
「また明日」
小さく手を振り……彼女は優雅に鞄を下げ、扉を出てゆく。
──あの子達と離れたくなかったなんて──まさか。
けれど、既に窓の外の景色は橙色に染まっており……これ以上寝っ転がっていたら時間ぎりぎりになることは必至だった。
……ので、のっそりと起き上がる。
頭の中で指折り数える。今から汗流して、晩飯買いだして食って、持ってきて下さいと頼まれた書類を揃えて、身支度も整えて……と。そうしたらだいたいちょうどいい時間になるだろう。
今きている服を脱ぎクリーニング用の袋に突っ込み、新しいシャツを漁る。別にTシャツにデニムでも文句言わないだろう。
シャワーを浴びた後、用意した服に着替え──少し考えて、長袖のTシャツの上に半袖のカッターシャツを羽織り、家を出た。
†
22時40分。施設に到着。
俺は軽く緊張していた。
単に見ているだけでいいとは言われたものの、相手は子供だ。うっかり泣かせてしまったらどうしよう、とか……いろんな心配事が頭をよぎる。
それに……いや、今は言うまい。
仕事なんだから。
俺は吐息をついて、ポケットから携帯電話を取り出した。
彼女の名刺を見ながら、注意深くボタンを押す。
一回。二回。……
七回目のコール音の途中で、受話ボタンを押した音がした。
「シーヴァーズですが」
「はい、こちらミラーです……きゃぁぁぁぁぁっっっ」
彼女の声が突然甲高い悲鳴になる。
「ど、どうしました?」
くぁんくぁん鳴る頭を押さえて、俺は訊ねた。
その向こうには走り回る軽い足音。……あいつらか?
返事は数十秒後に返ってきた。
「す、すいません、シーヴァーズさん……到着されたんですよね、ただいま向かいますっ」
心なしか涙声で一方的に彼女は告げると、そのまま携帯電話は切れた。
そのままその場で待つこと一分程。
がちゃり、と扉が開いた。
「お待たせしました。入ってください」
俺はその言葉に従って中に入り込んだ。
「ごめんなさい……電話口で叫んだりして」
彼女は瞳を潤ませて鼻にかかった声で溜息まじりに言った。
「電話取った途端、ちょっと騒ぎが起きちゃって……」
そういいながら、まなじりを細い指先で軽く抑えている。
何だか自分が彼女を泣かせたような気まずさを感じて、反対側の斜め上を見上げた。
彼女が、個室の鍵を開ける。
中に入ると──子供達は部屋の中央に固まるように座り込んでいた。
俺達に気付いたのか、一人の子供がこちらを向く。
「リュシィ?」
子供はそのまま後ろ手に宝物を隠すようにしてとてとてと走ってきた。
「見て、俺が仕留めたんだぜー」
得意げにニコニコしながら、その子供は宝物を彼女の前で披露する。
──彼女が硬直する。そのまま、その場に崩れ落ちた。
「リュシュカさん?」
俺は軽く彼女を揺さぶった。……彼女は無意識の中に完全に逃亡を決め込んでいた。
「……リュシィ?」
子供が不思議そうに彼女を見ている。
……手のひらに乗っている大事な宝物は、ほとんど瀕死の白いねずみさんだった。
†
彼女が目を覚ましたのは、十数分後だった。
「気がつきましたか?」
俺は声をかけ、淹れたてのコーヒーをすすった。
いいコーヒー使ってるな。戦場の配給のやつより原価は遥かに高そうだ。
「あの……私……」
携帯電話以外に彼女に関する連絡先を知らない俺は、仕方なく子供達のベッドに彼女を寝かせてあった。
「『あれ』はもう俺が取り上げて処分しました。掃除もしましたから安心してください」
……気絶直前の出来事を思い出したのだろう。彼女は情けなさそうな顔をしていた。
「すいません、ご面倒かけました……」
「いえいえ。苦手なものはしょうがないですよ」
俺だって、極限状況でもなければ瀕死のねずみなんて触りたくない。
「この部屋を事前に確認に来る前、実験使用前のマウスを逃がしてしまった、というのは聞いてたんです。どうやらそれが通風孔を伝ってこの部屋へ入り込んでしまったみたいで……」
彼女は身体を起こし、そのままベッドに腰掛け……深く息を吐いた。
「研究者なのに、情けないですよね……普段、滅菌室でマウスを扱うときは覚悟を決めてるから大丈夫なんですけど……」
必死に言い訳をする彼女を見ながら、自然と口の端が持ち上がる。少なくとも笑顔を防御に利用していた昨日の姿より、断然魅力的に思えたからだろう。
「……笑わないで下さい」
そういわれて、慌てて表情をまじめに整えた。
「すいません」
「いえ……あの……ごめんなさい……その」
言い淀みながら彼女が立ち上がる。
「……他のメンバーには……できれば、話さないで下さい……」
「……?……」
「科学者って……特にこういった大きいラボに所属している人というのは……言葉遣いこそ丁寧なんですけど、結構キツい人が多いんです」
……慇懃無礼ってヤツか。嫌だな、そういうのは。
「言われたからと言っていちいち取り合ったりはしませんけど……ね」
強気に呟く声。
けれど、少なからずそのことに傷ついたことはあるのだろう。
俺は飲み終わったコーヒーのカップを机に置いて言った。
「……分かりました。喋りません」
彼女は微笑んで……それでは私、帰りますので、と断ってこの部屋を出て行った。
ぱたん……と扉が閉まる。
──俺は、ずっと感じていた非難の視線をどうしようか考えていた。
彼らにとって宝物であろうと、実験用の飼われていたものであろうと、ねずみの死骸ってのは非衛生的としか思えない。だから俺は子供からそいつを無理やり取り上げた訳なんだが……
怒ってる。すげー怒ってる。第一印象最悪か。こりゃ。
しかし俺もここで引く訳にはいかない。
「……俺の獲物……」
「だめつったらだめ」
「だって俺が仕留めたんだぞ」
「うん、すごい。すごいけど人の嫌がることをするのは良くない」
「けど、リュシィ自分で獲物捕まえることできないじゃん。だからあげようと思ったのに……」
……は? 意味不明。
意味不明だけど……だめなものはだめだ。
「リュシィは別にそんなのはいらないんだ」
「マットはいるのか?」
「へ?」
「とりあげたじゃん」
「俺だっていらないよ」
「じゃ、返してよー」
「汚いから、だめ」
「えー」
「だめったらだめ」
そこまで言うと。埒があかないと思ったのか、子供はぷーとふくれて彼らの輪の中に戻っていった。
……だめったらだめ、か。
自分が子供の頃を思い出す。お袋がそう言ったらもう絶対だめ、で──納得できない、って俺も拗ねたよなぁ。
けれど、いざ自分が大人になると……あっさり使っちまうもんなんだな。
†
俺は、部屋の片隅に申し訳程度に置いてある椅子に腰掛けると……遊んでいる子供達を遠目に眺めた。
端から見ると、子供達は面白いくらい個人主義で……2人でずっと遊んでても、片方が飽きるとあっさり別のことに切り換えてしまう。置いてかれるほうも全く気にしてないみたいだ。
さっきの、『俺』って言ってたのはシナモン、だったっけ。
シナモンの隣で一緒に遊んでるんだか口喧嘩してるんだかよくわからないのがマロウ。
一人で遊んでるのがジンジャー。
ジャングルジムに登って遊んでるのがミントとセージ。
あと、仲良く本を読んでるのが……ローレルとタイム……あ、あれは違うかな。一人で本を読んでるローレルに、一方的に構ってるのがタイム、か。初等学校にもいたよな、一人でいる奴を構って何とか周りに溶け込まそうとする奴ってのが。
この分だと、すぐって言ったら無理だけど、数日もすれば区別がつくようになるだろう。
……しっかし、暇だな。俺も雑誌なり本なり持ってこないと時間つぶせないかもしれない。でも、私物の持込は許可を取らなきゃいけないって契約書には書いてあったし……毎日許可をもらうのも面倒だしなぁ。
……どた。
落下物の音がして、俺はぎょっと顔を上げる。
ジャングルジムの下で子供が倒れていた。
「お……おい」
慌てて俺はそばに駆け寄る。
小さい身体を抱きかかえると──寝て……る?
「……あ。マットも驚いた」
ミント、だっけか。子供にしては随分と冷静な声で言う。
「……も?」
「リュシィも最初、驚いた。でも、セージ、寝てるだけだから」
そういうとミントも、あーふ、と大きいあくびをした。
「今日、昼間、仕事だったからちょっと眠たいんだ……仕事っていっても、線つないだりとかだけど」
……仕事? 線?
頭は疑問符だらけだが、とりあえずただ眠ってるだけ、というのは理解できた。呼吸も規則的だし。
しょうがないな。こいつも運んでやるか。
抱えていた身体をそのまま持ち上げ、ベッドまで運ぶ。
うわ、軽いし柔らかい。……まるでぬいぐるみみたいだ。違うのは温かいということくらいか。子供は基礎体温が高いって言うからな。
ひとまず、仰向けに寝かせてシーツをかけてやると、すぐにごろんと横向きになって、すーすーと寝息を立てていた。
改めて先程まで座っていた椅子に戻り……ぐるりと部屋の全景を見回す。
窓のない、閉鎖された空間。
おもちゃこそたくさん置いてあるけど……駆け回れる広さもあるけれど。
ここのイメージは……『檻』、だ。
……俺は、ここにいられなくなった、と言った彼女の気持ちが……わかったような気がした。
†
「リュシュカ」
モニターだらけの小さな部屋。
頬杖ついて、子供達の部屋の様子を見ていた女性が、ゆっくりと振り返る。
「彼、どう?」
「特に……何も教えてないから、ごく普通に見えるわね」
それだけ答えて、彼女はもう一度モニターに視線を戻す。
「そう」
声をかけた女性も、彼女の後ろから屈んで同じモニターを覗き込んだ。
「それにしちゃ、やたら未練たっぷりな後姿だったわよ。……本当は、あの子達から離れるの、嫌だったんじゃない?」
「まさか」
苦さを含ませて、彼女は笑う。
「あまりあの子達に関わり過ぎるのは──科学者として、よくないわ。いざというとき、思いきることができなくなるもの」
「そうね」
「そうよ」
彼女は、返事と共にモニターを切って──席を立ち上がる。
「さて、本当に帰るわ。うちの子も待ってるし」
「お疲れ様」
「また明日」
小さく手を振り……彼女は優雅に鞄を下げ、扉を出てゆく。
──あの子達と離れたくなかったなんて──まさか。