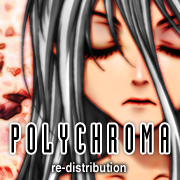杁傜傟偨墿崹嘥丗GateOdyssey丗novels乥憂嶌彫愢廤抍CRAFTWORX乮僋儔僼僩儚乕僋僗乯
杁傜傟偨墿崹嘥
Silvery eyes
丂戞擇攇偑棃傞婥攝偼側偄丅
丂壌偼偦偺応偐傜備偭偔傝偲婲偒忋偑傞偲丄廃埻傪娤嶡偡傞丅
丂偨偩惷庘偑巟攝偡傞嬻娫丅暡嵱偝傟偨壠嬶丅彴偵偼恖岺揑偵拝怓偝傟偨僇儔僼儖側揰偑嶶傜偽偭偰偄偨丅偁傟偼乧乧栻偐丠
丂椻偨偄奜婥偑擖傝崬傫偱偔傞丅暻偵偼嫄戝側晽寠偑奐偒丄偓傝偓傝偺偲偙傠偱寶暔偼偦偺崪慻傒傪曐偭偰偄偨丅
丂傕偲傕偲嫮搙偵偼晄埨偺偁偭偨寶憿暔偺巆奫偩丅奜偵弌傞偺偼婋尟偩偑丄曵傟傞偺傕帪娫偺栤戣偩傠偆丅
丂奨偺拞墰晹偺寶暔偵偼丄抧壓偺嬻娫偑巆偝傟偰偄偨偼偢偩丅斵彈偩偗偱傕偦偙傊摝偑偝側偗傟偽丅
乽儕儏僔儏僇偝傫乿
丂傑偩彴偵暁偣偨傑傑偺斵彈偵惡傪偐偗傞丅斵彈偼備偭偔傝偲婄傪忋偘劅劅偦偺傑傑恎懱傪婲偙偟偨丅
丂憮偞傔偨昞忣丅恔偊傞惡偱丄壌偵恥偹偨丅
乽傾僯僞偼丠乿
丂斵彈偺埵抲偐傜偦偺斷偺岦偙偆偼尒偊側偄丅壌偼墴偟栙傝劅劅惷偐偵庱傪墶偵怳偭偨丅
乽偳偄偰両乿
丂梊憐奜偺椡偵墴偝傟丄亀偦傟亁傪斵彈偺帇奅偐傜幷偭偰偄偨壌偺恎懱偼偡偙偟墶偵偢傟偨丅
乽傾僯僞乧乧丠乿
丂偐偡傟傞惡丅巭傔傞娫傕側偔斵彈偼斷偩偭偨応強偵嬱偗婑傝丄悢廫僉儘偼偁傞揝惢偺暘岤偄偦偺巆奫傪曅庤偱彴偐傜堷偒攳偑偡丅
乽傾僯僞乿
丂斵彈偼曵傟棊偪傞傛偆偵偦偺応傊嵗傝崬傫偩丅
丂壌偼偟偽傜偔偦偺條巕傪尒偮傔偰偄偨偑劅劅偦偭偲嬤婑傝丄尐偵庤傪抲偄偨丅
丂屘恖偵偼怽偟栿側偄偑丄崱偼偦偺巰傪搲傓帪娫偑側偄丅
乽寶暔偑曵傟傞偐傕偟傟傑偣傫丅奜傊弌傑偟傚偆乿
丂斵彈偼備偭偔傝偲庱傪嵍塃偵怳偭偨丅
乽寵乿
乽偙偙傪棧傟傑偡乿
丂柍棟傪彸抦偱斵彈偺朤偵孅傫偱偦偺庤傪捦傓丅斀幩揑偵堷偐傟傞榬丅
乽偩偭偰丄傾僯僞偑乿
乽儕儏僔儏僇偝傫両乿
丂壌偼嫮堷偵斵彈偺恎懱傪堷偒婑偣傞偲丄寉偔杍傪扏偄偨丅
丂戝偒側摰丅嬃偒偲壗偐偑崿偞傝偁偭偨昞忣丅劅劅嫰偊丅
丂壌偼扏偄偨杍偵丄彾傪揧偊傞丅
乽嵪傒傑偣傫乿
丂偦偺傑傑丄摦偐側偄斵彈傪書偒婑偣偨丅
乽乧乧儅僢僩偝傫乧乧丠乿
乽偍婅偄偟傑偡乿
丂斵彈傪書偔榬偵椡傪偙傔傞丅
乽壌偼丄栚偺慜偵偄傞恖傪尒幪偰傞偙偲偩偗偼偱偒傑偣傫乿
丂乧乧傑偟偰丄偦傟偑偁側偨偱偁傞側傜偽丅怱偺拞偱丄偦偭偲尵偄揧偊傞丅
丂偳偺偔傜偄偦偆偟偰偄偨偩傠偆偐丅抁偄帪娫偺偼偢偩偑丄偦傟偼偲偰傕挿偔姶偠傜傟偨丅
乽劅劅側偝偄乿
丂嫻嫋偵棊偪偨恔偊傞惡偱丄壌偼榬偺椡傪夝偄偨丅
乽偛傔傫側偝偄乧乧乿
丂壌偼備偭偔傝庱傪墶偵怳傞丅
乽偁側偨偑幱傞偙偲偠傖側偄乿
丂棫偪忋偑傝斵彈偺庤傪堷偔偲丄摢傪椪愴忬懺偵愗傝懼偊傞丅
丂崱偺朇寕偵巊梡偝傟偨傕偺偼丄懳暔儔僀僼儖偺椶偐丅埿椡偑寘堘偄偱偼偁傞偑丅
丂揋偑傕偟偙偺応強偵愮恖嬤偄恖娫偑偄傞偙偲傪抦偭偰偄偰丄偐偮偙偪傜偺焤柵傪慱偭偰偄傞偲偟偨側傜偽丄崱偺朇寕偱慡偰寛偣傜傟傞偲偼巚偭偰偄側偄偩傠偆丅
丂偙偺梊應偑惓偟偄偺側傜丄崱搙偼抏枊偺栐偐傜摝傟偨恖娫傪憒摙偵棃傞丅偙偙傑偱曪埻傪弅傔傞偺偵1帪娫掱搙偼偐偐傞偲偟偰乧乧30乣40暘偺娫偵壜擻側尷傝偺惗懚幰偲崌棳偟丄彮偟偱傕埨慡側応強傑偱桿摫偟側偗傟偽丅鏢鏞偟偰偄傞帪娫偼側偄丅
乽儕儏僔儏僇偝傫乿
乽偼偄乿
丂斵彈偼偐偮偰偺摨椈偩偭偨彈惈偺巔偵栚傪棊偲偟劅劅儀僢僪偺巆奫偐傜僔乕僣傪堷偒敳偔偲偦偺恎懱偵偦偭偲偐偗傞丅
乽劅劅峴偒傑偟傚偆乿
丂偦偟偰丄崱搙偼壌偺栚傪尒偰偟偭偐傝偲偦偆尵偭偨丅
丂奜傊弌偰丄傑偢崱屻偺峴摦傪懪偪崌傢偣傞偙偲偵偡傞丅
乽儕儏僔儏僇偝傫偵偼惗懚幰偺妋擣偲桿摫傪偍婅偄偟傑偡乿
乽偗偳乧乧乿
乽嫲傜偔廝寕幰偼亀Kitten亁偑偙偙偵偄傞偙偲傪抦偭偰偄傞傫偱偡丅偙偙偵偄傞幰払偺側偐偱堦斣偺嫼埿劅劅偁偄偮傜偵崌傢偣偰偙偺峌寕傪巇妡偗偰偒偨乿
丂抏憅偺悢傪妋擣偟側偑傜懕偗傞丅
乽偩偐傜堦斣婋尟側偺偼偁偄偮傜偺嫋偱偡丅偦偪傜偵偼壌偑峴偒傑偡乿
丂斵彈偑偼偭偲偟偨婄偱壌傪尒偨丅
丂偦偺婄偑備偭偔傝偆偮傓偒乧乧晄埨偦偆側昞忣偵曄傢傞丅
乽暘偐傝傑偟偨乿
乽偍婅偄偟傑偡丅婥傪偮偗偰乿
乽乧乧儅僢僩偝傫偙偦乿
乽戝忎晇偱偡傛乿
丂埨惪偗崌偄偵夁偓傞偐偲帺殅婥枴偵巚偆丅偩偑偦偺傛偆偵偟偐曉帠偺偟傛偆偑側偄丅
乽偁偺乧乧乿
乽偼偄乿
丂曉帠偲偲傕偵婄傪忋偘偨搑抂劅劅
乽偁偺丄巹乧乧偁偲偱儅僢僩偝傫偵恥偹偨偄偙偲偲偐尵偄偨偄偙偲偲偐嶳偺傛偆偵偁傝傑偡偐傜乿
丂戝偒側摰偑壌傪嵘傒偮偗偰偄偨丅
乽偩偐傜丄偦偺劅劅栠偭偰偙側偒傖偩傔偱偡偐傜乿
丂偦傟偩偗傪尵偆偲丄斵彈偼奨偺拞墰傊偲憱傝弌偡丅
丂堦弖曫婥偵偲傜傟劅劅
乽偼偄乿
丂宧楃偟偰丄壌偼廻幧偺曽傊嬱偗弌偟偨丅
乽柍條偩側乿
丂儔儞僌偑欔偔丅
乽壗偐嬄偄傑偟偨偐丄僿儖丒儔儞僌乿
丂嬤偔偵嵗傞懱奿偺椙偄抝偑栤偄曉偡丅
丂偙偙偼忋嬻1枩儊乕僩儖傪廃夞旘峴偟懕偗傞嫄恖峲嬻婡偺拞丅AI惂屼偺柍恖愴摤婡40婡偵庣傜傟傞丄墷廈寳偺孯帠揑椡偺梫偱偁傝偦偺嫼埿偵傛偭偰墷廈慡搚傪寢傃偮偗傞灦偱偁偭偨丅
丂儔儞僌偺帇慄偼惓柺偵偁傞2偮偺儌僯僞乕偺偆偪亀嬻敀抧懷亁偲屇徧偝傟傞応強偺忬嫷偵屌掕偝傟偰偄偨丅
乽柍條偩偲尵偭偨乿
丂旲敀傫偩抝偺昞忣偵峔傢偢丄儔儞僌偼尵梩傪懕偗偨丅
乽偙傫側柍悎側壩婍偺椡傪庁傝偹偽峌寕偡傜傑傑側傜傫丅儗儀儖4埲壓偺傾僋僙儔偼丄巹偺棟憐偐傜偐偗棧傟偨僋僘偩乿
乽偙傟偩偗偺愴摤擻椡傪帩偮暫巑傪偟偰偁側偨偼亀僋僘亁偲嬄傞偺偐丠乿
丂抝偑偦偺尵梩傪暦偒欓傔傞丅
乽偦偆偩丅幪偰嬵偵巊偭偰偄偨偩偄偰寢峔偩傛丅乧乧偁偲堦寧偁傟偽丄亀僛僯僗僛傾亁偑儘乕儖傾僂僩偟偰偄偨傕偺傪乧乧乿
乽亀僛僯僗乧乧亁側傫偱偡丠乿
乽孨偵偼抦傞尃棙偑側偄丅巹偼僨乕僞傪帩偪婣傟傟偽偦傟偱偄偄丅亀椺亁偺弨旛傕偁傞偺偩傠偆丠丂偝偭偝偲撍擖偝偣偨傑偊乿
丂堄偵夘偡傞條巕傕側偔丄儔儞僌偑尵偄幪偰偨丅抝偼晄夣偦偆偵儔儞僌傪尒偨偑丄偡偖嬤偔偺僆儁儗乕僞偵恥偹傞丅
乽忬嫷奐巒傑偱偼乿
乽偁偲5暘30昩偱偡乿
丂榬帪寁傪偪傜偭偲傒偰丄抝偼僼儘傾偺壓巑姱偵捠払偡傞丅
乽偙偪傜偺梡堄偼惍偭偨丅抧忋偺僋乕僨僞乕晹戉偵捠払偣傛乿
丂摦偒弌偡廃埻偵峔傢偢丄儔儞僌偼儌僯僞乕偺條巕傪嬅帇偟懕偗偰偄偨丅
丂摉弶亀幚峴幰乮僄僌僛僉儏乕僞乯亁奐敪偺僀僯僔傾僥傿償傪偲偭偰偄偨偺偼戞堦庬偩偭偨丅悽奅揑堚揱巕岺妛偺尃埿偱偁傞償傿儖僿儖儉=儈儔乕攷巑傪屭栤偵寎偊丄惛椡揑偵偦偺奐敪傪悇偟恑傔偰偄偨丅
丂偦偺尃埿偼亀僸儏僎儖儀儖幚尡亁偲屇徧偝傟偨偁傞寁夋偺幐攕偵傛傝幐傢傟傞偙偲偲側傞丅
丂2擭慜偺7寧20擔丄偦偺幚尡偼奐巒偝傟偨丅
丂code*A偲徧偝傟偨偦傟偼丄僸僩偺帩偮帺屓嵞惗擻椡傪嬌尷傑偱崅傔傞偙偲偺偱偒傞僸僩愼怓懱枹敪尰場巕亀A亁偺奐曻偵偁偭偨丅慖傃敳偐傟偨桪廏側慺抧傪帩偮尡懱偵亀傾僋僙儔丒償傿儔僗亁偲傛偽傟傞摿庩側僾儘僌儔儉丒儀僋僞乕傪怉偊偮偗丄DNA傪屻揤揑偵彂偒姺偊傞偙偲偱丄僸僩偺擻椡傪梱偐偵挻偊偨暫婍偲偟偰偺恖椶傪嶌傝弌偡劅劅
丂尡懱偵偼亀塧亁偲偟偰僸儏僎儖儀儖偵廤傔傜傟偨惌帯揑擄柉偳傕傪梌偊丄偦偺惉壥偵傛傝code*A偼亀傾儘儔僂儚亁偵懳峈偡傞暫婍偲偟偰検嶻偝傟偰偄偔偼偢偩偭偨丅
丂偟偐偟尡懱偼扤傂偲傝偲偟偰惗偒巆傜側偐偭偨丅
丂屻揤揑偵DNA傪彂偒姺偊傜傟偨恖娫払偼棟惈傪幐偄朶憱偟丄惂屼偱偒側偄僸僩側傜偞傞亀壗偐亁傊曄杄偟偰偄偨丅
丂寢壥丄尡懱偺張暘偼拲栚偡傜偝傟偰偄側偐偭偨戞嶰庬偑悇偟恑傔傞code*E劅劅亀Kitten亁偵埾偹傜傟丄偦偺惉岟偵傛傝僀僯僔傾僥傿償偼戞嶰庬傊偲堏摦偡傞丅償傿儖僿儖儉=儈儔乕攷巑偺柡偲徧偡傞偁偺亀恖宍亁偑亀Kitten亁偺巜婗傪峴偭偰偄偨偲偄偆偺偩偐傜丄旂擏埲奜偺壗幰偱傕偁傞傑偄丅
丂尃埿傪幐偭偨戞堦庬偺儊儞僶乕偼彊乆偵偦偺悢傪尭偠偰偄偔偙偲偵側傞丅
丂巹偼偦傫側戞堦庬偵巆偭偨堦恖偩偭偨丅
丂峴偔偁偰偑側偐偭偨栿偱傕code*A偵屌幏偟偨栿偱傕側偄丅
丂巹偵偼偐偮偰偺code*A傪婎偲偟丄撈帺偺棟榑傪壛偊偨怴偨側亀傾僋僙儔峔憐亁偑偁偭偨偺偩丅
丂亀Kitten亁偑帩偮亀摿惈亁偲屇偽傟傞擻椡偼嬼慠偵傛傞晹暘偑梋傝偵傕戝偒偄丅擻椡傪奐壴偱偒側偐偭偨僥僗僩僞僀僾偼尒愗傝傪偮偗傜傟偨帪揰偱亀幏峴幰乮僷僯僢僔儍乕乯亁偲屇偽傟傞惓懱晄柧偺傾儞僠丒償傿儔僗丒儐僯僢僩偵傛傝徚媝偝傟傞丅壗昐懱偲嶌傜傟側偑傜丄幚梡偵懴偊傜傟傞偲偝傟偨偺偼傢偢偐7懱偵偡偓側偄丅偩偑巹偺亀傾僋僙儔峔憐亁側傜丄桪傟偨儌僲偑惗傑傟傞妋棪偙偦摨偠側偑傜丄愗傝幪偰傞儌僲偱偡傜偙偆傗偭偰桳岠偵妶梡偱偒傞丅偳偪傜偑傛傝桳塿偱偁傞偐側偳丄堦栚椖慠側偼偢偩丅
丂亀僸儏僎儖儀儖幚尡亁偱巊梡偝傟偨慺懱偼婛偵惉挿偡傞梋抧偺側偄惉恖抝巕偩偭偨丅偩偐傜偙偦彂偒懼偊傜傟偨DNA傪庴偗晅偗偢嫅愨斀墳傪婲偙偟丄帺柵偟偰偄偭偨丅側傜偽偨偭偨堦恖丄尩慖偟偨惉恖慜偺僸僩偺DNA偺彂偒懼偊傪峴偄丄惗偒巆偭偨慺懱傪僋儘乕僯儞僌偡傟偽偄偄丅
丂偙偆偟偰丄code*A'偲柤偯偗傜傟偨偦偺寁夋偼奐巒偝傟偨丅
丂嫮堷偵悇偟恑傔摦偒弌偟偨偦偺撪梕偵恖堳偼偝傜偵搼懣偝傟丄戞堦庬偵偼code*A'偵巀摨偡傞庒偄尋媶幰払偩偗偑巆偭偰偄偔偙偲偲側傞丅
丂柺巕側偳偳偆偱傕偄偄丅傛偆傗偔斵彈払亀傾僋僙儔亁偑丄抧傪嬱偗嬻傪晳偆擔偑朘傟偨偺偩丅
丂尒偰偄傞偑偄偄丅
丂偙偺棟榑偩偗偑亀偁偺懚嵼亁偵懪偪彑偰傞桞堦偺恀棟側偺偩偲丄偙偙偱徹柧偟偰傒偣傞丅
乽彮彨乿
丂抧忋丄庱搒拞墰晅嬤偺楬抧棤丅
乽亀償傽儖僴儔亁傛傝忬嫷奐巒偑揱払偝傟傑偟偨乿
乽乧乧傢偐偭偨乿
丂楢棈偡傞惡偵実懷揹榖偱曉帠傪偟偨偺偼丄庒偄惵擭彨峑偩偭偨丅
丂偦偺朤傜偵偼丄嬧敮偺彮彈偑堦恖儃僨傿乕僗乕僣偵恎傪曪傒樔傓丅偝傜偵偦偺廃埻偵偼庒偄暫巑払偑10悢恖斵傪庢傝埻傓傛偆偵棫偭偰偄偨丅
乽0930傪帩偭偰抧忋晹戉偺嶌愴傪奐巒偡傞丅劅劅亀棟憐傪変偑庤偵亁乿
乽棟憐傪変偑庤偵乿
丂婘偺忋偵偼2枃偺幨恀偑傓偒弌偟偺傑傑暲傋傜傟偰偄偨丅
丂傾儎偼偠偭偲偦傟傪尒偮傔偰偄傞丅
丂嶐擔憲傜傟偰偒偨曬崘儊乕儖偺拞偵丄儔儞僌攷巑偑儕儏僔傿偲尵偄憟偭偰偄偨偲偄偆巪偺婰嵹偑偁偭偨丅
丂僇僞儕僫=僶僂傾乕丅斵彈偼埲慜偐傜儕儏僔傿傪揋帇偟偰偄傞愡偑偁偭偨丅屻偐傜偺擖嬊偱偁傞偵傕娭傢傜偢徃恑傪敳偐傟偨偲偄偆偙偲傕偁傞偩傠偆偑丄偦傟偵懳偟偰儕儏僔傿帺恎偵壗偺姶奡傕側偄偲偄偆偲偙傠偑婥偵忈傞偺偩傠偆丅
丂巇曽偑側偄偙偲偩丅儕儏僔傿偼壗傕朷傫偱偄側偄丅戞嶰庬偵棃偨偺傕丄巹偺梫惪偵墳偠偰偔傟偨偩偗側偺偩丅
丂偩偐傜偙偦壗偲偐偟偰傗傝偨偄偲偄偆婥帩偪偼偁傞偺偩偑丄偦偙偱巹偑岥傪弌偣偽偦傟傪亀傂偄偒亁偲姶偠傞幰傕彮側偔側偄偩傠偆丅
丂晛抜側傜摢捝偺庬偩偑丄崱夞偺偦偺曬崘偵揧偊傜傟偨僨僕僞儖僨乕僞偵暿偺壙抣偑尒弌偝傟偨丅
丂弮敀偲尒暣偆偽偐傝偺嬧敮偲愒偄摰傪帩偮彮彈丅嫲傜偔愭揤揑側怓慺寚懝劅劅傾儖價僲偩傠偆丅庤慜偵偄傞僗乕僣巔偼戞堦庬偺儘儀乕儖=儔儞僌攷巑偲巚傢傟傞丅
丂堦弿偵暲傋傜傟偨傕偆堦枃偺幨恀偵偼塟擇偮偺彮彈丅偨偩偟偙偪傜偼僾儔僠僫僽儘儞僪偺敮偲惵偄摰偺帩偪庡偩丅
丂偙偺幨恀偼戞堦庬偱嶣塭偝傟偨傕偺偩偲尵傢傟偰偄傞丅僨乕僞傪嵦庢拞側偺偩傠偆丄敀偄娧堖傪偐傇傝堉巕偵崢妡偗偰壗偐傪懸偭偰偄傞傛偆側條巕偩丅
丂僀乕儕儎=儕僸僥儖丅儘僔傾偺偲偁傞惌晎婡娭偑挿擭偵搉傝旈摻偟懕偗偨悢彮側偄code*A偺庤偑偐傝偺傂偲偮偲偝傟偰偄傞丅
丂4擭慜偵偦偺抁偄惗奤傪暵偠丄愭揤惈偺晄帯偺昦偲堷偒姺偊偵恖側傜偞傞擻椡傪帩偭偰惗傑傟偨偲偝傟偨彮彈劅劅
丂傾儎偼婘偺庴榖婍傪庢傞偲偡偖偵弌偨尋媶堳偵恥偹傞丅
乽掕帪楢棈偼丠乿
乽傑偩棃偰偄傑偣傫乿
丂旣傪傂偦傔傞丅
乽偍偐偟偄傢偹乧乧乿
丂掕帪楢棈偑擖偭偰偒偨傜丄偡偖揹榖傪夞偡傛偆偵崱挬堦斣偱僗僞僢僼偵廃抦傪峴偭偰偄偨丅
丂偩偑6帪娫偛偲偵擖傞偼偢偺掕帪楢棈偼梊掕帪娫偺屵慜9帪傪30暘偡偓偨崱傕擖偭偰偒偰偄側偄丅
乽嵜懀偟傑偡偐丠乿
丂恥偹曉偡尋媶堳偵丄斲偲摎偊傞丅
乽巹偑擖傟傞傢乿
丂傾儎偼実懷揹榖傪庢傝弌偟儃僞儞傪慺憗偔墴偟偨丅柍婡幙側怣崋壒偺偺偪丄亀寳奜亁偺儊僢僙乕僕偑棳傟傞丅
丂実懷揹榖傪偨偨傒丄僨僗僋偺庴榖婍傪偲傝抁弅斣崋傪墴偡丅斀墳偼摨偠偩丅
乮劅劅傑偝偐乯
丂寉偔怬傪姎傒拡傪偵傜傒偮偗傞丅
丂傾儎偼庴榖婍傪扏偒偮偗傞傛偆偵栠偡偲棫偪忋偑偭偨丅
丂僨僗僋偺揹榖偼旕忢梡偺塹惎夞慄偵宷偑偭偰偄傞丅偦傟偑捠偠側偄偲偄偆偙偲偼丄壗傜偐偺嫮椡側捠怣朩奞偑峴傢傟偰偄傞壜擻惈偑崅偄丅
丂楲壓偵弌偰丄嵞傃実懷揹榖傪庢傝弌偟暿偺斣崋傪墴偡丅
丂僐乕儖壒偼偟偽傜偔柭傝懕偗劅劅10僐乕儖栚偱墳摎偑婣偭偰偒偨丅
乽偼偄乿
丂偟偽傜偔栙傝崬傫偩屻丄恥偹傞丅
乽乧乧僌僂僃儞丠乿
丂捑栙偑栤偄傪峬掕偟偰偄偨丅傾儎偼懅傪揻偔丅
乽偲偄偆偙偲偼偁偺僶僇偼偄側偄偺偹乿
乽劅劅傾儎偪傖傫偐乿
乽乧乧偍屳偄偄偄擭側傫偩偐傜丄亀偪傖傫亁偼傛偟偰乿
丂偄傜偮偄偨傛偆偵傾儎偑尵偄幪偰傞丅
乽埆偄丄偮偄側丅偁偄偮傕娫偑埆偄側丄偙傫側偲偒偵尷偭偰乧乧乿
乽乧乧傎傫偲偵丄偙傫側偲偒偵尷偭偰偹乿
丂戝偒偔懅傪揻偔丅
乽偙偺揹榖偼丄偁偄偮偵棅傑傟偰梐偐偭偰偄傞丅偲偄偆偙偲偼丄壗偐偁偭偨偭偰偙偲側傫偩側乿
乽亀嬻敀抧懷亁偲楢棈偑庢傟側偔側偭偨傢丅劅劅偍偦傜偔偙偙傕帪娫偺栤戣偹乿
乽偁偦偙偵偼妋偐僸儏僎儖儀儖偺惗偒巆傝偑偄偨側乿
乽偊偊乿
乽戝帠側徹嫆偩丅惗偒巆偭偰偔傟傟偽偄偄傫偩偑乿
乽惗偒巆偭偰偔傟側偄偲崲傞傢乿
丂斵偼嫸尵帠審傑偱堷偒婲偙偟偰丄亀偙偪傜懁亁偵妋曐偟偨恎暱偩丅
丂摨帪偵夋嶔偝傟偰偄偨丄儕儏僔傿傪戞嶰庬偺慜慄偐傜堷偒棧偡偲偄偆栚揑偑悑峴偱偒側偐偭偨偺偼岆嶼偩偭偨偑乧乧
乽晹戉傪亀嬻敀抧懷亁偲偦偪傜偵岦偐傢偣傞丅偦傟傑偱壗偲偐劅劅乿
丂寈曬偑柭傞丅摨帪偵宷偑偭偰偄偨実懷偺捠榖偑晄夣側僲僀僘偲偲傕偵愗傟偨丅
乮劅劅巒傑偭偨傢偹乯
丂傾儎偼実懷揹榖傪偦偺傑傑偟傑偄崬傓偲帺暘偺僆僼傿僗偵栠傝丄埨慡梡偺僷僢僉儞偺偮偄偨僗僀僢僠傪奜偡帪娫傕惿偟偄偲偽偐傝偵墸傝偮偗傞丅墴偟崬傑傟偨僗僀僢僠偑彫偝偔柭偭偨丅
乽娰撪慡堳偵崘偖丅忬嫷亀C-2亁丅儅僯儏傾儖偵廬偄恦懍偵峴摦偡傞傛偆偵丅偨偩偟丄柍棟側傜掞峈偣偢搳崀偟側偝偄丅柦傑偱偼扗傢傟側偄偼偢傛丅摨帪偵尰帪崗傪埲偭偰慡怑堳偺夝屬傪捠払偟傑偡丅
丂崱傑偱偁傝偑偲偆丅傒傫側丄巰側側偄偱丅劅劅埲忋乿
丂惡傪挘偭偰堦婥偵尵偆偲丄懅傪揻偔丅
乮廝寕幰偑恖摴揑慬抲傪偲偭偰偔傟傟偽丄偩偗偳乯
丂怬傪姎傓丅姰慡偵屻庤偵夞偭偨丅撉傒娫堘偊偨帺暘偺柍擻偝偵揻偒婥偑偡傞丅
丂亀嬻敀抧懷亁偵偼Kitten偑偄傞丅偙偪傜偺惂埑偵梫偡傞悢廫攞偺愴椡偑拲偓崬傑傟偰偄傞偵堘偄側偄丅弌岦偄偨娭學幰偺傎偲傫偳偼巰偸丅
丂彮側偔偲傕巹偼償傽儖僴儔偵偼峴偗傑偄丅
丂傗傞偣側偄婥帩偪傪書偊偨傑傑婘偺堷偒弌偟偐傜岇恎梡偺廵傪夰偵擖傟偨丅栶偵棫偮偲傕巚偊側偄偑丄婥媥傔偔傜偄偵偼側傞偩傠偆丅
乽劅劅巹傕峴偐側偔偪傖偹乿
丂傾儎偼惷偐偵帺幒傪弌傞偲斷傪暵傔乧乧帺傜偼儅僯儏傾儖偵媡傜偄丄寶暔偺墱傊偲岦偐偭偰偄偭偨丅
丂庱搒儀儖儕儞丅
丂夛媍幒偺斷偑棎朶偵墴偟奐偐傟偨丅
乽乧乧幐楃乿
丂偦偺惡偱丄幒撪偺傎傏慡堳偑怳傝曉傞丅
丂廫悢恖偺抝惈払丅
丂偞傢偮偒巒傔偨幒撪傪丄墱偐傜尰傟偨惵擭彨峑偺堦尵偑捔傔偨丅
乽側偐側偐擬拞偟偨媍榑偺傛偆偱丅寢峔側偙偲偱偡乿
乽壗偩偹孨偼乿
丂擖傝岥晅嬤偵嵗偭偰偄偨抝偑扤壗偡傞丅
乽僈乕僪儅儞偼壗傪偟偰偄傞乿
乽柊偭偰偄傑偡傛丅擇搙偲婲偒忋偑傞偙偲傕側偄偱偟傚偆偑乿
丂僗乕僣巔偺壗恖偐偑搑榝偭偨昞忣傪尒偣劅劅屳偄偺婄傪尒崌偡丅
乽劅劅僼儗僪儕僸=僆僢僩乕彮彨乿
丂偦偺拞偐傜堦恖偺媍堳偑曕傒弌傞丅
乽乧乧慶晝偺柤傪偐偭偰塸梇婥庢傝偐丅巆擮偩偑丄変乆偼埨偭傐偄棟憐偵悓偆庒憿嫟偺尵偄側傝偵側傞傎偳惼庛偱偼側偄乿
乽偝偡偑丄崙傪摦偐偡幰偺婥奣偼偦偆偱側偔偰偼乿
丂敄偔徫偆惵擭彨峑偺慜偵彮彈偑棫偭偨丅
丂曕傒弌偨媍堳偺庤庱傪捦傓丅
乽偱偡偑丄掞峈偼柍堄枴偱偡丅劅劅傗傟乿
丂彮彈偺嵶偄庤偑媍堳偺庤庱偺忋傪捦傒忋偘傞丅
丂堦弖旲傪撍偔堎廘偲慚岝丅
丂師偺弖娫丄媍堳偺庤偼旾偐傜壓偑柍偔側偭偰偄偨丅
丂夛媍幒偵愨嫨偑嬁偒搉傞丅抝偼幐傢傟偨帺恎偺榬傪墴偝偊丄揮偘傑傢傞丅幒撪偵偄偨懠偺恖娫偼搥傝偮偄偨傛偆偵偦偺彮彈偺庤嫋傪嬅帇偟偰偄傞丅
丂彮彈偺巜愭偑撦偔岝偭偰偄偨丅
乽乧乧壗傪偟偨乧乧丠乿
丂惷庘傪忋偢偭偨惡偑攋傞丅
乽偁側偨偼掞峈偟側偄偺偱偡偐丠乿
丂彮彨偼偆偭偡傜偲徫偭偨丅
乽暿偵巭傔偼偟傑偣傫傛乿
乽摎偊傞婥偼側偄偲偄偆偙偲偐乿
乽尵偭偨偲偙傠偱丄偁側偨偨偪偵壗偑偱偒傞偲傕巚偊傑偣傫丅劅劅偦傟偵巹偼壈昦幰偱偡偐傜丄庤偺撪傪偝傜偡傛偆側偙偲偼偟傑偣傫傛乿
丂偦偺攚屻偱丄旈彂偲巚偟偒抝偑墱偵偄傞堦恖偵帹懪偪偟偨丅
乽戞嶰庬丄宷偑傝傑偣傫丅捠怣朩奞偱偡乿
丂幐堄偑揱攄偡傞丅
乽劅劅巇曽偁傞傑偄丅変乆傕搳崀偟傛偆乿
丂拞怱恖暔偲偍傏偟偒恖暔偑嬯廰偺昞忣偱愰尵偟偨丅
丂偦偙偐傜悢僉儘棧傟偨偲偁傞応強丅偦偺彮彈偼敀偄懅傪揻偒側偑傜寴楽側僎乕僩偺朤偵棫偭偰偄偨丅
乽尒偮偗偨乿
丂戞嶰庬尋媶強惓栧慜丅
丂暼偺嫮偄愒栄偺僔儑乕僩僇僢僩丄娽嬀偺岦偙偆偐傜擿偔戝偒側摰偼梒偝傪巆偟側偑傜傕抦惈偺崅偝傪巉傢偣傞岝傪廻偟偰偄傞丅
乽拝偄偨傛丄亀儀儕僼傽亁乿
丂斵彈偼屻傠傪怳傝曉偭偨丅
丂僉傿乧乧偲惡偲傕嬥懏偺鏰傒偲傕偮偐側偄壒偑偡傞丅暘岤偄斂晍偺傛偆側傕偺傪偐傇偭偨嫄恖偑斵彈偺屻傠偵偮偒廬偭偰偄偨丅
乽偙偙偱懸婡乿
丂婤慠偲偟偨惡偱柦椷偡傞偲丄嫄恖偼偦偺尵梩偵廬偆傛偆偵摦偒傪巭傔傞丅
丂斵彈偼惓栧傪擖傞偲丄僈儔僗挘傝偺尯娭傪擿偒崬傓丅
乽扤偐丄偄傑偣傫偐乿
丂儘價乕偲巚傢偟偒嬻娫偵偦偺惡偼彫偝偔偙偩傑偟偰徚偊偨丅
乽偍偐偟偄側乧乧崱擔偩偭偨偼偢偩偗偳乿
丂斵彈偼嫻億働僢僩偐傜実懷抂枛傪庢傝弌偟丄僗働僕儏乕儖傪妋擣偡傞丅
丂偠偭偲彫偝側夋柺傪嬅帇偟丄奧傪暵偠傞丅
乽壖偵杔偺儊儌偑儈僗偩偭偨偵偟偰傕丄恖偺婥攝偑慡偔側偄偺偼彮偟偍偐偟偄丅乧乧惷偐偡偓傞乿
丂斵彈偼嫄恖偺嫋傊栠傞丅偦偟偰丅
乽亀儀儕僼傽亁丄棃偄乿
丂嫨傇偲嵞傃僎乕僩傊偲憱傝弌偡丅
丂嫄恖偼寉偔偦偺恎傪恔傢偣傞偲丄柍悢偺儌乕僞乕壒傪嬁偐偣側偑傜彮彈偺屻傠傪捛偆傛偆偵備偭偔傝偲摦偒弌偟偨丅
丂恖婥偺側偄楲壓傪丄偁偨傝傪尒夞偟側偑傜曕偔丅
丂彮彈偲亀儀儕僼傽亁偺懌壒偩偗偑捠楬偵嬁偄偰偄偨丅嬻婥拞偵崿偠傞旝偐側揝嶬傔偄偨擋偄偑斵彈偺惛恄偵捾傪棫偰傞丅
乽乧乧巭傑傟亀儀儕僼傽亁乿
丂鏰傫偩儌乕僞乕壒偑惷巭偡傞偲惷庘偼偦偺怓傪峏偵擹偔偵偠傑偣傞丅
丂彮彈偼帺暘傕棫偪巭傑傝丄帹傪悷傑偟偨丅
丂墦偔劅劅偄傗寶憿暔偺墱偱姡偄偨攋楐壒偑偡傞丅
丂寉偔旣傪傂偦傔傞偲彮彈偼壒偺偡傞傎偆傊懌傪恑傔偨丅嫄懱偑屻傠偵廬偆丅
丂妏傪嬋偑偭偨偲偨傫丄孋偺捾愭偑壗偐偵傂偭偐偐偭偨丅
丂彮彈偼偦偺忈奞暔傪嬅帇偡傞丅
丂揝嶬偺擋偄傪傛傝擹偔傑偲偭偨偦傟偼丄暻偵傕偨傟偐偐偭偨彈惈偩偭偨丅庤偵偼壗傕帩偨偢丄摢忋偺暻偵偼愒偔昤偐傟偨暋悢偺捈慄丅
乽乧乧寵偄偩側乿
丂尵梩偼帺慠偵怬偐傜楇傟偨丅
丂偄偮偩偭偰杔傜偼棟晄恠傪墴偟偮偗傜傟丄摜傒偵偠傜傟傞丅
乽亀儀儕僼傽亁丄峴偔傛丅乧乧偦偙偱柊偭偰傞恖偼摜傑側偄傛偆偵偹乿
丂柦偠側偑傜彮彈偼恑峴曽岦傪偒偭偲尒偮傔傞丅
丂偦偺愭偵偼擇搙偲栚妎傔偸恖乆偺巔偑僆僽僕僃偝側偑傜偵楢側偭偰偄偨丅
丂壌偲巕嫙払偑怮攽傝偟偰偄偨寶暔偼怮彴偑偁偭偨1奒晹暘偑攋夡偝傟丄2奒晹暘偺宍傪偓傝偓傝巆偟偨傑傑壓偵捑傒偙傫偱偄偨丅
丂巕嫙払偼堦扷寶暔偺姠釯偺拞偵杽傕傟偨偑丄帺椡偱敳偗弌偟偨偲尵偭偰偄偨丅
丂偳偆傗偭偰敳偗弌偟偨偐偼丄帪娫偑側偄偙偲傕偁偭偰恥偄偰偄側偄丅偲傝偁偊偢懠偺儊儞僶乕偲崌棳偡傞偙偲偑愭寛偲峫偊偨偺偩丅
丂拞墰偺抧壓嬻娫傊栠偭偰偔傞偲丄拞偱偼摙榑偺恀偭嵟拞偩偭偨丅
乽愭崗偺峌寕偱婡嵽偺傎偲傫偳偑懝夡偝偣傜傟偨傢丅偄偭偨偄偳偆傗偭偰乧乧乿
丂曅曽偼妋偐僇僞儕僫偲柤忔偭偨彈惈丅傕偆曅曽偼儕儏僔儏僇偝傫偩丅
乽埲慜偐傜峫偊偰偄偨偙偲偑偁傝傑偡丅偙偺棟榑偑惓偟偗傟偽劅劅乿
乽婘忋偺嬻榑偩傢両乿
乽劅劅偁偺乿
丂壌偼愭偵巕嫙払傪擖傟傞偲丄偦偺偁偲傪懕偔傛偆偵奒抜傪崀傝乧乧儕儏僔儏僇偝傫偵惡傪偐偗偨丅
乽乧乧儅僢僩偝傫両乿
丂儕儏僔儏僇偝傫偑怳傝岦偔丅
丂僇僞儕僫忟偺尵梩偑偦傟傪巭傔傛偆偲偡傞偐偺傛偆偵偐傇偝偭偨丅
乽榖偼傑偩廔傢偭偰側偄傢丅偁側偨丄偦偺峫偊偑惓偟偔偭偰丄偙偙偵惗偒巆偭偨儊儞僶乕偑偪傖傫偲惗偒巆傟傞偭偰曐徹偑弌棃傞偺丠乿
丂夵傔偰拞偵偄傞恖悢傪悢偊傞丅偞偭偲50柤嫮偐丅
乽曐徹偼偱偒傑偣傫丅偱偡偑劅劅乿
丂儕儏僔儏僇偝傫偺惡偼彮乆庛傔偩丅
乽偩偭偨傜帪娫偺柍懯偱偟傚偆丅僞僀儉偵亀弬亁傪挘偭偰傕傜偭偰楿忛偟偨傎偆偑傑偩乿
乽偦傟偙偦柍懯偩偲巚偄傑偡傛乿
乽壗屘両乿
丂僇僞儕僫偝傫偺峌寕揑側岥挷偑偙偪傜傪岦偔丅
乽岦偙偆偺巚榝偑丄偙偙偵偄傞恖娫偺慡柵偵偁傞偐傜偱偡乿
丂壌偼嵞傃奒抜偵懌傪偐偗偨丅
乽偳偙傊峴偔偺丠乿
乽僟儊尦偺掞峈偵乿
乽懸偪側偝偄乿
丂僇僞儕僫忟偑壌傪堷偒巭傔傞丅廃曈偺彈惈払傕偞傢傔偒巒傔偨丅
乽彑庤側峴摦偼崲傞傢乿
乽偦偆傛丅偁側偨傪屬偭偰偄傞偺偼戞嶰庬丄偮傑傝巹払側偺傛乿
丂壌偼怳傝曉傞丅
乽乧乧傗傞偐傗傜側偄偐乿
丂傑偭偡偖丄斵彈傜傪尒傗傞丅
乽傗傞側傜扤偑丅劅劅帪娫偺柍懯偱偡丅慡柵偟偨偄側傜暿偱偡偑乿
乽壗傪乧乧両乿
乽偙偺傑傑偱偼巰偸偺傪懸偮偩偗偱偡丅摦偄偰傕摨偠偐傕偟傟傑偣傫偑劅劅惗偒巆傟傞偐傕偟傟傑偣傫乿
丂尵偄側偑傜丄怱偺拞偱嬯徫偡傞丅
丂亀柍堊偵偼巰偵偨偔側偄亁劅劅偦偺婥帩偪偑巰傊偲岦偐偆堄幆偵斀偟偰丄壌傪惗偒塱傜偊偝偣偰偒偨偲偄偆偺偵丅
丂偩偑丄壌偼壌偺婅偄偵懠恖傪姫偒崬傓偙偲傪嫋偡偙偲偑偱偒側偄丅
乽偁側偨丄壗傪尵偭偰偄傞偺偐暘偐偭偰偄傞偺乧乧丠乿
丂曫慠偲偟偨傛偆偵僇僞儕僫忟偑尵偆丅
乽孯恖偼偦偆偄偆惗偒暔偱偡傛乿
丂岥偺抂偵徫傒傪晜偐傋傞丅
丂偩偑彈惈払偺娽偼婃側偵壌偺尵梩傪嫅斲偟懕偗偰偄偨丅
乽傢偐傝傑偟偨乿
丂壌偼懅傪揻偔丅
乽偁偔傑偱傕媍榑偺忋偲偄偆偺偱偟偨傜丄側傞傋偔憗偔寛傔偰偔偩偝偄丅劅劅壌偼偦傟傑偱偺娫丄壗偲偐偙偙傪曐偨偣傑偟傚偆乿
丂嵞傃敪惗偟偨偞傢傔偒傪柍帇偟偰丄壌偼嵞傃抧壓嬻娫偺擖傝岥傪奐偗丄抧忋傊弌偨丅
丂嵒偲側偭偨姠釯偑晽偵忔偭偰旘傫偱偔傞丅晽偺壒偺崌娫偵惷庘偑昚偆丅
乽懸偭偰偔偩偝偄乿
丂攚拞偐傜挳偙偊偨惡偵壌偼彮偟峇偰偰怳傝曉偭偨丅
乽儕儏僔儏僇偝傫乧乧乿
丂儕儏僔儏僇偝傫偑巕嫙払傪楢傟丄屻傠偵棫偭偰偄偨丅
乽壗偟偰偄傞傫偱偡両乿
乽巹偵峫偊偑偁傞傫偱偡乿
乽壗偑乧乧乿
乽亀摦偗偽惗偒巆傟傞偐傕偟傟側偄亁乧乧偱傕丄偁側偨偼偦偺拞偵帺暘帺恎傪擖傟偰偼偄側偄偱偟傚偆丠乿
丂斀榑偟偐偗偨壌傪丄斵彈偼傑偭偡偖尒偮傔傞丅
乽惗偒傞偐巰偸偐偩傕偺丄崱峏墦椂側傫偐偟側偄傢乿
丂曉帠偵媷偡傞壌偵丄斵彈偼懕偗偨丅
乽尵偭偨偱偟傚偆丠丂巹偼偁側偨偵尵偄偨偄偙偲偑偁傞偺乧乧偩偐傜丄彑庤偵徚偊傜傟偨傜崲傞偺傛乿
丂堦曕偢偮丄嬤偯偔斵彈丅
乽偱傕崱偼偦偺榖傪偡傞帪偠傖側偄傢丅偩偐傜丄堦弿偵惗偒墑傃傑偟傚偆乿
乽偦傟偼乧乧柦椷偱偡偐丠乿
丂傛偆傗偔嶏傝弌偟偨尵梩偵丄斵彈偑旝徫傓丅
乽偦傟偑偍朷傒偱偟偨傜乿
丂偁偁丅劅劅偙偺恖偼丄壗偲側偔壌偺惛恄乮偙偙傠乯偺嵼傝曽偵婥偯偄偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅
丂揋傢側偄側丅壌偼嬯徫偱斵彈偵墳偊偨丅
乽劅劅亀Kitten亁傪婲摦偟傑偡丅偁偺巕払偺巜婗姱偵婱曽傪擟柦偡傞傢乿
丂斵彈偼儈儞僩傪庤彽偒偟偰屇傫偩丅偦偟偰丄壌偵庤傪嵎偟弌偡丅
乽儅僢僩偝傫丄偙傟偐傜儈儞僩偵偁側偨偺擼攇傪搊榐偟傑偡乿
丂嵎偟弌偝傟偨巜愭偵怗傟傞丅斵彈偼旝偐偵徫偭偰丄鏢鏞偡傞壌偺庤傪屌偔埇偭偨丅
乽儈儞僩乿
丂斵彈偺尵梩偵儈儞僩偑柍尵偱桴偒丄斵彈偺庤偲壌偺庤傪偲傞丅偦偺傑傑寉偔栚傪暵偠偨丅
乽乧乧壌偼壗傪偡傟偽乿
乽栚傪暵偠偰丅堄幆傪奐偄偰乿
乽奐偔乧乧丠乿
乽巹払偵堄幆傪岦偗傞傛偆側姶妎偱乿
丂寉偔栚傪暵偠傞丅
乽劅劅Shift乿
丂儕儏僔儏僇偝傫偺尵梩偑偡偭偲堄幆偵妸傝崬傓丅
丂巜愭偐傜擖傝崬傫偱偔傞亀擬亁偑恄宱傪梙偝傇傝偙偠奐偗丄榬傪捠偠偰愐悜傪骧鏦偟慡恎偵峴偒搉傞丅
丂偦傟偼丄愭掱婋婡傪抦傜偣偨偁偺堄幆偵崜帡偟偰偄偨傛偆偵巚偊偨丅
丂尵梩偵側傜側偄堄巚偑嵶偄棳傟偐傜朶椡揑側杬棳傊曄傢傞丅
乽乧乧乿
丂嫨傃傪忋偘偨偔側傞傎偳偺晄夣姶丅岮偵偙傒忋偘傞惡傪梷偊崬傓丅懱壏偑搑換傕側偄惃偄偱忋偑偭偰偄偔偺偑傢偐傞丅
丂尷奅偩丅劅劅偦偆巚偭偨弖娫丅
乽乧乧Anfang乿
丂斵彈偺師偺尵梩偲偲傕偵丄偦偺椡偺杬棳偼彊乆偵嵶偔側傝劅劅婯懃惓偟偄椡偺棳傟傊偲曄傢偭偰偄偭偨丅
丂斵彈偲儈儞僩偺庤偑棧傟傞丅
乽儈儞僩偼斵偺巜帵偑偁傞傑偱偙偺傑傑懸婡乿
丂桴偄偨儈儞僩偺摰偼丄晛抜偺怺椢傪扻偊偢丄偨偩柍婡幙側敀嬧偺偦傟偵愼傑偭偰偄偨丅
丂壌偼偦偺応偐傜備偭偔傝偲婲偒忋偑傞偲丄廃埻傪娤嶡偡傞丅
丂偨偩惷庘偑巟攝偡傞嬻娫丅暡嵱偝傟偨壠嬶丅彴偵偼恖岺揑偵拝怓偝傟偨僇儔僼儖側揰偑嶶傜偽偭偰偄偨丅偁傟偼乧乧栻偐丠
丂椻偨偄奜婥偑擖傝崬傫偱偔傞丅暻偵偼嫄戝側晽寠偑奐偒丄偓傝偓傝偺偲偙傠偱寶暔偼偦偺崪慻傒傪曐偭偰偄偨丅
丂傕偲傕偲嫮搙偵偼晄埨偺偁偭偨寶憿暔偺巆奫偩丅奜偵弌傞偺偼婋尟偩偑丄曵傟傞偺傕帪娫偺栤戣偩傠偆丅
丂奨偺拞墰晹偺寶暔偵偼丄抧壓偺嬻娫偑巆偝傟偰偄偨偼偢偩丅斵彈偩偗偱傕偦偙傊摝偑偝側偗傟偽丅
乽儕儏僔儏僇偝傫乿
丂傑偩彴偵暁偣偨傑傑偺斵彈偵惡傪偐偗傞丅斵彈偼備偭偔傝偲婄傪忋偘劅劅偦偺傑傑恎懱傪婲偙偟偨丅
丂憮偞傔偨昞忣丅恔偊傞惡偱丄壌偵恥偹偨丅
乽傾僯僞偼丠乿
丂斵彈偺埵抲偐傜偦偺斷偺岦偙偆偼尒偊側偄丅壌偼墴偟栙傝劅劅惷偐偵庱傪墶偵怳偭偨丅
乽偳偄偰両乿
丂梊憐奜偺椡偵墴偝傟丄亀偦傟亁傪斵彈偺帇奅偐傜幷偭偰偄偨壌偺恎懱偼偡偙偟墶偵偢傟偨丅
乽傾僯僞乧乧丠乿
丂偐偡傟傞惡丅巭傔傞娫傕側偔斵彈偼斷偩偭偨応強偵嬱偗婑傝丄悢廫僉儘偼偁傞揝惢偺暘岤偄偦偺巆奫傪曅庤偱彴偐傜堷偒攳偑偡丅
乽傾僯僞乿
丂斵彈偼曵傟棊偪傞傛偆偵偦偺応傊嵗傝崬傫偩丅
丂壌偼偟偽傜偔偦偺條巕傪尒偮傔偰偄偨偑劅劅偦偭偲嬤婑傝丄尐偵庤傪抲偄偨丅
丂屘恖偵偼怽偟栿側偄偑丄崱偼偦偺巰傪搲傓帪娫偑側偄丅
乽寶暔偑曵傟傞偐傕偟傟傑偣傫丅奜傊弌傑偟傚偆乿
丂斵彈偼備偭偔傝偲庱傪嵍塃偵怳偭偨丅
乽寵乿
乽偙偙傪棧傟傑偡乿
丂柍棟傪彸抦偱斵彈偺朤偵孅傫偱偦偺庤傪捦傓丅斀幩揑偵堷偐傟傞榬丅
乽偩偭偰丄傾僯僞偑乿
乽儕儏僔儏僇偝傫両乿
丂壌偼嫮堷偵斵彈偺恎懱傪堷偒婑偣傞偲丄寉偔杍傪扏偄偨丅
丂戝偒側摰丅嬃偒偲壗偐偑崿偞傝偁偭偨昞忣丅劅劅嫰偊丅
丂壌偼扏偄偨杍偵丄彾傪揧偊傞丅
乽嵪傒傑偣傫乿
丂偦偺傑傑丄摦偐側偄斵彈傪書偒婑偣偨丅
乽乧乧儅僢僩偝傫乧乧丠乿
乽偍婅偄偟傑偡乿
丂斵彈傪書偔榬偵椡傪偙傔傞丅
乽壌偼丄栚偺慜偵偄傞恖傪尒幪偰傞偙偲偩偗偼偱偒傑偣傫乿
丂乧乧傑偟偰丄偦傟偑偁側偨偱偁傞側傜偽丅怱偺拞偱丄偦偭偲尵偄揧偊傞丅
丂偳偺偔傜偄偦偆偟偰偄偨偩傠偆偐丅抁偄帪娫偺偼偢偩偑丄偦傟偼偲偰傕挿偔姶偠傜傟偨丅
乽劅劅側偝偄乿
丂嫻嫋偵棊偪偨恔偊傞惡偱丄壌偼榬偺椡傪夝偄偨丅
乽偛傔傫側偝偄乧乧乿
丂壌偼備偭偔傝庱傪墶偵怳傞丅
乽偁側偨偑幱傞偙偲偠傖側偄乿
丂棫偪忋偑傝斵彈偺庤傪堷偔偲丄摢傪椪愴忬懺偵愗傝懼偊傞丅
丂崱偺朇寕偵巊梡偝傟偨傕偺偼丄懳暔儔僀僼儖偺椶偐丅埿椡偑寘堘偄偱偼偁傞偑丅
丂揋偑傕偟偙偺応強偵愮恖嬤偄恖娫偑偄傞偙偲傪抦偭偰偄偰丄偐偮偙偪傜偺焤柵傪慱偭偰偄傞偲偟偨側傜偽丄崱偺朇寕偱慡偰寛偣傜傟傞偲偼巚偭偰偄側偄偩傠偆丅
丂偙偺梊應偑惓偟偄偺側傜丄崱搙偼抏枊偺栐偐傜摝傟偨恖娫傪憒摙偵棃傞丅偙偙傑偱曪埻傪弅傔傞偺偵1帪娫掱搙偼偐偐傞偲偟偰乧乧30乣40暘偺娫偵壜擻側尷傝偺惗懚幰偲崌棳偟丄彮偟偱傕埨慡側応強傑偱桿摫偟側偗傟偽丅鏢鏞偟偰偄傞帪娫偼側偄丅
乽儕儏僔儏僇偝傫乿
乽偼偄乿
丂斵彈偼偐偮偰偺摨椈偩偭偨彈惈偺巔偵栚傪棊偲偟劅劅儀僢僪偺巆奫偐傜僔乕僣傪堷偒敳偔偲偦偺恎懱偵偦偭偲偐偗傞丅
乽劅劅峴偒傑偟傚偆乿
丂偦偟偰丄崱搙偼壌偺栚傪尒偰偟偭偐傝偲偦偆尵偭偨丅
丂奜傊弌偰丄傑偢崱屻偺峴摦傪懪偪崌傢偣傞偙偲偵偡傞丅
乽儕儏僔儏僇偝傫偵偼惗懚幰偺妋擣偲桿摫傪偍婅偄偟傑偡乿
乽偗偳乧乧乿
乽嫲傜偔廝寕幰偼亀Kitten亁偑偙偙偵偄傞偙偲傪抦偭偰偄傞傫偱偡丅偙偙偵偄傞幰払偺側偐偱堦斣偺嫼埿劅劅偁偄偮傜偵崌傢偣偰偙偺峌寕傪巇妡偗偰偒偨乿
丂抏憅偺悢傪妋擣偟側偑傜懕偗傞丅
乽偩偐傜堦斣婋尟側偺偼偁偄偮傜偺嫋偱偡丅偦偪傜偵偼壌偑峴偒傑偡乿
丂斵彈偑偼偭偲偟偨婄偱壌傪尒偨丅
丂偦偺婄偑備偭偔傝偆偮傓偒乧乧晄埨偦偆側昞忣偵曄傢傞丅
乽暘偐傝傑偟偨乿
乽偍婅偄偟傑偡丅婥傪偮偗偰乿
乽乧乧儅僢僩偝傫偙偦乿
乽戝忎晇偱偡傛乿
丂埨惪偗崌偄偵夁偓傞偐偲帺殅婥枴偵巚偆丅偩偑偦偺傛偆偵偟偐曉帠偺偟傛偆偑側偄丅
乽偁偺乧乧乿
乽偼偄乿
丂曉帠偲偲傕偵婄傪忋偘偨搑抂劅劅
乽偁偺丄巹乧乧偁偲偱儅僢僩偝傫偵恥偹偨偄偙偲偲偐尵偄偨偄偙偲偲偐嶳偺傛偆偵偁傝傑偡偐傜乿
丂戝偒側摰偑壌傪嵘傒偮偗偰偄偨丅
乽偩偐傜丄偦偺劅劅栠偭偰偙側偒傖偩傔偱偡偐傜乿
丂偦傟偩偗傪尵偆偲丄斵彈偼奨偺拞墰傊偲憱傝弌偡丅
丂堦弖曫婥偵偲傜傟劅劅
乽偼偄乿
丂宧楃偟偰丄壌偼廻幧偺曽傊嬱偗弌偟偨丅
侕
乽柍條偩側乿
丂儔儞僌偑欔偔丅
乽壗偐嬄偄傑偟偨偐丄僿儖丒儔儞僌乿
丂嬤偔偵嵗傞懱奿偺椙偄抝偑栤偄曉偡丅
丂偙偙偼忋嬻1枩儊乕僩儖傪廃夞旘峴偟懕偗傞嫄恖峲嬻婡偺拞丅AI惂屼偺柍恖愴摤婡40婡偵庣傜傟傞丄墷廈寳偺孯帠揑椡偺梫偱偁傝偦偺嫼埿偵傛偭偰墷廈慡搚傪寢傃偮偗傞灦偱偁偭偨丅
丂儔儞僌偺帇慄偼惓柺偵偁傞2偮偺儌僯僞乕偺偆偪亀嬻敀抧懷亁偲屇徧偝傟傞応強偺忬嫷偵屌掕偝傟偰偄偨丅
乽柍條偩偲尵偭偨乿
丂旲敀傫偩抝偺昞忣偵峔傢偢丄儔儞僌偼尵梩傪懕偗偨丅
乽偙傫側柍悎側壩婍偺椡傪庁傝偹偽峌寕偡傜傑傑側傜傫丅儗儀儖4埲壓偺傾僋僙儔偼丄巹偺棟憐偐傜偐偗棧傟偨僋僘偩乿
乽偙傟偩偗偺愴摤擻椡傪帩偮暫巑傪偟偰偁側偨偼亀僋僘亁偲嬄傞偺偐丠乿
丂抝偑偦偺尵梩傪暦偒欓傔傞丅
乽偦偆偩丅幪偰嬵偵巊偭偰偄偨偩偄偰寢峔偩傛丅乧乧偁偲堦寧偁傟偽丄亀僛僯僗僛傾亁偑儘乕儖傾僂僩偟偰偄偨傕偺傪乧乧乿
乽亀僛僯僗乧乧亁側傫偱偡丠乿
乽孨偵偼抦傞尃棙偑側偄丅巹偼僨乕僞傪帩偪婣傟傟偽偦傟偱偄偄丅亀椺亁偺弨旛傕偁傞偺偩傠偆丠丂偝偭偝偲撍擖偝偣偨傑偊乿
丂堄偵夘偡傞條巕傕側偔丄儔儞僌偑尵偄幪偰偨丅抝偼晄夣偦偆偵儔儞僌傪尒偨偑丄偡偖嬤偔偺僆儁儗乕僞偵恥偹傞丅
乽忬嫷奐巒傑偱偼乿
乽偁偲5暘30昩偱偡乿
丂榬帪寁傪偪傜偭偲傒偰丄抝偼僼儘傾偺壓巑姱偵捠払偡傞丅
乽偙偪傜偺梡堄偼惍偭偨丅抧忋偺僋乕僨僞乕晹戉偵捠払偣傛乿
丂摦偒弌偡廃埻偵峔傢偢丄儔儞僌偼儌僯僞乕偺條巕傪嬅帇偟懕偗偰偄偨丅
丂摉弶亀幚峴幰乮僄僌僛僉儏乕僞乯亁奐敪偺僀僯僔傾僥傿償傪偲偭偰偄偨偺偼戞堦庬偩偭偨丅悽奅揑堚揱巕岺妛偺尃埿偱偁傞償傿儖僿儖儉=儈儔乕攷巑傪屭栤偵寎偊丄惛椡揑偵偦偺奐敪傪悇偟恑傔偰偄偨丅
丂偦偺尃埿偼亀僸儏僎儖儀儖幚尡亁偲屇徧偝傟偨偁傞寁夋偺幐攕偵傛傝幐傢傟傞偙偲偲側傞丅
丂2擭慜偺7寧20擔丄偦偺幚尡偼奐巒偝傟偨丅
丂code*A偲徧偝傟偨偦傟偼丄僸僩偺帩偮帺屓嵞惗擻椡傪嬌尷傑偱崅傔傞偙偲偺偱偒傞僸僩愼怓懱枹敪尰場巕亀A亁偺奐曻偵偁偭偨丅慖傃敳偐傟偨桪廏側慺抧傪帩偮尡懱偵亀傾僋僙儔丒償傿儔僗亁偲傛偽傟傞摿庩側僾儘僌儔儉丒儀僋僞乕傪怉偊偮偗丄DNA傪屻揤揑偵彂偒姺偊傞偙偲偱丄僸僩偺擻椡傪梱偐偵挻偊偨暫婍偲偟偰偺恖椶傪嶌傝弌偡劅劅
丂尡懱偵偼亀塧亁偲偟偰僸儏僎儖儀儖偵廤傔傜傟偨惌帯揑擄柉偳傕傪梌偊丄偦偺惉壥偵傛傝code*A偼亀傾儘儔僂儚亁偵懳峈偡傞暫婍偲偟偰検嶻偝傟偰偄偔偼偢偩偭偨丅
丂偟偐偟尡懱偼扤傂偲傝偲偟偰惗偒巆傜側偐偭偨丅
丂屻揤揑偵DNA傪彂偒姺偊傜傟偨恖娫払偼棟惈傪幐偄朶憱偟丄惂屼偱偒側偄僸僩側傜偞傞亀壗偐亁傊曄杄偟偰偄偨丅
丂寢壥丄尡懱偺張暘偼拲栚偡傜偝傟偰偄側偐偭偨戞嶰庬偑悇偟恑傔傞code*E劅劅亀Kitten亁偵埾偹傜傟丄偦偺惉岟偵傛傝僀僯僔傾僥傿償偼戞嶰庬傊偲堏摦偡傞丅償傿儖僿儖儉=儈儔乕攷巑偺柡偲徧偡傞偁偺亀恖宍亁偑亀Kitten亁偺巜婗傪峴偭偰偄偨偲偄偆偺偩偐傜丄旂擏埲奜偺壗幰偱傕偁傞傑偄丅
丂尃埿傪幐偭偨戞堦庬偺儊儞僶乕偼彊乆偵偦偺悢傪尭偠偰偄偔偙偲偵側傞丅
丂巹偼偦傫側戞堦庬偵巆偭偨堦恖偩偭偨丅
丂峴偔偁偰偑側偐偭偨栿偱傕code*A偵屌幏偟偨栿偱傕側偄丅
丂巹偵偼偐偮偰偺code*A傪婎偲偟丄撈帺偺棟榑傪壛偊偨怴偨側亀傾僋僙儔峔憐亁偑偁偭偨偺偩丅
丂亀Kitten亁偑帩偮亀摿惈亁偲屇偽傟傞擻椡偼嬼慠偵傛傞晹暘偑梋傝偵傕戝偒偄丅擻椡傪奐壴偱偒側偐偭偨僥僗僩僞僀僾偼尒愗傝傪偮偗傜傟偨帪揰偱亀幏峴幰乮僷僯僢僔儍乕乯亁偲屇偽傟傞惓懱晄柧偺傾儞僠丒償傿儔僗丒儐僯僢僩偵傛傝徚媝偝傟傞丅壗昐懱偲嶌傜傟側偑傜丄幚梡偵懴偊傜傟傞偲偝傟偨偺偼傢偢偐7懱偵偡偓側偄丅偩偑巹偺亀傾僋僙儔峔憐亁側傜丄桪傟偨儌僲偑惗傑傟傞妋棪偙偦摨偠側偑傜丄愗傝幪偰傞儌僲偱偡傜偙偆傗偭偰桳岠偵妶梡偱偒傞丅偳偪傜偑傛傝桳塿偱偁傞偐側偳丄堦栚椖慠側偼偢偩丅
丂亀僸儏僎儖儀儖幚尡亁偱巊梡偝傟偨慺懱偼婛偵惉挿偡傞梋抧偺側偄惉恖抝巕偩偭偨丅偩偐傜偙偦彂偒懼偊傜傟偨DNA傪庴偗晅偗偢嫅愨斀墳傪婲偙偟丄帺柵偟偰偄偭偨丅側傜偽偨偭偨堦恖丄尩慖偟偨惉恖慜偺僸僩偺DNA偺彂偒懼偊傪峴偄丄惗偒巆偭偨慺懱傪僋儘乕僯儞僌偡傟偽偄偄丅
丂偙偆偟偰丄code*A'偲柤偯偗傜傟偨偦偺寁夋偼奐巒偝傟偨丅
丂嫮堷偵悇偟恑傔摦偒弌偟偨偦偺撪梕偵恖堳偼偝傜偵搼懣偝傟丄戞堦庬偵偼code*A'偵巀摨偡傞庒偄尋媶幰払偩偗偑巆偭偰偄偔偙偲偲側傞丅
丂柺巕側偳偳偆偱傕偄偄丅傛偆傗偔斵彈払亀傾僋僙儔亁偑丄抧傪嬱偗嬻傪晳偆擔偑朘傟偨偺偩丅
丂尒偰偄傞偑偄偄丅
丂偙偺棟榑偩偗偑亀偁偺懚嵼亁偵懪偪彑偰傞桞堦偺恀棟側偺偩偲丄偙偙偱徹柧偟偰傒偣傞丅
乽彮彨乿
丂抧忋丄庱搒拞墰晅嬤偺楬抧棤丅
乽亀償傽儖僴儔亁傛傝忬嫷奐巒偑揱払偝傟傑偟偨乿
乽乧乧傢偐偭偨乿
丂楢棈偡傞惡偵実懷揹榖偱曉帠傪偟偨偺偼丄庒偄惵擭彨峑偩偭偨丅
丂偦偺朤傜偵偼丄嬧敮偺彮彈偑堦恖儃僨傿乕僗乕僣偵恎傪曪傒樔傓丅偝傜偵偦偺廃埻偵偼庒偄暫巑払偑10悢恖斵傪庢傝埻傓傛偆偵棫偭偰偄偨丅
乽0930傪帩偭偰抧忋晹戉偺嶌愴傪奐巒偡傞丅劅劅亀棟憐傪変偑庤偵亁乿
乽棟憐傪変偑庤偵乿
侕
丂婘偺忋偵偼2枃偺幨恀偑傓偒弌偟偺傑傑暲傋傜傟偰偄偨丅
丂傾儎偼偠偭偲偦傟傪尒偮傔偰偄傞丅
丂嶐擔憲傜傟偰偒偨曬崘儊乕儖偺拞偵丄儔儞僌攷巑偑儕儏僔傿偲尵偄憟偭偰偄偨偲偄偆巪偺婰嵹偑偁偭偨丅
丂僇僞儕僫=僶僂傾乕丅斵彈偼埲慜偐傜儕儏僔傿傪揋帇偟偰偄傞愡偑偁偭偨丅屻偐傜偺擖嬊偱偁傞偵傕娭傢傜偢徃恑傪敳偐傟偨偲偄偆偙偲傕偁傞偩傠偆偑丄偦傟偵懳偟偰儕儏僔傿帺恎偵壗偺姶奡傕側偄偲偄偆偲偙傠偑婥偵忈傞偺偩傠偆丅
丂巇曽偑側偄偙偲偩丅儕儏僔傿偼壗傕朷傫偱偄側偄丅戞嶰庬偵棃偨偺傕丄巹偺梫惪偵墳偠偰偔傟偨偩偗側偺偩丅
丂偩偐傜偙偦壗偲偐偟偰傗傝偨偄偲偄偆婥帩偪偼偁傞偺偩偑丄偦偙偱巹偑岥傪弌偣偽偦傟傪亀傂偄偒亁偲姶偠傞幰傕彮側偔側偄偩傠偆丅
丂晛抜側傜摢捝偺庬偩偑丄崱夞偺偦偺曬崘偵揧偊傜傟偨僨僕僞儖僨乕僞偵暿偺壙抣偑尒弌偝傟偨丅
丂弮敀偲尒暣偆偽偐傝偺嬧敮偲愒偄摰傪帩偮彮彈丅嫲傜偔愭揤揑側怓慺寚懝劅劅傾儖價僲偩傠偆丅庤慜偵偄傞僗乕僣巔偼戞堦庬偺儘儀乕儖=儔儞僌攷巑偲巚傢傟傞丅
丂堦弿偵暲傋傜傟偨傕偆堦枃偺幨恀偵偼塟擇偮偺彮彈丅偨偩偟偙偪傜偼僾儔僠僫僽儘儞僪偺敮偲惵偄摰偺帩偪庡偩丅
丂偙偺幨恀偼戞堦庬偱嶣塭偝傟偨傕偺偩偲尵傢傟偰偄傞丅僨乕僞傪嵦庢拞側偺偩傠偆丄敀偄娧堖傪偐傇傝堉巕偵崢妡偗偰壗偐傪懸偭偰偄傞傛偆側條巕偩丅
丂僀乕儕儎=儕僸僥儖丅儘僔傾偺偲偁傞惌晎婡娭偑挿擭偵搉傝旈摻偟懕偗偨悢彮側偄code*A偺庤偑偐傝偺傂偲偮偲偝傟偰偄傞丅
丂4擭慜偵偦偺抁偄惗奤傪暵偠丄愭揤惈偺晄帯偺昦偲堷偒姺偊偵恖側傜偞傞擻椡傪帩偭偰惗傑傟偨偲偝傟偨彮彈劅劅
丂傾儎偼婘偺庴榖婍傪庢傞偲偡偖偵弌偨尋媶堳偵恥偹傞丅
乽掕帪楢棈偼丠乿
乽傑偩棃偰偄傑偣傫乿
丂旣傪傂偦傔傞丅
乽偍偐偟偄傢偹乧乧乿
丂掕帪楢棈偑擖偭偰偒偨傜丄偡偖揹榖傪夞偡傛偆偵崱挬堦斣偱僗僞僢僼偵廃抦傪峴偭偰偄偨丅
丂偩偑6帪娫偛偲偵擖傞偼偢偺掕帪楢棈偼梊掕帪娫偺屵慜9帪傪30暘偡偓偨崱傕擖偭偰偒偰偄側偄丅
乽嵜懀偟傑偡偐丠乿
丂恥偹曉偡尋媶堳偵丄斲偲摎偊傞丅
乽巹偑擖傟傞傢乿
丂傾儎偼実懷揹榖傪庢傝弌偟儃僞儞傪慺憗偔墴偟偨丅柍婡幙側怣崋壒偺偺偪丄亀寳奜亁偺儊僢僙乕僕偑棳傟傞丅
丂実懷揹榖傪偨偨傒丄僨僗僋偺庴榖婍傪偲傝抁弅斣崋傪墴偡丅斀墳偼摨偠偩丅
乮劅劅傑偝偐乯
丂寉偔怬傪姎傒拡傪偵傜傒偮偗傞丅
丂傾儎偼庴榖婍傪扏偒偮偗傞傛偆偵栠偡偲棫偪忋偑偭偨丅
丂僨僗僋偺揹榖偼旕忢梡偺塹惎夞慄偵宷偑偭偰偄傞丅偦傟偑捠偠側偄偲偄偆偙偲偼丄壗傜偐偺嫮椡側捠怣朩奞偑峴傢傟偰偄傞壜擻惈偑崅偄丅
丂楲壓偵弌偰丄嵞傃実懷揹榖傪庢傝弌偟暿偺斣崋傪墴偡丅
丂僐乕儖壒偼偟偽傜偔柭傝懕偗劅劅10僐乕儖栚偱墳摎偑婣偭偰偒偨丅
乽偼偄乿
丂偟偽傜偔栙傝崬傫偩屻丄恥偹傞丅
乽乧乧僌僂僃儞丠乿
丂捑栙偑栤偄傪峬掕偟偰偄偨丅傾儎偼懅傪揻偔丅
乽偲偄偆偙偲偼偁偺僶僇偼偄側偄偺偹乿
乽劅劅傾儎偪傖傫偐乿
乽乧乧偍屳偄偄偄擭側傫偩偐傜丄亀偪傖傫亁偼傛偟偰乿
丂偄傜偮偄偨傛偆偵傾儎偑尵偄幪偰傞丅
乽埆偄丄偮偄側丅偁偄偮傕娫偑埆偄側丄偙傫側偲偒偵尷偭偰乧乧乿
乽乧乧傎傫偲偵丄偙傫側偲偒偵尷偭偰偹乿
丂戝偒偔懅傪揻偔丅
乽偙偺揹榖偼丄偁偄偮偵棅傑傟偰梐偐偭偰偄傞丅偲偄偆偙偲偼丄壗偐偁偭偨偭偰偙偲側傫偩側乿
乽亀嬻敀抧懷亁偲楢棈偑庢傟側偔側偭偨傢丅劅劅偍偦傜偔偙偙傕帪娫偺栤戣偹乿
乽偁偦偙偵偼妋偐僸儏僎儖儀儖偺惗偒巆傝偑偄偨側乿
乽偊偊乿
乽戝帠側徹嫆偩丅惗偒巆偭偰偔傟傟偽偄偄傫偩偑乿
乽惗偒巆偭偰偔傟側偄偲崲傞傢乿
丂斵偼嫸尵帠審傑偱堷偒婲偙偟偰丄亀偙偪傜懁亁偵妋曐偟偨恎暱偩丅
丂摨帪偵夋嶔偝傟偰偄偨丄儕儏僔傿傪戞嶰庬偺慜慄偐傜堷偒棧偡偲偄偆栚揑偑悑峴偱偒側偐偭偨偺偼岆嶼偩偭偨偑乧乧
乽晹戉傪亀嬻敀抧懷亁偲偦偪傜偵岦偐傢偣傞丅偦傟傑偱壗偲偐劅劅乿
丂寈曬偑柭傞丅摨帪偵宷偑偭偰偄偨実懷偺捠榖偑晄夣側僲僀僘偲偲傕偵愗傟偨丅
乮劅劅巒傑偭偨傢偹乯
丂傾儎偼実懷揹榖傪偦偺傑傑偟傑偄崬傓偲帺暘偺僆僼傿僗偵栠傝丄埨慡梡偺僷僢僉儞偺偮偄偨僗僀僢僠傪奜偡帪娫傕惿偟偄偲偽偐傝偵墸傝偮偗傞丅墴偟崬傑傟偨僗僀僢僠偑彫偝偔柭偭偨丅
乽娰撪慡堳偵崘偖丅忬嫷亀C-2亁丅儅僯儏傾儖偵廬偄恦懍偵峴摦偡傞傛偆偵丅偨偩偟丄柍棟側傜掞峈偣偢搳崀偟側偝偄丅柦傑偱偼扗傢傟側偄偼偢傛丅摨帪偵尰帪崗傪埲偭偰慡怑堳偺夝屬傪捠払偟傑偡丅
丂崱傑偱偁傝偑偲偆丅傒傫側丄巰側側偄偱丅劅劅埲忋乿
丂惡傪挘偭偰堦婥偵尵偆偲丄懅傪揻偔丅
乮廝寕幰偑恖摴揑慬抲傪偲偭偰偔傟傟偽丄偩偗偳乯
丂怬傪姎傓丅姰慡偵屻庤偵夞偭偨丅撉傒娫堘偊偨帺暘偺柍擻偝偵揻偒婥偑偡傞丅
丂亀嬻敀抧懷亁偵偼Kitten偑偄傞丅偙偪傜偺惂埑偵梫偡傞悢廫攞偺愴椡偑拲偓崬傑傟偰偄傞偵堘偄側偄丅弌岦偄偨娭學幰偺傎偲傫偳偼巰偸丅
丂彮側偔偲傕巹偼償傽儖僴儔偵偼峴偗傑偄丅
丂傗傞偣側偄婥帩偪傪書偊偨傑傑婘偺堷偒弌偟偐傜岇恎梡偺廵傪夰偵擖傟偨丅栶偵棫偮偲傕巚偊側偄偑丄婥媥傔偔傜偄偵偼側傞偩傠偆丅
乽劅劅巹傕峴偐側偔偪傖偹乿
丂傾儎偼惷偐偵帺幒傪弌傞偲斷傪暵傔乧乧帺傜偼儅僯儏傾儖偵媡傜偄丄寶暔偺墱傊偲岦偐偭偰偄偭偨丅
侕
丂庱搒儀儖儕儞丅
丂夛媍幒偺斷偑棎朶偵墴偟奐偐傟偨丅
乽乧乧幐楃乿
丂偦偺惡偱丄幒撪偺傎傏慡堳偑怳傝曉傞丅
丂廫悢恖偺抝惈払丅
丂偞傢偮偒巒傔偨幒撪傪丄墱偐傜尰傟偨惵擭彨峑偺堦尵偑捔傔偨丅
乽側偐側偐擬拞偟偨媍榑偺傛偆偱丅寢峔側偙偲偱偡乿
乽壗偩偹孨偼乿
丂擖傝岥晅嬤偵嵗偭偰偄偨抝偑扤壗偡傞丅
乽僈乕僪儅儞偼壗傪偟偰偄傞乿
乽柊偭偰偄傑偡傛丅擇搙偲婲偒忋偑傞偙偲傕側偄偱偟傚偆偑乿
丂僗乕僣巔偺壗恖偐偑搑榝偭偨昞忣傪尒偣劅劅屳偄偺婄傪尒崌偡丅
乽劅劅僼儗僪儕僸=僆僢僩乕彮彨乿
丂偦偺拞偐傜堦恖偺媍堳偑曕傒弌傞丅
乽乧乧慶晝偺柤傪偐偭偰塸梇婥庢傝偐丅巆擮偩偑丄変乆偼埨偭傐偄棟憐偵悓偆庒憿嫟偺尵偄側傝偵側傞傎偳惼庛偱偼側偄乿
乽偝偡偑丄崙傪摦偐偡幰偺婥奣偼偦偆偱側偔偰偼乿
丂敄偔徫偆惵擭彨峑偺慜偵彮彈偑棫偭偨丅
丂曕傒弌偨媍堳偺庤庱傪捦傓丅
乽偱偡偑丄掞峈偼柍堄枴偱偡丅劅劅傗傟乿
丂彮彈偺嵶偄庤偑媍堳偺庤庱偺忋傪捦傒忋偘傞丅
丂堦弖旲傪撍偔堎廘偲慚岝丅
丂師偺弖娫丄媍堳偺庤偼旾偐傜壓偑柍偔側偭偰偄偨丅
丂夛媍幒偵愨嫨偑嬁偒搉傞丅抝偼幐傢傟偨帺恎偺榬傪墴偝偊丄揮偘傑傢傞丅幒撪偵偄偨懠偺恖娫偼搥傝偮偄偨傛偆偵偦偺彮彈偺庤嫋傪嬅帇偟偰偄傞丅
丂彮彈偺巜愭偑撦偔岝偭偰偄偨丅
乽乧乧壗傪偟偨乧乧丠乿
丂惷庘傪忋偢偭偨惡偑攋傞丅
乽偁側偨偼掞峈偟側偄偺偱偡偐丠乿
丂彮彨偼偆偭偡傜偲徫偭偨丅
乽暿偵巭傔偼偟傑偣傫傛乿
乽摎偊傞婥偼側偄偲偄偆偙偲偐乿
乽尵偭偨偲偙傠偱丄偁側偨偨偪偵壗偑偱偒傞偲傕巚偊傑偣傫丅劅劅偦傟偵巹偼壈昦幰偱偡偐傜丄庤偺撪傪偝傜偡傛偆側偙偲偼偟傑偣傫傛乿
丂偦偺攚屻偱丄旈彂偲巚偟偒抝偑墱偵偄傞堦恖偵帹懪偪偟偨丅
乽戞嶰庬丄宷偑傝傑偣傫丅捠怣朩奞偱偡乿
丂幐堄偑揱攄偡傞丅
乽劅劅巇曽偁傞傑偄丅変乆傕搳崀偟傛偆乿
丂拞怱恖暔偲偍傏偟偒恖暔偑嬯廰偺昞忣偱愰尵偟偨丅
侕
丂偦偙偐傜悢僉儘棧傟偨偲偁傞応強丅偦偺彮彈偼敀偄懅傪揻偒側偑傜寴楽側僎乕僩偺朤偵棫偭偰偄偨丅
乽尒偮偗偨乿
丂戞嶰庬尋媶強惓栧慜丅
丂暼偺嫮偄愒栄偺僔儑乕僩僇僢僩丄娽嬀偺岦偙偆偐傜擿偔戝偒側摰偼梒偝傪巆偟側偑傜傕抦惈偺崅偝傪巉傢偣傞岝傪廻偟偰偄傞丅
乽拝偄偨傛丄亀儀儕僼傽亁乿
丂斵彈偼屻傠傪怳傝曉偭偨丅
丂僉傿乧乧偲惡偲傕嬥懏偺鏰傒偲傕偮偐側偄壒偑偡傞丅暘岤偄斂晍偺傛偆側傕偺傪偐傇偭偨嫄恖偑斵彈偺屻傠偵偮偒廬偭偰偄偨丅
乽偙偙偱懸婡乿
丂婤慠偲偟偨惡偱柦椷偡傞偲丄嫄恖偼偦偺尵梩偵廬偆傛偆偵摦偒傪巭傔傞丅
丂斵彈偼惓栧傪擖傞偲丄僈儔僗挘傝偺尯娭傪擿偒崬傓丅
乽扤偐丄偄傑偣傫偐乿
丂儘價乕偲巚傢偟偒嬻娫偵偦偺惡偼彫偝偔偙偩傑偟偰徚偊偨丅
乽偍偐偟偄側乧乧崱擔偩偭偨偼偢偩偗偳乿
丂斵彈偼嫻億働僢僩偐傜実懷抂枛傪庢傝弌偟丄僗働僕儏乕儖傪妋擣偡傞丅
丂偠偭偲彫偝側夋柺傪嬅帇偟丄奧傪暵偠傞丅
乽壖偵杔偺儊儌偑儈僗偩偭偨偵偟偰傕丄恖偺婥攝偑慡偔側偄偺偼彮偟偍偐偟偄丅乧乧惷偐偡偓傞乿
丂斵彈偼嫄恖偺嫋傊栠傞丅偦偟偰丅
乽亀儀儕僼傽亁丄棃偄乿
丂嫨傇偲嵞傃僎乕僩傊偲憱傝弌偡丅
丂嫄恖偼寉偔偦偺恎傪恔傢偣傞偲丄柍悢偺儌乕僞乕壒傪嬁偐偣側偑傜彮彈偺屻傠傪捛偆傛偆偵備偭偔傝偲摦偒弌偟偨丅
丂恖婥偺側偄楲壓傪丄偁偨傝傪尒夞偟側偑傜曕偔丅
丂彮彈偲亀儀儕僼傽亁偺懌壒偩偗偑捠楬偵嬁偄偰偄偨丅嬻婥拞偵崿偠傞旝偐側揝嶬傔偄偨擋偄偑斵彈偺惛恄偵捾傪棫偰傞丅
乽乧乧巭傑傟亀儀儕僼傽亁乿
丂鏰傫偩儌乕僞乕壒偑惷巭偡傞偲惷庘偼偦偺怓傪峏偵擹偔偵偠傑偣傞丅
丂彮彈偼帺暘傕棫偪巭傑傝丄帹傪悷傑偟偨丅
丂墦偔劅劅偄傗寶憿暔偺墱偱姡偄偨攋楐壒偑偡傞丅
丂寉偔旣傪傂偦傔傞偲彮彈偼壒偺偡傞傎偆傊懌傪恑傔偨丅嫄懱偑屻傠偵廬偆丅
丂妏傪嬋偑偭偨偲偨傫丄孋偺捾愭偑壗偐偵傂偭偐偐偭偨丅
丂彮彈偼偦偺忈奞暔傪嬅帇偡傞丅
丂揝嶬偺擋偄傪傛傝擹偔傑偲偭偨偦傟偼丄暻偵傕偨傟偐偐偭偨彈惈偩偭偨丅庤偵偼壗傕帩偨偢丄摢忋偺暻偵偼愒偔昤偐傟偨暋悢偺捈慄丅
乽乧乧寵偄偩側乿
丂尵梩偼帺慠偵怬偐傜楇傟偨丅
丂偄偮偩偭偰杔傜偼棟晄恠傪墴偟偮偗傜傟丄摜傒偵偠傜傟傞丅
乽亀儀儕僼傽亁丄峴偔傛丅乧乧偦偙偱柊偭偰傞恖偼摜傑側偄傛偆偵偹乿
丂柦偠側偑傜彮彈偼恑峴曽岦傪偒偭偲尒偮傔傞丅
丂偦偺愭偵偼擇搙偲栚妎傔偸恖乆偺巔偑僆僽僕僃偝側偑傜偵楢側偭偰偄偨丅
侕
丂壌偲巕嫙払偑怮攽傝偟偰偄偨寶暔偼怮彴偑偁偭偨1奒晹暘偑攋夡偝傟丄2奒晹暘偺宍傪偓傝偓傝巆偟偨傑傑壓偵捑傒偙傫偱偄偨丅
丂巕嫙払偼堦扷寶暔偺姠釯偺拞偵杽傕傟偨偑丄帺椡偱敳偗弌偟偨偲尵偭偰偄偨丅
丂偳偆傗偭偰敳偗弌偟偨偐偼丄帪娫偑側偄偙偲傕偁偭偰恥偄偰偄側偄丅偲傝偁偊偢懠偺儊儞僶乕偲崌棳偡傞偙偲偑愭寛偲峫偊偨偺偩丅
丂拞墰偺抧壓嬻娫傊栠偭偰偔傞偲丄拞偱偼摙榑偺恀偭嵟拞偩偭偨丅
乽愭崗偺峌寕偱婡嵽偺傎偲傫偳偑懝夡偝偣傜傟偨傢丅偄偭偨偄偳偆傗偭偰乧乧乿
丂曅曽偼妋偐僇僞儕僫偲柤忔偭偨彈惈丅傕偆曅曽偼儕儏僔儏僇偝傫偩丅
乽埲慜偐傜峫偊偰偄偨偙偲偑偁傝傑偡丅偙偺棟榑偑惓偟偗傟偽劅劅乿
乽婘忋偺嬻榑偩傢両乿
乽劅劅偁偺乿
丂壌偼愭偵巕嫙払傪擖傟傞偲丄偦偺偁偲傪懕偔傛偆偵奒抜傪崀傝乧乧儕儏僔儏僇偝傫偵惡傪偐偗偨丅
乽乧乧儅僢僩偝傫両乿
丂儕儏僔儏僇偝傫偑怳傝岦偔丅
丂僇僞儕僫忟偺尵梩偑偦傟傪巭傔傛偆偲偡傞偐偺傛偆偵偐傇偝偭偨丅
乽榖偼傑偩廔傢偭偰側偄傢丅偁側偨丄偦偺峫偊偑惓偟偔偭偰丄偙偙偵惗偒巆偭偨儊儞僶乕偑偪傖傫偲惗偒巆傟傞偭偰曐徹偑弌棃傞偺丠乿
丂夵傔偰拞偵偄傞恖悢傪悢偊傞丅偞偭偲50柤嫮偐丅
乽曐徹偼偱偒傑偣傫丅偱偡偑劅劅乿
丂儕儏僔儏僇偝傫偺惡偼彮乆庛傔偩丅
乽偩偭偨傜帪娫偺柍懯偱偟傚偆丅僞僀儉偵亀弬亁傪挘偭偰傕傜偭偰楿忛偟偨傎偆偑傑偩乿
乽偦傟偙偦柍懯偩偲巚偄傑偡傛乿
乽壗屘両乿
丂僇僞儕僫偝傫偺峌寕揑側岥挷偑偙偪傜傪岦偔丅
乽岦偙偆偺巚榝偑丄偙偙偵偄傞恖娫偺慡柵偵偁傞偐傜偱偡乿
丂壌偼嵞傃奒抜偵懌傪偐偗偨丅
乽偳偙傊峴偔偺丠乿
乽僟儊尦偺掞峈偵乿
乽懸偪側偝偄乿
丂僇僞儕僫忟偑壌傪堷偒巭傔傞丅廃曈偺彈惈払傕偞傢傔偒巒傔偨丅
乽彑庤側峴摦偼崲傞傢乿
乽偦偆傛丅偁側偨傪屬偭偰偄傞偺偼戞嶰庬丄偮傑傝巹払側偺傛乿
丂壌偼怳傝曉傞丅
乽乧乧傗傞偐傗傜側偄偐乿
丂傑偭偡偖丄斵彈傜傪尒傗傞丅
乽傗傞側傜扤偑丅劅劅帪娫偺柍懯偱偡丅慡柵偟偨偄側傜暿偱偡偑乿
乽壗傪乧乧両乿
乽偙偺傑傑偱偼巰偸偺傪懸偮偩偗偱偡丅摦偄偰傕摨偠偐傕偟傟傑偣傫偑劅劅惗偒巆傟傞偐傕偟傟傑偣傫乿
丂尵偄側偑傜丄怱偺拞偱嬯徫偡傞丅
丂亀柍堊偵偼巰偵偨偔側偄亁劅劅偦偺婥帩偪偑巰傊偲岦偐偆堄幆偵斀偟偰丄壌傪惗偒塱傜偊偝偣偰偒偨偲偄偆偺偵丅
丂偩偑丄壌偼壌偺婅偄偵懠恖傪姫偒崬傓偙偲傪嫋偡偙偲偑偱偒側偄丅
乽偁側偨丄壗傪尵偭偰偄傞偺偐暘偐偭偰偄傞偺乧乧丠乿
丂曫慠偲偟偨傛偆偵僇僞儕僫忟偑尵偆丅
乽孯恖偼偦偆偄偆惗偒暔偱偡傛乿
丂岥偺抂偵徫傒傪晜偐傋傞丅
丂偩偑彈惈払偺娽偼婃側偵壌偺尵梩傪嫅斲偟懕偗偰偄偨丅
乽傢偐傝傑偟偨乿
丂壌偼懅傪揻偔丅
乽偁偔傑偱傕媍榑偺忋偲偄偆偺偱偟偨傜丄側傞傋偔憗偔寛傔偰偔偩偝偄丅劅劅壌偼偦傟傑偱偺娫丄壗偲偐偙偙傪曐偨偣傑偟傚偆乿
丂嵞傃敪惗偟偨偞傢傔偒傪柍帇偟偰丄壌偼嵞傃抧壓嬻娫偺擖傝岥傪奐偗丄抧忋傊弌偨丅
丂嵒偲側偭偨姠釯偑晽偵忔偭偰旘傫偱偔傞丅晽偺壒偺崌娫偵惷庘偑昚偆丅
乽懸偭偰偔偩偝偄乿
丂攚拞偐傜挳偙偊偨惡偵壌偼彮偟峇偰偰怳傝曉偭偨丅
乽儕儏僔儏僇偝傫乧乧乿
丂儕儏僔儏僇偝傫偑巕嫙払傪楢傟丄屻傠偵棫偭偰偄偨丅
乽壗偟偰偄傞傫偱偡両乿
乽巹偵峫偊偑偁傞傫偱偡乿
乽壗偑乧乧乿
乽亀摦偗偽惗偒巆傟傞偐傕偟傟側偄亁乧乧偱傕丄偁側偨偼偦偺拞偵帺暘帺恎傪擖傟偰偼偄側偄偱偟傚偆丠乿
丂斀榑偟偐偗偨壌傪丄斵彈偼傑偭偡偖尒偮傔傞丅
乽惗偒傞偐巰偸偐偩傕偺丄崱峏墦椂側傫偐偟側偄傢乿
丂曉帠偵媷偡傞壌偵丄斵彈偼懕偗偨丅
乽尵偭偨偱偟傚偆丠丂巹偼偁側偨偵尵偄偨偄偙偲偑偁傞偺乧乧偩偐傜丄彑庤偵徚偊傜傟偨傜崲傞偺傛乿
丂堦曕偢偮丄嬤偯偔斵彈丅
乽偱傕崱偼偦偺榖傪偡傞帪偠傖側偄傢丅偩偐傜丄堦弿偵惗偒墑傃傑偟傚偆乿
乽偦傟偼乧乧柦椷偱偡偐丠乿
丂傛偆傗偔嶏傝弌偟偨尵梩偵丄斵彈偑旝徫傓丅
乽偦傟偑偍朷傒偱偟偨傜乿
丂偁偁丅劅劅偙偺恖偼丄壗偲側偔壌偺惛恄乮偙偙傠乯偺嵼傝曽偵婥偯偄偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅
丂揋傢側偄側丅壌偼嬯徫偱斵彈偵墳偊偨丅
乽劅劅亀Kitten亁傪婲摦偟傑偡丅偁偺巕払偺巜婗姱偵婱曽傪擟柦偡傞傢乿
丂斵彈偼儈儞僩傪庤彽偒偟偰屇傫偩丅偦偟偰丄壌偵庤傪嵎偟弌偡丅
乽儅僢僩偝傫丄偙傟偐傜儈儞僩偵偁側偨偺擼攇傪搊榐偟傑偡乿
丂嵎偟弌偝傟偨巜愭偵怗傟傞丅斵彈偼旝偐偵徫偭偰丄鏢鏞偡傞壌偺庤傪屌偔埇偭偨丅
乽儈儞僩乿
丂斵彈偺尵梩偵儈儞僩偑柍尵偱桴偒丄斵彈偺庤偲壌偺庤傪偲傞丅偦偺傑傑寉偔栚傪暵偠偨丅
乽乧乧壌偼壗傪偡傟偽乿
乽栚傪暵偠偰丅堄幆傪奐偄偰乿
乽奐偔乧乧丠乿
乽巹払偵堄幆傪岦偗傞傛偆側姶妎偱乿
丂寉偔栚傪暵偠傞丅
乽劅劅Shift乿
丂儕儏僔儏僇偝傫偺尵梩偑偡偭偲堄幆偵妸傝崬傓丅
丂巜愭偐傜擖傝崬傫偱偔傞亀擬亁偑恄宱傪梙偝傇傝偙偠奐偗丄榬傪捠偠偰愐悜傪骧鏦偟慡恎偵峴偒搉傞丅
丂偦傟偼丄愭掱婋婡傪抦傜偣偨偁偺堄幆偵崜帡偟偰偄偨傛偆偵巚偊偨丅
丂尵梩偵側傜側偄堄巚偑嵶偄棳傟偐傜朶椡揑側杬棳傊曄傢傞丅
乽乧乧乿
丂嫨傃傪忋偘偨偔側傞傎偳偺晄夣姶丅岮偵偙傒忋偘傞惡傪梷偊崬傓丅懱壏偑搑換傕側偄惃偄偱忋偑偭偰偄偔偺偑傢偐傞丅
丂尷奅偩丅劅劅偦偆巚偭偨弖娫丅
乽乧乧Anfang乿
丂斵彈偺師偺尵梩偲偲傕偵丄偦偺椡偺杬棳偼彊乆偵嵶偔側傝劅劅婯懃惓偟偄椡偺棳傟傊偲曄傢偭偰偄偭偨丅
丂斵彈偲儈儞僩偺庤偑棧傟傞丅
乽儈儞僩偼斵偺巜帵偑偁傞傑偱偙偺傑傑懸婡乿
丂桴偄偨儈儞僩偺摰偼丄晛抜偺怺椢傪扻偊偢丄偨偩柍婡幙側敀嬧偺偦傟偵愼傑偭偰偄偨丅