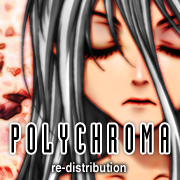崟偄怷嘦丗GateOdyssey丗novels乥憂嶌彫愢廤抍CRAFTWORX乮僋儔僼僩儚乕僋僗乯
崟偄怷嘦
Engage the slaughter girl
丂崟偔暵偞偝傟偨怷偺傎傏拞墰偵偦偺寶暔偼偁偭偨丅
丂庤擖傟偝傟傞偙偲傕側偔丄朘栤幰偵彑庤偵巊偊偲偽偐傝偵曻抲偝傟偨偐偮偰偼鄋煭側暤埻婥傪帩偭偰偄偨偱偁傠偆儘僌僴僂僗丅
乽......乿
丂偩偑丄偦偺斷偼柍嶴偵傕懪偪嵱偐傟丄墝偺擋偄傪昚傢偣偰偄傞丅
丂......姰慡偵攑婞偝傟偨柍恖偺巤愝偩偲暦偄偰偄偨傫偩偑側丅
丂僋儗僀僌偼拲堄怺偔廃埻傪挷傋丄劅劅劅劅偦偟偰懅傪揻偄偨丅
丂尞側偳摉慠愓宍傕側偄丅斷偑偁偭偨偱偁傠偆埵抲傪偔偖傝劅劅劅劅棫偪崬傔傞擋偄偵婄傪偟偐傔傞丅
丂寣偲徤墝偺擋偄丅敄偄埮偺拞偵揮偑偭偰偄傞恖傜偟偒塭傪3偮擣傔傞丅偦偺偆偪偺堦偮偵嬤晅偒劅劅劅劅僽乕僣偺愭偱嬄岦偗偵揮偑偟偨丅
丂偦偺傑傑僋儗僀僌偼孅傒崬傒丄偦偺亀巰懱亁傪娤嶡偡傞丅
丂攚拞偵抏偑娧捠偟偨愓偼側偔丄暊晹偼20cm嬤偔偊偖傟劅劅劅劅廵抏傪懪偪崬傑傟偨偱偁傠偆屄強偑從偗徟偘偰偄偨丅
丂掞峈偺婥攝傕側偔丄懄巰偝偣傜傟偰偄傞丅鄖楐抏偺椶偐......偟偐偟丅
丂懳恖梡掅懍鄖楐抏偼嶦彎椡偺崅偝偵斀斾椺偟丄偦偺撪晹峔憿偺暋嶨偝偐傜旘嫍棧偑弌偢娧揙椡傕嬌抂偵掅偄丅岠壥傪妋幚偵忋偘傞堊偵偼栚昗偐傜10m埲撪偵愙嬤巊梡偡傞昁梫偑偁傝丄愴摤偲偄偆忬嫷偵偍偗傞幚梡搙偼尷傝側偔楇偵嬤偄丅偨偩偟懱偺拞墰晹偵柦拞偡傟偽妋幚偵愨柦偝偣傜傟傞偟丄巐巿偺偳偙偐偵柦拞偡傟偽丄攋夡椡偵暔傪尵傢偣丄偦偺晹埵傪妋幚偵懱偐傜暘抐偝偣傜傟傞丅
丂偮傑傝偙偺巰懱偺亀惗惉幰亁偼丄嵟弶偐傜廵寕愴傪峫椂偟偰偄側偄偲偄偆偙偲偩丅
丂廵抏偑妋幚偵柦拞偡傞帄嬤嫍棧傑偱敪尒偝傟偢偵愙揋偡傞帺怣偑偁傞偺偐......偦傟偲傕丅
丂僋儗僀僌偼棫偪忋偑傝丄晹壆傪尒搉偡丅墱傑偭偨妏偺彴偐傜旝偐偵楇傟傞岝傪尒偮偗丄備偭偔傝曕傒婑偭偨丅
丂抧壓偵宷偑傞奒抜偑偁傞偺偐丅
丂偟偽傜偔懅傪巭傔丄帹傪悷傑偡丅劅劅劅劅恖偺婥攝偑側偄偙偲傪妋擣偡傞偲僋儗僀僌偼偍傕傓傠偵偦偺奒抜傪壓傝巒傔傞丅
丂崅偝偵偟偰2奒暘傎偳偺嫍棧傪崀傝傞偲峴偔庤傪幷傞傛偆偵懚嵼偡傞斷偲懳柺偟偨丅
丂儘僌僴僂僗偵帡偮偐傢偟偔側偄丄桘埑儘僢僋偝傟偨懴埑斷丅偦偙偵庢傝晅偗傜傟偨奐曻尞偼巜栦擣徹偺傛偆偩偭偨丅
丂斷偺愭偵恑傓曽朄傪巚埬偟......傆偲丄彴偵揮偑偭偰偄傞偁傞暔懱偵婥偑偮偔丅
丂偪偓傟偨恖娫偺榬丅嫲傜偔奜偺暫巑傪弖嶦偟偨壗幰偐偑斷傪奐曻偡傞偺偵巰懱偐傜攓庁偟偨傕偺偩傠偆丅
丂僋儗僀僌偼偦偺榬傪偠偭偲尒偮傔劅劅劅劅
乽......埆偄側乿
丂堦恖偛偪傞傛偆偵尵偆偲偦偺榬傪廍偄忋偘丄擣徹僙儞僒乕偵恖嵎偟巜傪墴偟偁偰偨丅
丂桘埑僔儕儞僟乕偺嬱摦壒偲嫟偵嵍塃偵奐曻偝傟傞斷丅
丂偦偺愭偵偼恖娫偺巰懱偑摴側傝偵揰嵼偟偰偄偨丅
丂備偭偔傝偲丄検嶻偝傟偨巰懱傪庤偑偐傝偵偟偰楲壓傪恑傫偱偄偔丅
丂楲壓傪壗搙偐嬋偑傞偆偪偵丄塻晀側挳妎偑摨曽岦傪愭峴偡傞懌壒傪曔傜偊偨丅帪愜姡偄偨攋楐壒偑偦偺側偐偵崿偠傞丅
丂懌壒偼巚偭偨傛傝寉偄劅劅劅劅亀廝寕幰亁偼偐側傝偺彫暱傜偟偄丅偄傗彫暱偲尵偆傛傝丄偙傟偼劅劅劅劅
丂僋儗僀僌偼恑傓懍搙傪懍傔丄亀廝寕幰亁偲偺嫍棧傪弅傔偰偄偔丅
丂亀廝寕幰亁偺恑傓僥儞億偼曄傢傜側偄丅僋儗僀僌偑愓傪捛偭偰偄傞偙偲偵婥晅偄偰偄側偄傛偆偩丅懌壒偲攋楐壒偼彊乆偵偦偺壒検傪憹偟劅劅劅劅
丂楲壓偺撍偒摉偨傝偺妏傪傑偑傞偲丄亀廝寕幰亁偺巔偑栚偵旘傃崬傓丅
丂偼偭偲偟偨傛偆偵怳傝岦偒丄廵傪岦偗傞亀廝寕幰亁丅傎傏摨帪偵僋儗僀僌傕廵傪亀廝寕幰亁偵岦偗劅劅劅劅
丂弖娫懅傪撣傓丅......偦偺巔偼10嵨偵傕枮偨側偄偱偁傠偆彮彈偺傕偺偱偁偭偨偐傜丅
丂偦偺嬐偐側寗傪彮彈偼摝偝側偄丅柍昞忣偺傑傑斵偵岦偗偨廵偺堷偒嬥傪堷偔丅
丂僋儗僀僌偺堄幆偼曫慠偲偟偨傑傑偩丅偩偑丄斵偺杮擻偲偱傕屇傇傋偒愴応偵偍偗傞摦懱斀幩偼昞憌堄幆偲偼暿偵恎懱傪嫲傞傋偒懍搙偱慁夞偝偣廵抏傪旔偗偝偣傞劅劅劅劅偦偺惃偄傪嶦偝偢彮彈偵愙嬤偟丄摨帪偵偦偺彮彈偺庤偵偼偁傑傝偵嫄戝偡偓傞廵偵岦偗恖娫偵寊捙傪堦寕偱暡嵱偱偒傞傎偳偺懍搙傪傕偭偰庤搧傪扏偒崬傓丅
丂廵偼彮彈偺庤傪棧傟傞丅僋儗僀僌偼偦偺傑傑傕偆堦曽偺嵍庤偱彮彈偺庤庱傪捦傓丅
丂彴偵掅偄壒傪嬁偐偣棊壓偡傞廵丅偦偺壒偐傜悇應偝傟傞廳検偼劅劅劅劅7乣8kg丅僋儗僀僌偼彮彈偺帩偮廵偑恞忢側傕偺偱側偄偲屽傞丅
乽......傗傔偰偍偗丅壌偵偦偺婥偑側偔偰傕丄廵傪岦偗傞憡庤偵偼忦審斀幩偱斀寕偟偪傑偆乿
丂僋儗僀僌偼捦傫偩庤庱傪偦偺傑傑悅捈偵帩偪忋偘傞丅彮彈偺恎懱偼娙扨偵拡偵晜偄偨丅
丂弖娫彮彈偼敀嬧偺廲挿偵怢傃偨摰岴傪偒偭偲尒奐偒丄恎傪傂偹傝嬻偄偰偄偨庤偱僋儗僀僌偺榬傪捦傓丅偦偺傑傑恎懱傪忋曽偵夞揮偝偣丄僋儗僀僌偺寊捙偵嫲傞傋偒懍搙偱廟傝傪擖傟傞丅偑丄偦偺堦寕偝偊傕僋儗僀僌偺塃榬偑偦偺懍搙偝偊椊夗偡傞恄懍傪傕偭偰庴偗巭傔偨丅偩偑丅
丂......壗偰廟傝偩劅劅劅劅偦偺嫮楏側椡偵婄傪偟偐傔傞丅
丂崪偺昞憌傪嵱偐傟偨偐丅懗偺撪懁偵偼帄嬤嫍棧偱偺僷儔儁儔儉抏偺捈寕偝偊巭傔傞僾儘僥僋僞乕傪巇崬傫偱偁傞偲偄偆偺偵丅
丂彮彈偼偦偺寗傪摝偝偢帺傜偺攚拞偵庤傪夞偟堷偒敳偔丅嵞傃尰傟偨庤偵偼愭傎偳抏偄偨暔偲塟擇偮偺嫄戝偱壭乆偟偄廵偑埇傜傟偰偄偨丅
丂偙偄偮 !?
丂僋儗僀僌偼捦傫偱偄偨彮彈偺恎懱傪暻柺偵岦偐偭偰欜歭偵曻傝搳偘偨丅
丂偦偺傑傑暻偵扏偒晅偗傜傟傞捈慜劅劅劅劅彮彈偼恎懱傪夞揮偝偣偨丅
丂恖娫偵偼側偟偊側偄廱偺傛偆側摦偒偱暻偵廟傝傪擖傟丄恎懱偺挼偹傞曽岦傪曄偊偦偺懱惃偐傜僋儗僀僌偵岦偐偭偰廵傪億僀儞僩偡傞丅
丂偩偑丄偦偺帪婛偵僋儗僀僌偺廵偺徟揰偼彮彈偵崌傢偣傜傟劅劅劅劅堷偒嬥偼峣傜傟偰偄偨丅
丂彮彈偺栚偑戝偒偔尒奐偐傟偨丅僋儗僀僌偼変偵婣傞丅
丂劅劅劅劅彮彈偺恎懱偼傑偩拞嬻偵偁傞丅斵彈偼偦偺抏傪亀旔偗傜傟側偄亁劅劅劅劅
丂彮彈偺恎懱偵廵抏偑愙嬤偡傞劅劅劅劅偲丅
乽婋側偄偱偡偹......巕嫙偵杮婥傪弌偟偪傖偄偗傑偣傫傛丄戝堁揳乿
丂偄偮偺娫偵偐丄彂惗晽偺惵擭偑彮彈偺恎懱傪書偒偐偐偊傞傛偆偵棫偭偰偄偨丅廵抏偼彮彈偑偄偨偼偢偺暻柺偵撍偒巋偝傝掆巭偟偰偄偨丅
丂偩偑丄僋儗僀僌偼欜歭偵嫨傇丅
乽劅劅劅劅傛偗傠 ! 乿
丂......撦偔丄帹忈傝側壒偑柭傝嬁偔丅彮彈偑帺暘偺恎懱傪書偒偐偐偊偨惵擭偺榬傪幉偵丄媡忋偑傝偺梫椞偱庱嬝偵廟傝傪擖傟偨偺偩丅
丂惵擭偺恎懱偑暻偵扏偒晅偗傜傟傞丅偦偺寗偵彮彈偼惵擭偺榬傪扙偟丄僋儗僀僌偵嵞傃廵偺慱偄傪掕傔劅劅劅劅鏢鏞偡傞丅
乽!!乿
丂僋儗僀僌偑暻偵傕偨傟偐偐偭偨惵擭劅劅劅劅傾儖僼儗僢僪=僕乕儕儞僌偺朤偵嬱偗婑偭偰偄偨丅偁偺壒偼娫堘偄側偔庱偺崪偑愜傟偨丅偙偺彮彈偺椡傪峫偊傟偽丄愨懳偵彆偐傜側偄丅
乽......偁偄偨偨丄偨乿
丂偩偑丄偦偺梊憐偼僕乕儕儞僌偺婥偺敳偗偨傛偆側惡偱暍偝傟偨丅
乽......乿
乽傂偳偄側丄彆偗偰偁偘偨偮傕傝側傫偱偡偑偹乿
丂嬯徫偄偟側偑傜僕乕儕儞僌偑備偭偔傝恎懱傪婲偙偡丅
乽......偍慜乿
丂僋儗僀僌偼曫慠偲偟偰欔偔丅
乽壗偲傕......側偄偺偐乿
乽偦傝傖捝偄偱偡傛乿
丂偸偗偸偗偲摎偊偨僕乕儕儞僌偵丄僋儗僀僌偼捦傒偐偐傞丅
乽偄傗丄崱妋偐偵庱偺崪偑愜傟偨偼偢偩丅惗偒偰偄傜傟傞傢偗偑......乿
乽婥偺偣偄偱偟傚偆丅庱偺崪傪愜傜傟偰惗偒偰偄傞恖娫側傫偰偄傑偣傫傛乿
丂傢偞偲傜偟偔庱傪偝偡傝側偑傜丄僕乕儕儞僌偼棫偪忋偑偭偨丅
丂僋儗僀僌偼懅傪揻偒劅劅劅劅旝徫偆僕乕儕儞僌偺嬢尦傪撍偒曻偡丅
乽......婱條丄杺朄尛偄偠傖側偔偰晄巰幰偩偭偨偺偐乿
丂僕乕儕儞僌偼尐傪偡偔傔偰丅
乽偝傝婥側偔傂偳偄偙偲偄偄傑偡偹丄戝堁揳乿
乽婱條偵偼尵偄偨偄帠偑嶳偺傛偆偵偁傞傫偩偑側乿
乽劅劅劅劅婱曽払丄堦懱壗側偺乿
丂僋儗僀僌偲僕乕儕儞僌偼彮彈偺惡偵帇慄傪尛傞丅
丂彮彈偼彴偵傌偨傫偲嵗傝崬傫偱偄偨丅
丂庤偵帩偭偨廵偼昗揑傪掕傔偢丄彴偵廵岥傪岦偗偨傑傑劅劅劅劅2恖傪尒忋偘傞偦偺娽偼敀嬧偺偦傟偱側偔丄廮傜偐偄拑怓偵曄傢偭偰偄偨丅
乽壗偩偲尵傢傟偰傕側......乿
乽傑偁丄晄朄怤擖幰傒偨偄側傕偺偱偡乿
乽......偍慜側乿
乽壗偐娫堘偄傑偟偨偐丠乿
乽......偄傗乿
丂彮彈偼偦傫側2恖偺傗傝庢傝傪偍偲側偟偔暦偄偰偄偨偑丄
乽巇帠偑偁傞偺丅偩偐傜......乿
丂棫偪忋偑傝丄僗僇乕僩偺悶傪偼偨偔丅
乽亀巇帠亁丠乿
丂僋儗僀僌偼偦偺彮彈偺尵梩偵堘榓姶傪妎偊偨丅
乽巇帠丅側偺偵婱曽払偑幾杺傪偡傞偐傜乿
乽......暿偵壌偼偍慜偺幾杺傪偟偵棃偨栿偠傖側偄乿
丂偦偺曉帠偵彮彈偺娽偑娵偔側傝劅劅劅劅昞忣偑嵨憡墳偺偦傟偵曄傢傞丅
乽廵傪岦偗偨偔偣偵乿
乽偍慜偺曽偑愭偩偭偨傠偆偑丅惓摉杊塹偩乿
丂慺捈側栤偄偵丄僋儗僀僌偼嫃忎崅偵摎偊偨丅
乽偍慜偺梡帠傕壗幰側偺偐傕抦傜傫丅壌偼壌偺梡帠偱偙偙偵棃偨乿
乽......偦偆乿
丂僋儗僀僌偺尵梩傪暦偄偰丄彮彈偺昞忣偑傆偭偲廮傜偐偔側傞丅
乽側傜丄婱曽払偼嶦偝側偔偰偄偄傫偩傢乿
丂埨揼傪娷傫偩摰偼劅劅劅劅偲偰傕偙傟傑偱偺亀巰懱偺検嶻幰亁偲偼巚偊側偄傎偳壐傗偐偩偭偨丅
乽偪偭丄傗傝偵偔偄側乿
丂僋儗僀僌偼傏偦偭偲欔偒劅劅劅劅
乽偍偄乿
丂嵞傃彮彈偵岦偒捈偭偨丅
乽壗丠乿
丂僋儗僀僌偼彮彈偐傜扏偒棊偟偨廵傪廍偄劅劅劅劅扨搧捈擖偵恥偹傞丅
乽偙偺僶僇偱偐偄廵丅寴婥偺傕傫偠傖偹乕側丅偳偙偱庤偵擖傟偨乿
丂彮彈偼墴偟栙傞丅
乽偍偄乿
丂捑栙傪懕偗傞彮彈偵丄僋儗僀僌偼媗傔婑傞丅
乽劅劅劅劅摎偊傞偮傕傝偑側偄傫側傜丄偙偭偪偵傕峫偊偑偁傞傫乿
乽廵偭偰偦傕偦傕寴婥側傫偱偡偐偹乿
丂偦傟傑偱僋儗僀僌偲彮彈偺夛榖傪朤娤偟偰偄偨僕乕儕儞僌偑岥傪偼偝傫偩丅
乽栙傟杺朄巊偄乿
丂悈傪嵎偝傟偰僋儗僀僌偑攚屻傪嵘傒偮偗傞丅
乽壌偼丄偦偙偺偍忟偪傖傫偵暦偄偰傞傫偩丅......偳偆側傫偩乿
乽......偁側偨傕偦傕偦傕亀僇僞僊亁側偺偐偟傜乿
丂栤偄偵栤偄偱曉偟偨彮彈偺尵梩偵僋儗僀僌偼尵梩傪幐偄劅劅劅劅摢傪書偊傞丅
乽......偙偄偮乿
丂擇恖偺條巕傪尒偰丄僕乕儕儞僌偑巚傢偢悂偒弌偟偨丅
乽堦杮庢傜傟偪傖偄傑偟偨偹乿
乽劅劅劅劅傕偆偄偄乿
丂僋儗僀僌偼戝嬄偵懅傪揻偔丅
乽......偹偊乿
丂彮彈偑岥傪奐偄偨丅
乽壗偩乿
乽巹傕丄暦偄偰偄偄丠乿
丂僋儗僀僌偼夦鎎偦偆偵丄僕乕儕儞僌偼嫽枴怺偘偵彮彈傪尒偮傔傞丅
丂彮彈偼帺暘偺惓柺偵偄傞抝2恖傪傑偭偡偖偵尒忋偘偰恥偹偨丅
乽......巹偭偰丄庛偄丠乿
丂僋儗僀僌偲僕乕儕儞僌偼偍屳偄偺婄傪尒崌傢偣劅劅劅劅岎屳偵摎偊傞丅
乽壔偗暔偩側乿
乽旕忢幆側偔傜偄偵乿
丂彮彈偼偦偺傑傑2恖偺婄傪尒偮傔偰偄偨偑......傗偑偰棴懅偲嫟偵傐偮傝偲欔偄偨丅
乽婱曽払偵尵傢傟偰傕愢摼椡偑側偄傢乿
丂偦偺傑傑偔傞偭偲屻傠傪岦偔丅
乽......偍偄乿
丂彮彈偼嬱偗弌偟偨懌傪巭傔劅劅劅劅僋儗僀僌偺傎偆傪怳傝岦偄偨丅
乽傑偩丄梡偑偁傞偺丠乿
乽偦偆媫偖側偭偰乿
乽尵偭偨偱偟傚丅帪娫偑側偄偺乿
乽堦媥傒偡傞偔傜偄偺帪娫偼偁傞偩傠乿
丂僋儗僀僌偼彮彈偵廍偭偨廵傪嵎偟弌偟偰偵傗偭偲徫偭偨丅
乽偍慜偺巇帠傪庤揱偭偰傗傞丅偩偐傜丄偍慜傕壌偺巇帠傪庤揱偊乿
乽......庤揱偄側傫偐偄傜側偄乿
乽傑偀偦偆偄偆側丅偍慜偺僞乕僎僢僩偼亀恖娫亁偩傠丅......壌偺偼亀儌僲亁偩偐傜乿
乽......乿
丂僋儗僀僌偼偦偺応偵嵗傝崬傫偱彮彈偵帇慄傪嬤偯偗偰恥偹傞丅
乽暦偐偣傠傛丅劅劅劅劅偍慜偺昗揑偼扤偩丠乿
丂柍榑慺捈偵摎偊傞偲巚偭偰恥偹偨栿偱偼側偄丅偩偑丅
乽......亀僌僗僞僼=儃僢僔儏亁偲偄偆恖乿
丂偦偺柤慜偼偡傫側傝偲彮彈偺岥偐傜朼偓弌偝傟偨丅
丂劅劅劅劅僞乕僎僢僩偵懳偡傞旈庣媊柋偼側偄偲偄偆偙偲側偺偐丅
丂怓乆側巚榝偑摢傪傛偓偭偨偑丄偦傟偵偮偄偰婄偵偼弌偝偢丄
乽偦偆尵偆偙偲偐丅......摴棟偱乿
丂巆傝偺抏憅偺妋擣傪峴側偄側偑傜丄僋儗僀僌偑欔偄偨丅
乽僌僗僞僼=儃僢僔儏偑偙偙偵偄傞偺偐乿
乽......扤側傫偱偡偐乿
乽孯偺忣曬嬊偺姴晹偺1恖偩丅惓懱偼亀鍨鍟亁偩偑側乿
乽亀鍨鍟亁丠乿
丂偒傚偲傫偲偟偨婄偱彮彈偑暦偒曉偟劅劅劅劅彮偟崲偭偨傛偆偵尵偆丅
乽暘偐傞傛偆偵尵偭偰乿
乽忟偪傖傫偼亀鍨鍟亁偼抦偭偰傞偐丠乿
乽......歁擕峧梼庤栚偺憤徧偱乿
乽惗暔恾娪傒偨偄側夞摎偩側乿
丂尵偄偐偗偨彮彈偺尵梩傪惂巭偟偰丄僋儗僀僌偼尵梩傪宲偖丅
乽僱僘儈偵傕帡偰傞偟捁偵傕帡偰傞丅屆憙偵偄傟偽枴曽偺怳傝傪偟偰捁偺偦偽偵偄傞帪偼偦偪傜偵垽憐傪怳傞乿
乽......僗僷僀峴堊偱偡偐乿
丂僕乕儕儞僌偺尵梩偵僋儗僀僌偼桴偄偨丅
乽嵟廔揑偵偼僱僘儈偺偦偽偵傕捁偺偦偽偵傕偄傜傟側偔側偭偨偲偄偆偙偲偩丅......偨偩偙偄偮偑乿
丂偲僋儗僀僌偼彮彈傪巜偝偟偰尵偆丅
乽偙偄偮偑嶦偟偨楢拞偼偦傫側偙偲抦傜偝傟偪傖偄側偄偩傠偆偑側乿
丂僕乕儕儞僌偑擺摼偟偨傛偆偵桴偔丅
乽......偳偆偟偰婱曽払偵偦傫側偙偲偑傢偐傞偺丠乿
丂偨偩堦恖彮彈偑摼怱偑峴偐側偄偺偐丄搑榝偭偨昞忣偺傑傑恥偹傞丅
乽崙偺斴岇偺嫋偸偔偸偔偲偟偰偄傞崢敳偗嫟偩偐傜偝丅劅劅劅劅偩偐傜偙偦帺暘偺曐恎偵偼擬怱偩丅搝偑傗傜偐偟偨帠幚傪抦偭偰偄傟偽丄戝恖偟偔偮偄偰偔傞栿偑側偄丅嫲傜偔偙偄偮傜偼儃僢僔儏偑揔摉偵漵憿偟偨柦椷偵丄偨偩晹壓偲偟偰偮偄偰偒偨偩偗偩傠偆乿
乽偮傑傝巹偑嶦偟偨恖娫払偼丄壗傕抦傜偝傟偰偄側偄偺偹乿
丂彮彈偺摰偑旝偐偵撥傞丅偦傫側斵彈偺條巕傪僕乕儕儞僌偼偠偭偲尒偮傔偰偄偨偑......傗偑偰僋儗僀僌偺傎偆傪怳傝曉傝恥偹偨丅
乽劅劅劅劅偙偺崙偺孯偵壗偐巚偆張偑偁傞傛偆偱偡偑丠乿
乽搝傜偲偼妋幏偑偁傞乿
丂楲壓偺岦偙偆傪尒傗傝丄僋儗僀僌偼偄傑偄傑偟偦偆偵尵梩傪揻偔丅
乽桪廏側晹壓偑壗恖傕嶦偝傟偰偄傞丅搝傜偺柍擻偝偲丄棙屓偺堊偵乿
乽......乿
乽愴憟傪惗嬈偵偟偰偄傞埲忋壌偵傕晹壓払偵傕妎屽偼偁傞丅偩偑......亀僸儏僎儖儀儖亁偺審偼嫋偟擄偄乿
乽亀僸儏僎儖儀儖亁......乿
乽亀徚偊偨愴栶亁偩丅劅劅劅劅偁傑傝偵傕晄帺慠夁偓偨乿
丂僋儗僀僌偼懅傪揻偔丅
乽媤傪偲傞偲偐丄偦偆偄偆栿偠傖側偄偑劅劅劅劅帠偑僌儗乕偵側偭偰偄傞偺偼偳偆傕懻偗側偄丅惗懚幰傪庢傝崬傫偩傝偼偟偰傒偨偑丄2擭宱偭偨崱傕壗偑婲偙偭偨偺偐偼偼偭偒傝偟側偄乿
乽......乿
乽儃僢僔儏偼偦偺嶌愴偺巟帩幰偺1恖偩乿
丂恎峔偊傞彮彈丅偦偺條巕傪墶栚偱尒偰丄僋儗僀僌偼嬯徫偟偨丅
乽偦偆晐偄婄偡傞側偭偰丅偍慜偺妉暔傪墶庢傝偡傞婥偼偹偉傛丅......儃僢僔儏傕扨側傞嬵偺1偮偵夁偓側偄乿
乽偳偆偟偰偦偆抐掕偱偒傞傫偱偡丠乿
丂嫽枴怺偘偵僕乕儕儞僌偑恥偔丅
乽偳偆峫偊偰傕孯偩偗偱偼側偟偊側偄亀壗偐亁傪峴側偭偰偄偨偐傜偩乿
乽......乿
乽巰傫偩晹壓払偺巰懱傪旈枾棤偵夞廂偟丄専巰傪峴側偭偨乿
丂偟偽偟偺捑栙偺偺偪僋儗僀僌偼戝偒偔懅傪揻偄偰......尵梩傪懕偗偨丅
乽巰場偼妋偐偵懡戝側奜彎偵傛傞傕偺偩偑劅劅劅劅晹壓払偺嵶朎偼丄捠忢偺恖娫偺偦傟偲偼慡偔堘偆傕偺偵曄幙偟偰偄偨偺偝乿
丂僕儞僕儍乕偑偙偺応強傪敪偭偰偐傜悢帪娫屻丅
丂壌偼崱屻偺孭楙偺梊掕偵偮偄偰榖偟崌偆偨傔偵僇僼僃僥儕傾偱儕儏僔儏僇偝傫傪懸偭偰偄偨丅
丂婛偵梉怘偵巜掕偝傟偰偄傞帪娫偐傜3帪娫掱丅僇僼僃僥儕傾偺拞偼傑偽傜偵恖偑嵗偭偰偄傞掱搙偩丅
乽偛傔傫側偝偄丄偙傫側帪娫傑偱乿
丂傗偑偰尰傟偨斵彈偼怽偟栿側偝偦偆偵尵偄側偑傜壌偺惓柺偺惾偵嵗偭偨丅壌偼寉偔徫偭偰墳偊傞丅
乽偄偊丄巇帠偱偡偐傜乿
丂幚嵺丄嵟弶偼椪帪怑堳偲偟偰屬傢傟傞梊掕偩偭偨壌偵偼妎偊側偔偰偼側傜側偄偙偲偑嶳偺傛偆偵偁傞偺偩丅
乽愭偵栚傪捠偟偰傕傜偊傑偡丠乿
丂偦偆尵偭偰彂椶偺懇傪搉偝傟偨丅愭摢偐傜弴偵儁乕僕傪孞傞丅偞偭偲栚傪捠偟劅劅劅劅
乽......亀僸儏僎儖儀儖亁乿
丂栚偵巭傑偭偨抧柤傪丄壌偼柍堄幆偵欔偄偨丅
乽......偁偁丄妋偐柧惎憪偑孮惗偟偰偄傞偺偱桳柤側張偱偡偹乿
丂曉偭偰偒偨尵梩偵丄堄幆偑怺偔捑傒偙傓丅
丂劅劅劅劅亀柧惎憪亁丅
丂摢偺拞偵晜偐傇丄晽偵梙傟傞敀偔橰偘側栰偵嶇偔壴丅堦柺偵嶇偒屩傝丄寧岝傪庴偗偰崹偒嬻偵岝傪挼偹曉偡丅
丂傗偨傜偲戝偒偔挳偙偊傞帺暘偺屇媧偲摦湩丅尒偊側偄揋偵澦偝傟偰偄偔拠娫丅敀偄壴傃傜偵崀傝偐偐傞愒丅
丂栚偺慜傪暍偆峠怓偺僼傿儖僞乕劅劅劅劅
乽......儅僢僩偝傫丠乿
丂搨撍偵怤擖偟偰偒偨惡偵丄堄幆傪嫮堷偵栠偝傟傞丅
丂搑榝偭偨傛偆偵壌傪尒偮傔偰偄傞斵彈丅
乽劅劅劅劅偡偄傑偣傫乿
丂擼偵晜偐傇塮憸傪寽柦偵捛偄暐偆丅......偁偺婰壇偵怗傟傞儌僲偼丄枹偩偵壌偺惛恄傪愗傝崗傓丅
乽戝忎晇偱偡偐丠丂婄怓偑乿
乽偊偊乿
丂偦偆偼揱偊偨傕偺偺丄晜偐傫偩塮憸偼惗敿偵偼擼偺帇奅偐傜偼棧傟側偄丅
丂斵彈偼怱攝偦偆偵壌偺婄傪擿偒崬傫偱偄偨偑劅劅劅劅偄偒側傝婘偵峀偘偰偄偨彂椶傪偐偒廤傔偨丅丂偦偺傑傑彂椶傪書偊傞偲婘偺偙偪傜懁傊夢偭偰偒偰丄壌偺庤庱傪柍憿嶌偵偲傞丅
丂梊應偟摼側偄偦偺峴摦偵丄偮偄斀幩揑偵榬傪傂偄偨丅
乽......偁乿
丂寉偔嬃偄偨傛偆側斵彈偺婄丅
乽偡偄傑偣傫......偁偺丄戝忎晇偱偡偐傜乿
丂嵾埆姶傪姶偠劅劅劅劅欜歭偵幱偭偨弖娫丅
乽偙傜乿
丂嵶偄巜偑壌偺妟傪寉偔撍偮偄偨丅
乽......乿
丂曫慠偲栚偺慜偺斵彈傪尒偮傔傞丅斵彈偼旝徫偭偰劅劅劅劅
乽偛傔傫側偝偄丅......偱傕偦偺條巕偠傖亀戝忎晇亁偲偐尵傢傟偰傕怣梡偱偒側偄偱偡乿
乽偄傗......偱偡偑......乿
丂偦傫側壌偺尵偄暘傪暦偄偰偄傞偺偐偄側偄偺偐丄斵彈偼嵞傃庤庱傪偲傞丅
乽偨傑偵偼偍巓偝傫偺尵偆偙偲傕暦偔傕偺偱偡傛丄儅僥傿傾僗孨乿
丂埆媃偭巕偺傛偆側徫婄偱埇傞斵彈偺庤偺椡偼堄奜偵嫮偔劅劅劅劅偄傗丄幚嵺偵偼偦傟傎偳嫮偔側偐偭偨偺偐傕偟傟側偄偑丄偦偺帪偺壌偼掞峈傜偟偄掞峈傕偣偢丄儕儏僔儏僇=儈儔乕偲偄偆彈惈偺朷傓傑傑偵廬偍偆偲巚偭偨偺偩丅
丂曻怱......偟偰偄偨偺偩傠偆偐丅
丂偦偺帪尒偣偨斵彈偺徫婄偼丄偒偭偲亀杮暔亁偱偁偭偨偩傠偆偐傜丅
乽偦偙偵嵗偭偰偰偔偩偝偄丄偡偖栠傝傑偡偐傜乿
丂偦傟偩偗尵偭偰丄斵彈劅劅劅劅儕儏僔儏僇偝傫偼晹壆傪弌偰峴偭偨丅
丂楢傟偰偙傜傟偨偺偼丄儔儃偺怑堳偺寶暔偺堦幒偩偭偨丅
丂姪傔傜傟偨偼偄偄傕偺偺丄儀僢僪偵偡偖偵崢妡偗傞偺傕鏢鏞傢傟偰......壌偼偦偺晹壆傪偖傞偭偲尒夞偟偨丅
丂嵍塃懳徧偵攝抲偝傟偰偄傞暻嵺偵婑偣傜傟偨儀僢僪偲彫偝偄婘丅偩偑曅曽偺僙僢僩偼巊傢傟偰偄側偄傛偆偩丅
乽......偁傜乿
丂斷偺奐偔壒丅
乽亀嵗偭偰偰偔偩偝偄亁偭偰尵偭偨偺偵乿
乽偡偄傑偣傫乿
乽婄怓傑偩椙偔側偭偰傑偣傫傛......偒傖丠乿
丂偙偪傜偵岦偐偭偰偒偨斵彈偺恎懱偑搨撍偵傛傠偗偨丅
乽偁傇側......乿
丂壌偼斀幩揑偵斵彈偺恎懱傪庴偗巭傔傞丅偦偺恎懱傪書偒偐偐偊偨忬懺偱屻傠偵搢傟崬傒劅劅劅劅栚偺慜偵壩壴偑嶶偭偨丅
丂斵彈偺恎懱傪書偊偨傑傑儀僢僪偺忋偱旾傪偮偄偰恎懱傪巟偊偨傕偺偺丄偦偺岦偙偆偺暻偵摢傪傇偮偗偰偟傑偭偨傛偆偩丅
乽偁偨偨......乿
丂帺暘偺摢傪柍堄幆偵偝偡傞丅尰忬傪攃埇偡傞偺偵彮偟帪娫偑偐偐偭偨丅
丂捝傒傪慽偊傞惡偵嬃偄偨偺偐丄斵彈偑峇偰偰婲偒忋偑傞丅
乽劅劅劅劅儅僢僩偝傫丄戝忎晇偱偡偐!?乿
丂忋偐傜斵彈偺惡偑偡傞丅
乽傊丄暯婥偱偡......乿
丂娽傪奐偗偨搑抂丄崌傢偝傞帇慄丅戝偒側摰丅媧偄崬傑傟偦偆側怺偄拑怓劅劅劅劅
丂......壌偼搨撍偵変偵婣傞丅
丂傑偢偄丅......偙偺巔惃偼旕忢偵傑偢偄丅
丂摨帪偵斵彈傕偦傟偵婥偑偮偄偨偺偐丄峇偰偰恎懱傪棧偟偨丅
乽偛丄偛傔傫側偝偄偭乿
乽劅劅劅劅偄偊乿
丂壌偼恎懱傪婲偙偡丅
丂斵彈偼扙偘偨僸乕儖傪廍偭偰棜偄偨丅
丂偁偁丄彴偺斅偵纟偑偼偝傑偭偨偺偐丅幒撪偲偼偄偊傕偲傕偲攑壆偩丅栘偺彴偼偐側傝榁媭壔偟偰偄傞丅
乽......乿
丂婘偺偦偽偵抲偄偰偁偭偨彫偝側堉巕丅斵彈偼偦傟傪堷偄偰偒偰丄儀僢僪偺榚偵抲偄偨丅
丂偦偺傑傑崢妡偗偰......彫偝側惡偱尵偆丅
乽墶偵側偭偰偰偔偩偝偄乿
乽偟偐偟乿
乽婄怓埆偄忋偵摢傇偮偗偨傫偱偡偐傜乿
乽......乿
乽戝恖偟偔尵偆偙偲暦偒側偝偄乿
丂......偦偺婄偑偆偭偡傜庨偔愼傑偭偰偄偨偺偼懡暘婥偺偣偄偱偼側偄偩傠偆丅嫮婥偺尵梩偼徠傟塀偟側偺偩偲屽偭偰壌偼戝恖偟偔孋傪扙偄偱墶偵側偭偨丅
丂偦偺傑傑丄栚傪寉偔暵偠傞丅
丂惓捈側張丄擼撪偵晜偐傫偱偄偨塮憸偼愭掱摢傪傇偮偗偨弖娫偵悂偭旘傫偱偟傑偭偰偄偨丅
丂......挳偙偊偨偐傕偟傟側偄丅
丂愭掱傑偱偲偼堄枴偺堘偆丄寖偟偄摦湩傪......挳偄偰偄偨偐傕偟傟側偄丅
丂斵彈偑傛傠偗偨弖娫丄壌偼斵彈偺恎懱傪偐偽偆偨傔偵......斵彈偺摢傪書偊崬傫偩丅壌偺惡偵嬃偄偰旘傃婲偒傞傑偱丄斵彈偺摢偼壌偺嫻偺忋偵偁偭偰丅
丂偦偺弖娫偺旲傪偔偡偖傞扺偄娒偄崄傝偲丄屇媧偲丄廮傜偐偄姶怗偵婥偑偮偄偨帪劅劅劅劅怱壒偑挼偹忋偑偭偨丅
丂劅劅劅劅傂傗傝偲偟偨姶怗傪丄妟偵姶偠傞丅
丂暵偠偰偄偨豳傪奐偔丅丂妟偵忔偣傜傟偨傕偺偵寉偔怗傟傞丅......屌偔峣傜傟偨僴儞僇僠丅
乽......婥媥傔偱偡偗偳乿
丂斵彈偑壌偺帇慄偵婥偑偮偄偨偺偐丄偙偪傜傪岦偄偰旝徫偆丅
丂怱偺墱掙偱殤偔惡偑丄桸偒忋偑傞憐偄偵寈崘傪梌偊傞丅
丂朷傓側丅偍慜偵偦偺帒奿偼側偄丄偲丅
乽桳擄偆偛偞偄傑偡乿
丂壌偼斵彈偵徫偄曉偟偰劅劅劅劅嵞傃栚傪暵偠偨丅
丂斵彈偺帇慄偵旝偐側偔偡偖偭偨偝傪姶偠側偑傜丅
丂殤偔惡偵壌偼摎偊傞丅
丂......斵彈偺徫婄偑尒偨偄丅偦偆婅偆偙偲帺懱偼嵾偱偼側偄偩傠偆......丠
丂庤擖傟偝傟傞偙偲傕側偔丄朘栤幰偵彑庤偵巊偊偲偽偐傝偵曻抲偝傟偨偐偮偰偼鄋煭側暤埻婥傪帩偭偰偄偨偱偁傠偆儘僌僴僂僗丅
乽......乿
丂偩偑丄偦偺斷偼柍嶴偵傕懪偪嵱偐傟丄墝偺擋偄傪昚傢偣偰偄傞丅
丂......姰慡偵攑婞偝傟偨柍恖偺巤愝偩偲暦偄偰偄偨傫偩偑側丅
丂僋儗僀僌偼拲堄怺偔廃埻傪挷傋丄劅劅劅劅偦偟偰懅傪揻偄偨丅
丂尞側偳摉慠愓宍傕側偄丅斷偑偁偭偨偱偁傠偆埵抲傪偔偖傝劅劅劅劅棫偪崬傔傞擋偄偵婄傪偟偐傔傞丅
丂寣偲徤墝偺擋偄丅敄偄埮偺拞偵揮偑偭偰偄傞恖傜偟偒塭傪3偮擣傔傞丅偦偺偆偪偺堦偮偵嬤晅偒劅劅劅劅僽乕僣偺愭偱嬄岦偗偵揮偑偟偨丅
丂偦偺傑傑僋儗僀僌偼孅傒崬傒丄偦偺亀巰懱亁傪娤嶡偡傞丅
丂攚拞偵抏偑娧捠偟偨愓偼側偔丄暊晹偼20cm嬤偔偊偖傟劅劅劅劅廵抏傪懪偪崬傑傟偨偱偁傠偆屄強偑從偗徟偘偰偄偨丅
丂掞峈偺婥攝傕側偔丄懄巰偝偣傜傟偰偄傞丅鄖楐抏偺椶偐......偟偐偟丅
丂懳恖梡掅懍鄖楐抏偼嶦彎椡偺崅偝偵斀斾椺偟丄偦偺撪晹峔憿偺暋嶨偝偐傜旘嫍棧偑弌偢娧揙椡傕嬌抂偵掅偄丅岠壥傪妋幚偵忋偘傞堊偵偼栚昗偐傜10m埲撪偵愙嬤巊梡偡傞昁梫偑偁傝丄愴摤偲偄偆忬嫷偵偍偗傞幚梡搙偼尷傝側偔楇偵嬤偄丅偨偩偟懱偺拞墰晹偵柦拞偡傟偽妋幚偵愨柦偝偣傜傟傞偟丄巐巿偺偳偙偐偵柦拞偡傟偽丄攋夡椡偵暔傪尵傢偣丄偦偺晹埵傪妋幚偵懱偐傜暘抐偝偣傜傟傞丅
丂偮傑傝偙偺巰懱偺亀惗惉幰亁偼丄嵟弶偐傜廵寕愴傪峫椂偟偰偄側偄偲偄偆偙偲偩丅
丂廵抏偑妋幚偵柦拞偡傞帄嬤嫍棧傑偱敪尒偝傟偢偵愙揋偡傞帺怣偑偁傞偺偐......偦傟偲傕丅
丂僋儗僀僌偼棫偪忋偑傝丄晹壆傪尒搉偡丅墱傑偭偨妏偺彴偐傜旝偐偵楇傟傞岝傪尒偮偗丄備偭偔傝曕傒婑偭偨丅
丂抧壓偵宷偑傞奒抜偑偁傞偺偐丅
丂偟偽傜偔懅傪巭傔丄帹傪悷傑偡丅劅劅劅劅恖偺婥攝偑側偄偙偲傪妋擣偡傞偲僋儗僀僌偼偍傕傓傠偵偦偺奒抜傪壓傝巒傔傞丅
丂崅偝偵偟偰2奒暘傎偳偺嫍棧傪崀傝傞偲峴偔庤傪幷傞傛偆偵懚嵼偡傞斷偲懳柺偟偨丅
丂儘僌僴僂僗偵帡偮偐傢偟偔側偄丄桘埑儘僢僋偝傟偨懴埑斷丅偦偙偵庢傝晅偗傜傟偨奐曻尞偼巜栦擣徹偺傛偆偩偭偨丅
丂斷偺愭偵恑傓曽朄傪巚埬偟......傆偲丄彴偵揮偑偭偰偄傞偁傞暔懱偵婥偑偮偔丅
丂偪偓傟偨恖娫偺榬丅嫲傜偔奜偺暫巑傪弖嶦偟偨壗幰偐偑斷傪奐曻偡傞偺偵巰懱偐傜攓庁偟偨傕偺偩傠偆丅
丂僋儗僀僌偼偦偺榬傪偠偭偲尒偮傔劅劅劅劅
乽......埆偄側乿
丂堦恖偛偪傞傛偆偵尵偆偲偦偺榬傪廍偄忋偘丄擣徹僙儞僒乕偵恖嵎偟巜傪墴偟偁偰偨丅
丂桘埑僔儕儞僟乕偺嬱摦壒偲嫟偵嵍塃偵奐曻偝傟傞斷丅
丂偦偺愭偵偼恖娫偺巰懱偑摴側傝偵揰嵼偟偰偄偨丅
侕
丂備偭偔傝偲丄検嶻偝傟偨巰懱傪庤偑偐傝偵偟偰楲壓傪恑傫偱偄偔丅
丂楲壓傪壗搙偐嬋偑傞偆偪偵丄塻晀側挳妎偑摨曽岦傪愭峴偡傞懌壒傪曔傜偊偨丅帪愜姡偄偨攋楐壒偑偦偺側偐偵崿偠傞丅
丂懌壒偼巚偭偨傛傝寉偄劅劅劅劅亀廝寕幰亁偼偐側傝偺彫暱傜偟偄丅偄傗彫暱偲尵偆傛傝丄偙傟偼劅劅劅劅
丂僋儗僀僌偼恑傓懍搙傪懍傔丄亀廝寕幰亁偲偺嫍棧傪弅傔偰偄偔丅
丂亀廝寕幰亁偺恑傓僥儞億偼曄傢傜側偄丅僋儗僀僌偑愓傪捛偭偰偄傞偙偲偵婥晅偄偰偄側偄傛偆偩丅懌壒偲攋楐壒偼彊乆偵偦偺壒検傪憹偟劅劅劅劅
丂楲壓偺撍偒摉偨傝偺妏傪傑偑傞偲丄亀廝寕幰亁偺巔偑栚偵旘傃崬傓丅
丂偼偭偲偟偨傛偆偵怳傝岦偒丄廵傪岦偗傞亀廝寕幰亁丅傎傏摨帪偵僋儗僀僌傕廵傪亀廝寕幰亁偵岦偗劅劅劅劅
丂弖娫懅傪撣傓丅......偦偺巔偼10嵨偵傕枮偨側偄偱偁傠偆彮彈偺傕偺偱偁偭偨偐傜丅
丂偦偺嬐偐側寗傪彮彈偼摝偝側偄丅柍昞忣偺傑傑斵偵岦偗偨廵偺堷偒嬥傪堷偔丅
丂僋儗僀僌偺堄幆偼曫慠偲偟偨傑傑偩丅偩偑丄斵偺杮擻偲偱傕屇傇傋偒愴応偵偍偗傞摦懱斀幩偼昞憌堄幆偲偼暿偵恎懱傪嫲傞傋偒懍搙偱慁夞偝偣廵抏傪旔偗偝偣傞劅劅劅劅偦偺惃偄傪嶦偝偢彮彈偵愙嬤偟丄摨帪偵偦偺彮彈偺庤偵偼偁傑傝偵嫄戝偡偓傞廵偵岦偗恖娫偵寊捙傪堦寕偱暡嵱偱偒傞傎偳偺懍搙傪傕偭偰庤搧傪扏偒崬傓丅
丂廵偼彮彈偺庤傪棧傟傞丅僋儗僀僌偼偦偺傑傑傕偆堦曽偺嵍庤偱彮彈偺庤庱傪捦傓丅
丂彴偵掅偄壒傪嬁偐偣棊壓偡傞廵丅偦偺壒偐傜悇應偝傟傞廳検偼劅劅劅劅7乣8kg丅僋儗僀僌偼彮彈偺帩偮廵偑恞忢側傕偺偱側偄偲屽傞丅
乽......傗傔偰偍偗丅壌偵偦偺婥偑側偔偰傕丄廵傪岦偗傞憡庤偵偼忦審斀幩偱斀寕偟偪傑偆乿
丂僋儗僀僌偼捦傫偩庤庱傪偦偺傑傑悅捈偵帩偪忋偘傞丅彮彈偺恎懱偼娙扨偵拡偵晜偄偨丅
丂弖娫彮彈偼敀嬧偺廲挿偵怢傃偨摰岴傪偒偭偲尒奐偒丄恎傪傂偹傝嬻偄偰偄偨庤偱僋儗僀僌偺榬傪捦傓丅偦偺傑傑恎懱傪忋曽偵夞揮偝偣丄僋儗僀僌偺寊捙偵嫲傞傋偒懍搙偱廟傝傪擖傟傞丅偑丄偦偺堦寕偝偊傕僋儗僀僌偺塃榬偑偦偺懍搙偝偊椊夗偡傞恄懍傪傕偭偰庴偗巭傔偨丅偩偑丅
丂......壗偰廟傝偩劅劅劅劅偦偺嫮楏側椡偵婄傪偟偐傔傞丅
丂崪偺昞憌傪嵱偐傟偨偐丅懗偺撪懁偵偼帄嬤嫍棧偱偺僷儔儁儔儉抏偺捈寕偝偊巭傔傞僾儘僥僋僞乕傪巇崬傫偱偁傞偲偄偆偺偵丅
丂彮彈偼偦偺寗傪摝偝偢帺傜偺攚拞偵庤傪夞偟堷偒敳偔丅嵞傃尰傟偨庤偵偼愭傎偳抏偄偨暔偲塟擇偮偺嫄戝偱壭乆偟偄廵偑埇傜傟偰偄偨丅
丂偙偄偮 !?
丂僋儗僀僌偼捦傫偱偄偨彮彈偺恎懱傪暻柺偵岦偐偭偰欜歭偵曻傝搳偘偨丅
丂偦偺傑傑暻偵扏偒晅偗傜傟傞捈慜劅劅劅劅彮彈偼恎懱傪夞揮偝偣偨丅
丂恖娫偵偼側偟偊側偄廱偺傛偆側摦偒偱暻偵廟傝傪擖傟丄恎懱偺挼偹傞曽岦傪曄偊偦偺懱惃偐傜僋儗僀僌偵岦偐偭偰廵傪億僀儞僩偡傞丅
丂偩偑丄偦偺帪婛偵僋儗僀僌偺廵偺徟揰偼彮彈偵崌傢偣傜傟劅劅劅劅堷偒嬥偼峣傜傟偰偄偨丅
丂彮彈偺栚偑戝偒偔尒奐偐傟偨丅僋儗僀僌偼変偵婣傞丅
丂劅劅劅劅彮彈偺恎懱偼傑偩拞嬻偵偁傞丅斵彈偼偦偺抏傪亀旔偗傜傟側偄亁劅劅劅劅
丂彮彈偺恎懱偵廵抏偑愙嬤偡傞劅劅劅劅偲丅
乽婋側偄偱偡偹......巕嫙偵杮婥傪弌偟偪傖偄偗傑偣傫傛丄戝堁揳乿
丂偄偮偺娫偵偐丄彂惗晽偺惵擭偑彮彈偺恎懱傪書偒偐偐偊傞傛偆偵棫偭偰偄偨丅廵抏偼彮彈偑偄偨偼偢偺暻柺偵撍偒巋偝傝掆巭偟偰偄偨丅
丂偩偑丄僋儗僀僌偼欜歭偵嫨傇丅
乽劅劅劅劅傛偗傠 ! 乿
丂......撦偔丄帹忈傝側壒偑柭傝嬁偔丅彮彈偑帺暘偺恎懱傪書偒偐偐偊偨惵擭偺榬傪幉偵丄媡忋偑傝偺梫椞偱庱嬝偵廟傝傪擖傟偨偺偩丅
丂惵擭偺恎懱偑暻偵扏偒晅偗傜傟傞丅偦偺寗偵彮彈偼惵擭偺榬傪扙偟丄僋儗僀僌偵嵞傃廵偺慱偄傪掕傔劅劅劅劅鏢鏞偡傞丅
乽!!乿
丂僋儗僀僌偑暻偵傕偨傟偐偐偭偨惵擭劅劅劅劅傾儖僼儗僢僪=僕乕儕儞僌偺朤偵嬱偗婑偭偰偄偨丅偁偺壒偼娫堘偄側偔庱偺崪偑愜傟偨丅偙偺彮彈偺椡傪峫偊傟偽丄愨懳偵彆偐傜側偄丅
乽......偁偄偨偨丄偨乿
丂偩偑丄偦偺梊憐偼僕乕儕儞僌偺婥偺敳偗偨傛偆側惡偱暍偝傟偨丅
乽......乿
乽傂偳偄側丄彆偗偰偁偘偨偮傕傝側傫偱偡偑偹乿
丂嬯徫偄偟側偑傜僕乕儕儞僌偑備偭偔傝恎懱傪婲偙偡丅
乽......偍慜乿
丂僋儗僀僌偼曫慠偲偟偰欔偔丅
乽壗偲傕......側偄偺偐乿
乽偦傝傖捝偄偱偡傛乿
丂偸偗偸偗偲摎偊偨僕乕儕儞僌偵丄僋儗僀僌偼捦傒偐偐傞丅
乽偄傗丄崱妋偐偵庱偺崪偑愜傟偨偼偢偩丅惗偒偰偄傜傟傞傢偗偑......乿
乽婥偺偣偄偱偟傚偆丅庱偺崪傪愜傜傟偰惗偒偰偄傞恖娫側傫偰偄傑偣傫傛乿
丂傢偞偲傜偟偔庱傪偝偡傝側偑傜丄僕乕儕儞僌偼棫偪忋偑偭偨丅
丂僋儗僀僌偼懅傪揻偒劅劅劅劅旝徫偆僕乕儕儞僌偺嬢尦傪撍偒曻偡丅
乽......婱條丄杺朄尛偄偠傖側偔偰晄巰幰偩偭偨偺偐乿
丂僕乕儕儞僌偼尐傪偡偔傔偰丅
乽偝傝婥側偔傂偳偄偙偲偄偄傑偡偹丄戝堁揳乿
乽婱條偵偼尵偄偨偄帠偑嶳偺傛偆偵偁傞傫偩偑側乿
乽劅劅劅劅婱曽払丄堦懱壗側偺乿
丂僋儗僀僌偲僕乕儕儞僌偼彮彈偺惡偵帇慄傪尛傞丅
丂彮彈偼彴偵傌偨傫偲嵗傝崬傫偱偄偨丅
丂庤偵帩偭偨廵偼昗揑傪掕傔偢丄彴偵廵岥傪岦偗偨傑傑劅劅劅劅2恖傪尒忋偘傞偦偺娽偼敀嬧偺偦傟偱側偔丄廮傜偐偄拑怓偵曄傢偭偰偄偨丅
乽壗偩偲尵傢傟偰傕側......乿
乽傑偁丄晄朄怤擖幰傒偨偄側傕偺偱偡乿
乽......偍慜側乿
乽壗偐娫堘偄傑偟偨偐丠乿
乽......偄傗乿
丂彮彈偼偦傫側2恖偺傗傝庢傝傪偍偲側偟偔暦偄偰偄偨偑丄
乽巇帠偑偁傞偺丅偩偐傜......乿
丂棫偪忋偑傝丄僗僇乕僩偺悶傪偼偨偔丅
乽亀巇帠亁丠乿
丂僋儗僀僌偼偦偺彮彈偺尵梩偵堘榓姶傪妎偊偨丅
乽巇帠丅側偺偵婱曽払偑幾杺傪偡傞偐傜乿
乽......暿偵壌偼偍慜偺幾杺傪偟偵棃偨栿偠傖側偄乿
丂偦偺曉帠偵彮彈偺娽偑娵偔側傝劅劅劅劅昞忣偑嵨憡墳偺偦傟偵曄傢傞丅
乽廵傪岦偗偨偔偣偵乿
乽偍慜偺曽偑愭偩偭偨傠偆偑丅惓摉杊塹偩乿
丂慺捈側栤偄偵丄僋儗僀僌偼嫃忎崅偵摎偊偨丅
乽偍慜偺梡帠傕壗幰側偺偐傕抦傜傫丅壌偼壌偺梡帠偱偙偙偵棃偨乿
乽......偦偆乿
丂僋儗僀僌偺尵梩傪暦偄偰丄彮彈偺昞忣偑傆偭偲廮傜偐偔側傞丅
乽側傜丄婱曽払偼嶦偝側偔偰偄偄傫偩傢乿
丂埨揼傪娷傫偩摰偼劅劅劅劅偲偰傕偙傟傑偱偺亀巰懱偺検嶻幰亁偲偼巚偊側偄傎偳壐傗偐偩偭偨丅
乽偪偭丄傗傝偵偔偄側乿
丂僋儗僀僌偼傏偦偭偲欔偒劅劅劅劅
乽偍偄乿
丂嵞傃彮彈偵岦偒捈偭偨丅
乽壗丠乿
丂僋儗僀僌偼彮彈偐傜扏偒棊偟偨廵傪廍偄劅劅劅劅扨搧捈擖偵恥偹傞丅
乽偙偺僶僇偱偐偄廵丅寴婥偺傕傫偠傖偹乕側丅偳偙偱庤偵擖傟偨乿
丂彮彈偼墴偟栙傞丅
乽偍偄乿
丂捑栙傪懕偗傞彮彈偵丄僋儗僀僌偼媗傔婑傞丅
乽劅劅劅劅摎偊傞偮傕傝偑側偄傫側傜丄偙偭偪偵傕峫偊偑偁傞傫乿
乽廵偭偰偦傕偦傕寴婥側傫偱偡偐偹乿
丂偦傟傑偱僋儗僀僌偲彮彈偺夛榖傪朤娤偟偰偄偨僕乕儕儞僌偑岥傪偼偝傫偩丅
乽栙傟杺朄巊偄乿
丂悈傪嵎偝傟偰僋儗僀僌偑攚屻傪嵘傒偮偗傞丅
乽壌偼丄偦偙偺偍忟偪傖傫偵暦偄偰傞傫偩丅......偳偆側傫偩乿
乽......偁側偨傕偦傕偦傕亀僇僞僊亁側偺偐偟傜乿
丂栤偄偵栤偄偱曉偟偨彮彈偺尵梩偵僋儗僀僌偼尵梩傪幐偄劅劅劅劅摢傪書偊傞丅
乽......偙偄偮乿
丂擇恖偺條巕傪尒偰丄僕乕儕儞僌偑巚傢偢悂偒弌偟偨丅
乽堦杮庢傜傟偪傖偄傑偟偨偹乿
乽劅劅劅劅傕偆偄偄乿
丂僋儗僀僌偼戝嬄偵懅傪揻偔丅
乽......偹偊乿
丂彮彈偑岥傪奐偄偨丅
乽壗偩乿
乽巹傕丄暦偄偰偄偄丠乿
丂僋儗僀僌偼夦鎎偦偆偵丄僕乕儕儞僌偼嫽枴怺偘偵彮彈傪尒偮傔傞丅
丂彮彈偼帺暘偺惓柺偵偄傞抝2恖傪傑偭偡偖偵尒忋偘偰恥偹偨丅
乽......巹偭偰丄庛偄丠乿
丂僋儗僀僌偲僕乕儕儞僌偼偍屳偄偺婄傪尒崌傢偣劅劅劅劅岎屳偵摎偊傞丅
乽壔偗暔偩側乿
乽旕忢幆側偔傜偄偵乿
丂彮彈偼偦偺傑傑2恖偺婄傪尒偮傔偰偄偨偑......傗偑偰棴懅偲嫟偵傐偮傝偲欔偄偨丅
乽婱曽払偵尵傢傟偰傕愢摼椡偑側偄傢乿
丂偦偺傑傑偔傞偭偲屻傠傪岦偔丅
乽......偍偄乿
丂彮彈偼嬱偗弌偟偨懌傪巭傔劅劅劅劅僋儗僀僌偺傎偆傪怳傝岦偄偨丅
乽傑偩丄梡偑偁傞偺丠乿
乽偦偆媫偖側偭偰乿
乽尵偭偨偱偟傚丅帪娫偑側偄偺乿
乽堦媥傒偡傞偔傜偄偺帪娫偼偁傞偩傠乿
丂僋儗僀僌偼彮彈偵廍偭偨廵傪嵎偟弌偟偰偵傗偭偲徫偭偨丅
乽偍慜偺巇帠傪庤揱偭偰傗傞丅偩偐傜丄偍慜傕壌偺巇帠傪庤揱偊乿
乽......庤揱偄側傫偐偄傜側偄乿
乽傑偀偦偆偄偆側丅偍慜偺僞乕僎僢僩偼亀恖娫亁偩傠丅......壌偺偼亀儌僲亁偩偐傜乿
乽......乿
丂僋儗僀僌偼偦偺応偵嵗傝崬傫偱彮彈偵帇慄傪嬤偯偗偰恥偹傞丅
乽暦偐偣傠傛丅劅劅劅劅偍慜偺昗揑偼扤偩丠乿
丂柍榑慺捈偵摎偊傞偲巚偭偰恥偹偨栿偱偼側偄丅偩偑丅
乽......亀僌僗僞僼=儃僢僔儏亁偲偄偆恖乿
丂偦偺柤慜偼偡傫側傝偲彮彈偺岥偐傜朼偓弌偝傟偨丅
丂劅劅劅劅僞乕僎僢僩偵懳偡傞旈庣媊柋偼側偄偲偄偆偙偲側偺偐丅
丂怓乆側巚榝偑摢傪傛偓偭偨偑丄偦傟偵偮偄偰婄偵偼弌偝偢丄
乽偦偆尵偆偙偲偐丅......摴棟偱乿
丂巆傝偺抏憅偺妋擣傪峴側偄側偑傜丄僋儗僀僌偑欔偄偨丅
乽僌僗僞僼=儃僢僔儏偑偙偙偵偄傞偺偐乿
乽......扤側傫偱偡偐乿
乽孯偺忣曬嬊偺姴晹偺1恖偩丅惓懱偼亀鍨鍟亁偩偑側乿
乽亀鍨鍟亁丠乿
丂偒傚偲傫偲偟偨婄偱彮彈偑暦偒曉偟劅劅劅劅彮偟崲偭偨傛偆偵尵偆丅
乽暘偐傞傛偆偵尵偭偰乿
乽忟偪傖傫偼亀鍨鍟亁偼抦偭偰傞偐丠乿
乽......歁擕峧梼庤栚偺憤徧偱乿
乽惗暔恾娪傒偨偄側夞摎偩側乿
丂尵偄偐偗偨彮彈偺尵梩傪惂巭偟偰丄僋儗僀僌偼尵梩傪宲偖丅
乽僱僘儈偵傕帡偰傞偟捁偵傕帡偰傞丅屆憙偵偄傟偽枴曽偺怳傝傪偟偰捁偺偦偽偵偄傞帪偼偦偪傜偵垽憐傪怳傞乿
乽......僗僷僀峴堊偱偡偐乿
丂僕乕儕儞僌偺尵梩偵僋儗僀僌偼桴偄偨丅
乽嵟廔揑偵偼僱僘儈偺偦偽偵傕捁偺偦偽偵傕偄傜傟側偔側偭偨偲偄偆偙偲偩丅......偨偩偙偄偮偑乿
丂偲僋儗僀僌偼彮彈傪巜偝偟偰尵偆丅
乽偙偄偮偑嶦偟偨楢拞偼偦傫側偙偲抦傜偝傟偪傖偄側偄偩傠偆偑側乿
丂僕乕儕儞僌偑擺摼偟偨傛偆偵桴偔丅
乽......偳偆偟偰婱曽払偵偦傫側偙偲偑傢偐傞偺丠乿
丂偨偩堦恖彮彈偑摼怱偑峴偐側偄偺偐丄搑榝偭偨昞忣偺傑傑恥偹傞丅
乽崙偺斴岇偺嫋偸偔偸偔偲偟偰偄傞崢敳偗嫟偩偐傜偝丅劅劅劅劅偩偐傜偙偦帺暘偺曐恎偵偼擬怱偩丅搝偑傗傜偐偟偨帠幚傪抦偭偰偄傟偽丄戝恖偟偔偮偄偰偔傞栿偑側偄丅嫲傜偔偙偄偮傜偼儃僢僔儏偑揔摉偵漵憿偟偨柦椷偵丄偨偩晹壓偲偟偰偮偄偰偒偨偩偗偩傠偆乿
乽偮傑傝巹偑嶦偟偨恖娫払偼丄壗傕抦傜偝傟偰偄側偄偺偹乿
丂彮彈偺摰偑旝偐偵撥傞丅偦傫側斵彈偺條巕傪僕乕儕儞僌偼偠偭偲尒偮傔偰偄偨偑......傗偑偰僋儗僀僌偺傎偆傪怳傝曉傝恥偹偨丅
乽劅劅劅劅偙偺崙偺孯偵壗偐巚偆張偑偁傞傛偆偱偡偑丠乿
乽搝傜偲偼妋幏偑偁傞乿
丂楲壓偺岦偙偆傪尒傗傝丄僋儗僀僌偼偄傑偄傑偟偦偆偵尵梩傪揻偔丅
乽桪廏側晹壓偑壗恖傕嶦偝傟偰偄傞丅搝傜偺柍擻偝偲丄棙屓偺堊偵乿
乽......乿
乽愴憟傪惗嬈偵偟偰偄傞埲忋壌偵傕晹壓払偵傕妎屽偼偁傞丅偩偑......亀僸儏僎儖儀儖亁偺審偼嫋偟擄偄乿
乽亀僸儏僎儖儀儖亁......乿
乽亀徚偊偨愴栶亁偩丅劅劅劅劅偁傑傝偵傕晄帺慠夁偓偨乿
丂僋儗僀僌偼懅傪揻偔丅
乽媤傪偲傞偲偐丄偦偆偄偆栿偠傖側偄偑劅劅劅劅帠偑僌儗乕偵側偭偰偄傞偺偼偳偆傕懻偗側偄丅惗懚幰傪庢傝崬傫偩傝偼偟偰傒偨偑丄2擭宱偭偨崱傕壗偑婲偙偭偨偺偐偼偼偭偒傝偟側偄乿
乽......乿
乽儃僢僔儏偼偦偺嶌愴偺巟帩幰偺1恖偩乿
丂恎峔偊傞彮彈丅偦偺條巕傪墶栚偱尒偰丄僋儗僀僌偼嬯徫偟偨丅
乽偦偆晐偄婄偡傞側偭偰丅偍慜偺妉暔傪墶庢傝偡傞婥偼偹偉傛丅......儃僢僔儏傕扨側傞嬵偺1偮偵夁偓側偄乿
乽偳偆偟偰偦偆抐掕偱偒傞傫偱偡丠乿
丂嫽枴怺偘偵僕乕儕儞僌偑恥偔丅
乽偳偆峫偊偰傕孯偩偗偱偼側偟偊側偄亀壗偐亁傪峴側偭偰偄偨偐傜偩乿
乽......乿
乽巰傫偩晹壓払偺巰懱傪旈枾棤偵夞廂偟丄専巰傪峴側偭偨乿
丂偟偽偟偺捑栙偺偺偪僋儗僀僌偼戝偒偔懅傪揻偄偰......尵梩傪懕偗偨丅
乽巰場偼妋偐偵懡戝側奜彎偵傛傞傕偺偩偑劅劅劅劅晹壓払偺嵶朎偼丄捠忢偺恖娫偺偦傟偲偼慡偔堘偆傕偺偵曄幙偟偰偄偨偺偝乿
侕
丂僕儞僕儍乕偑偙偺応強傪敪偭偰偐傜悢帪娫屻丅
丂壌偼崱屻偺孭楙偺梊掕偵偮偄偰榖偟崌偆偨傔偵僇僼僃僥儕傾偱儕儏僔儏僇偝傫傪懸偭偰偄偨丅
丂婛偵梉怘偵巜掕偝傟偰偄傞帪娫偐傜3帪娫掱丅僇僼僃僥儕傾偺拞偼傑偽傜偵恖偑嵗偭偰偄傞掱搙偩丅
乽偛傔傫側偝偄丄偙傫側帪娫傑偱乿
丂傗偑偰尰傟偨斵彈偼怽偟栿側偝偦偆偵尵偄側偑傜壌偺惓柺偺惾偵嵗偭偨丅壌偼寉偔徫偭偰墳偊傞丅
乽偄偊丄巇帠偱偡偐傜乿
丂幚嵺丄嵟弶偼椪帪怑堳偲偟偰屬傢傟傞梊掕偩偭偨壌偵偼妎偊側偔偰偼側傜側偄偙偲偑嶳偺傛偆偵偁傞偺偩丅
乽愭偵栚傪捠偟偰傕傜偊傑偡丠乿
丂偦偆尵偭偰彂椶偺懇傪搉偝傟偨丅愭摢偐傜弴偵儁乕僕傪孞傞丅偞偭偲栚傪捠偟劅劅劅劅
乽......亀僸儏僎儖儀儖亁乿
丂栚偵巭傑偭偨抧柤傪丄壌偼柍堄幆偵欔偄偨丅
乽......偁偁丄妋偐柧惎憪偑孮惗偟偰偄傞偺偱桳柤側張偱偡偹乿
丂曉偭偰偒偨尵梩偵丄堄幆偑怺偔捑傒偙傓丅
丂劅劅劅劅亀柧惎憪亁丅
丂摢偺拞偵晜偐傇丄晽偵梙傟傞敀偔橰偘側栰偵嶇偔壴丅堦柺偵嶇偒屩傝丄寧岝傪庴偗偰崹偒嬻偵岝傪挼偹曉偡丅
丂傗偨傜偲戝偒偔挳偙偊傞帺暘偺屇媧偲摦湩丅尒偊側偄揋偵澦偝傟偰偄偔拠娫丅敀偄壴傃傜偵崀傝偐偐傞愒丅
丂栚偺慜傪暍偆峠怓偺僼傿儖僞乕劅劅劅劅
乽......儅僢僩偝傫丠乿
丂搨撍偵怤擖偟偰偒偨惡偵丄堄幆傪嫮堷偵栠偝傟傞丅
丂搑榝偭偨傛偆偵壌傪尒偮傔偰偄傞斵彈丅
乽劅劅劅劅偡偄傑偣傫乿
丂擼偵晜偐傇塮憸傪寽柦偵捛偄暐偆丅......偁偺婰壇偵怗傟傞儌僲偼丄枹偩偵壌偺惛恄傪愗傝崗傓丅
乽戝忎晇偱偡偐丠丂婄怓偑乿
乽偊偊乿
丂偦偆偼揱偊偨傕偺偺丄晜偐傫偩塮憸偼惗敿偵偼擼偺帇奅偐傜偼棧傟側偄丅
丂斵彈偼怱攝偦偆偵壌偺婄傪擿偒崬傫偱偄偨偑劅劅劅劅偄偒側傝婘偵峀偘偰偄偨彂椶傪偐偒廤傔偨丅丂偦偺傑傑彂椶傪書偊傞偲婘偺偙偪傜懁傊夢偭偰偒偰丄壌偺庤庱傪柍憿嶌偵偲傞丅
丂梊應偟摼側偄偦偺峴摦偵丄偮偄斀幩揑偵榬傪傂偄偨丅
乽......偁乿
丂寉偔嬃偄偨傛偆側斵彈偺婄丅
乽偡偄傑偣傫......偁偺丄戝忎晇偱偡偐傜乿
丂嵾埆姶傪姶偠劅劅劅劅欜歭偵幱偭偨弖娫丅
乽偙傜乿
丂嵶偄巜偑壌偺妟傪寉偔撍偮偄偨丅
乽......乿
丂曫慠偲栚偺慜偺斵彈傪尒偮傔傞丅斵彈偼旝徫偭偰劅劅劅劅
乽偛傔傫側偝偄丅......偱傕偦偺條巕偠傖亀戝忎晇亁偲偐尵傢傟偰傕怣梡偱偒側偄偱偡乿
乽偄傗......偱偡偑......乿
丂偦傫側壌偺尵偄暘傪暦偄偰偄傞偺偐偄側偄偺偐丄斵彈偼嵞傃庤庱傪偲傞丅
乽偨傑偵偼偍巓偝傫偺尵偆偙偲傕暦偔傕偺偱偡傛丄儅僥傿傾僗孨乿
丂埆媃偭巕偺傛偆側徫婄偱埇傞斵彈偺庤偺椡偼堄奜偵嫮偔劅劅劅劅偄傗丄幚嵺偵偼偦傟傎偳嫮偔側偐偭偨偺偐傕偟傟側偄偑丄偦偺帪偺壌偼掞峈傜偟偄掞峈傕偣偢丄儕儏僔儏僇=儈儔乕偲偄偆彈惈偺朷傓傑傑偵廬偍偆偲巚偭偨偺偩丅
丂曻怱......偟偰偄偨偺偩傠偆偐丅
丂偦偺帪尒偣偨斵彈偺徫婄偼丄偒偭偲亀杮暔亁偱偁偭偨偩傠偆偐傜丅
侕
乽偦偙偵嵗偭偰偰偔偩偝偄丄偡偖栠傝傑偡偐傜乿
丂偦傟偩偗尵偭偰丄斵彈劅劅劅劅儕儏僔儏僇偝傫偼晹壆傪弌偰峴偭偨丅
丂楢傟偰偙傜傟偨偺偼丄儔儃偺怑堳偺寶暔偺堦幒偩偭偨丅
丂姪傔傜傟偨偼偄偄傕偺偺丄儀僢僪偵偡偖偵崢妡偗傞偺傕鏢鏞傢傟偰......壌偼偦偺晹壆傪偖傞偭偲尒夞偟偨丅
丂嵍塃懳徧偵攝抲偝傟偰偄傞暻嵺偵婑偣傜傟偨儀僢僪偲彫偝偄婘丅偩偑曅曽偺僙僢僩偼巊傢傟偰偄側偄傛偆偩丅
乽......偁傜乿
丂斷偺奐偔壒丅
乽亀嵗偭偰偰偔偩偝偄亁偭偰尵偭偨偺偵乿
乽偡偄傑偣傫乿
乽婄怓傑偩椙偔側偭偰傑偣傫傛......偒傖丠乿
丂偙偪傜偵岦偐偭偰偒偨斵彈偺恎懱偑搨撍偵傛傠偗偨丅
乽偁傇側......乿
丂壌偼斀幩揑偵斵彈偺恎懱傪庴偗巭傔傞丅偦偺恎懱傪書偒偐偐偊偨忬懺偱屻傠偵搢傟崬傒劅劅劅劅栚偺慜偵壩壴偑嶶偭偨丅
丂斵彈偺恎懱傪書偊偨傑傑儀僢僪偺忋偱旾傪偮偄偰恎懱傪巟偊偨傕偺偺丄偦偺岦偙偆偺暻偵摢傪傇偮偗偰偟傑偭偨傛偆偩丅
乽偁偨偨......乿
丂帺暘偺摢傪柍堄幆偵偝偡傞丅尰忬傪攃埇偡傞偺偵彮偟帪娫偑偐偐偭偨丅
丂捝傒傪慽偊傞惡偵嬃偄偨偺偐丄斵彈偑峇偰偰婲偒忋偑傞丅
乽劅劅劅劅儅僢僩偝傫丄戝忎晇偱偡偐!?乿
丂忋偐傜斵彈偺惡偑偡傞丅
乽傊丄暯婥偱偡......乿
丂娽傪奐偗偨搑抂丄崌傢偝傞帇慄丅戝偒側摰丅媧偄崬傑傟偦偆側怺偄拑怓劅劅劅劅
丂......壌偼搨撍偵変偵婣傞丅
丂傑偢偄丅......偙偺巔惃偼旕忢偵傑偢偄丅
丂摨帪偵斵彈傕偦傟偵婥偑偮偄偨偺偐丄峇偰偰恎懱傪棧偟偨丅
乽偛丄偛傔傫側偝偄偭乿
乽劅劅劅劅偄偊乿
丂壌偼恎懱傪婲偙偡丅
丂斵彈偼扙偘偨僸乕儖傪廍偭偰棜偄偨丅
丂偁偁丄彴偺斅偵纟偑偼偝傑偭偨偺偐丅幒撪偲偼偄偊傕偲傕偲攑壆偩丅栘偺彴偼偐側傝榁媭壔偟偰偄傞丅
乽......乿
丂婘偺偦偽偵抲偄偰偁偭偨彫偝側堉巕丅斵彈偼偦傟傪堷偄偰偒偰丄儀僢僪偺榚偵抲偄偨丅
丂偦偺傑傑崢妡偗偰......彫偝側惡偱尵偆丅
乽墶偵側偭偰偰偔偩偝偄乿
乽偟偐偟乿
乽婄怓埆偄忋偵摢傇偮偗偨傫偱偡偐傜乿
乽......乿
乽戝恖偟偔尵偆偙偲暦偒側偝偄乿
丂......偦偺婄偑偆偭偡傜庨偔愼傑偭偰偄偨偺偼懡暘婥偺偣偄偱偼側偄偩傠偆丅嫮婥偺尵梩偼徠傟塀偟側偺偩偲屽偭偰壌偼戝恖偟偔孋傪扙偄偱墶偵側偭偨丅
丂偦偺傑傑丄栚傪寉偔暵偠傞丅
丂惓捈側張丄擼撪偵晜偐傫偱偄偨塮憸偼愭掱摢傪傇偮偗偨弖娫偵悂偭旘傫偱偟傑偭偰偄偨丅
丂......挳偙偊偨偐傕偟傟側偄丅
丂愭掱傑偱偲偼堄枴偺堘偆丄寖偟偄摦湩傪......挳偄偰偄偨偐傕偟傟側偄丅
丂斵彈偑傛傠偗偨弖娫丄壌偼斵彈偺恎懱傪偐偽偆偨傔偵......斵彈偺摢傪書偊崬傫偩丅壌偺惡偵嬃偄偰旘傃婲偒傞傑偱丄斵彈偺摢偼壌偺嫻偺忋偵偁偭偰丅
丂偦偺弖娫偺旲傪偔偡偖傞扺偄娒偄崄傝偲丄屇媧偲丄廮傜偐偄姶怗偵婥偑偮偄偨帪劅劅劅劅怱壒偑挼偹忋偑偭偨丅
丂劅劅劅劅傂傗傝偲偟偨姶怗傪丄妟偵姶偠傞丅
丂暵偠偰偄偨豳傪奐偔丅丂妟偵忔偣傜傟偨傕偺偵寉偔怗傟傞丅......屌偔峣傜傟偨僴儞僇僠丅
乽......婥媥傔偱偡偗偳乿
丂斵彈偑壌偺帇慄偵婥偑偮偄偨偺偐丄偙偪傜傪岦偄偰旝徫偆丅
丂怱偺墱掙偱殤偔惡偑丄桸偒忋偑傞憐偄偵寈崘傪梌偊傞丅
丂朷傓側丅偍慜偵偦偺帒奿偼側偄丄偲丅
乽桳擄偆偛偞偄傑偡乿
丂壌偼斵彈偵徫偄曉偟偰劅劅劅劅嵞傃栚傪暵偠偨丅
丂斵彈偺帇慄偵旝偐側偔偡偖偭偨偝傪姶偠側偑傜丅
丂殤偔惡偵壌偼摎偊傞丅
丂......斵彈偺徫婄偑尒偨偄丅偦偆婅偆偙偲帺懱偼嵾偱偼側偄偩傠偆......丠