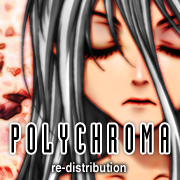廃墟にて - 動機ある必然 -:GateOdyssey:novels|創作小説集団CRAFTWORX(クラフトワークス)
廃墟にて - 動機ある必然 -
Outside already-known
2日目の掃除は、午前中で片をつけた。
実の処、床面積だけで言えば使用するのは1階だけで十分だ。あえて2階に手をつけたというのは────単に自分が着替えに使える場所を確保したかった、というだけだった。
「マットー」
下から聴こえる声。あれはマロウか。
「何だー?」
大声で返事をすると、足音が階段へ近づいてきて......止まった。
「あのね、リュシィが呼んでる」
2階を覗き込む顔に向かって返事をする。
「分かった。どこに行けばいい?」
「外」
────そりゃ随分範囲が広いな。
「すぐに行く、って伝えてくれるか」
そう言うとマロウは頷いて、元来た方向へ走っていった。
バッグのファスナーを閉め立ち上がり、開け放していた窓を閉じる。そのまま軽く身体を伸ばして────俺は階段を降り、外に出た。
リュシュカさんは俺たちの宿舎からちょっと離れた位置に佇んでいた。
「お待たせしました」
子供達が宿舎の裏で駆け回ってるのが見える。
「いえ。お疲れ様です」
彼女は微笑んで......時間をちらっと確認した。
「あの......ちょっと早いんですけど時間がかかっちゃいそうなので、お昼ご飯を食べながら午後の打合せをさせていただけないかと思って」
そう言われて、俺は自分の腕時計を見た。
11時30分。確かに微妙な時間だ。
「いいですよ。────あいつらは?」
子供達のほうをちらとみると、
「メニューは前日のうちに作ってしまうんです。それを元に朝、一緒に作りおきして冷蔵庫に入れてありますから、お腹が空いたら勝手に食べると思います」
......食べ終わった後の散らかり具合を考えると少々不安がよぎったが、まぁそのときはそのときだな。
「わかりました」
「それじゃ、行きましょう」
「はい」
俺はリュシュカさんについて食堂のある棟に向かって歩きだした。
まだ人がまばらな仮設食堂の片隅で、俺は自分の分の食事を買って戻ってきた。
リュシュカさんはコーヒーだけを脇において、椅子に腰掛けている。
「ご自分の分は?」
俺が訊ねると、彼女はくすっと笑って言った。
「あともうちょっとで仕上がるから待ってくださいって」
ちょっと早すぎたということか。しかし、国が絡んでくるプロジェクトってのは何か違うよな。職員のためとはいえカフェテリアを丸ごと持ってきちまうんだから。
「......マットさん......」
リュシュカさんがコーヒーにポーションミルクを落としながら訊ねる。
「それ、どこに入るんですか」
視線の先は俺の持ってきたトレイ。俺は苦笑して答えた。
「......普通に胃に」
リュシュカさんはしばらく沈黙して、『......うらやましい』と呟いた。
思わず問い返す。
「ダイエットでもしてるんですか?」
「してませんけれど......」
「でしょうね。必要なさそうですし」
そう言うと、リュシュカさんは目を丸くして......急に吹き出した。
「やだ、マットさん。その言葉はイエローカードだと思いますよ?」
言いながら、彼女は口を抑えて、肩を震わせて笑っている。
「す、すみません」
「いえ、悪気がないのは分かりますから。でも気をつけたほうがいいですね」
ラボに限らず、オフィスでのセクシャル・ハラスメントについてのガイドラインはかなり厳しいものになってきている。......気をつけねば。
黙々とパンを消費していると、カウンターからリュシュカさんを呼ぶ声が聴こえた。
「あ、出来たみたいです。とってきますね」
「はい」
コーヒーに口をつけて......目で彼女の背中を追う。
マグカップをトレイに置いて、頬杖をついた。
「お待たせしました」
リュシュカさんがトレイに出来たての料理を載せて戻ってきた。
「さ、始めましょうか」
そのままトレイを脇に置き、書類を広げ始める。
「あの......リュシュカさん」
「はい」
「食べないんですか......?」
トレイに載っているのはチキンドリア。上にかかっているチーズがくつくつ言っている。
「ああ」
リュシュカさんがちょっと気恥ずかしそうに笑う。そして、小さな声で、答えた。
「猫舌なんです」
成程。納得。
「.......午後から子供達とスタッフに、明日から開始される訓練の具体的な説明をお願いしようと考えてます。可能なら、実際に手本を見せていただければと思うのですが」
「分かりました」
リハビリ中の身だが、毎日の射撃訓練は欠かしてはいない。デモンストレーション程度なら問題ないだろう。
「有難うございます。......それでですね」
打合せはとんとん拍子に進み────ドリアが程よく冷めた頃、休憩がてら食事を再開した。
「......リュシュカさん」
食事が終わり、彼女がコーヒーに口をつけたあたりでふと尋ねる。
「はい」
「あいつらは......最終的にはどうなるんでしょう」
リュシュカさんはしばし黙り込み────ぽつりと言った。
「USFEへ侵攻するための切り札として......戦場へ赴くことになるでしょうね」
「......」
「USFEに長距離戦略兵器を含む航空兵力が一切通用しない現状......私達はこの計画に希望を託すよりありません」
俺はリュシュカさんの言葉を聞きながら、2杯目のコーヒーに口をつけた。────それは、多少煮つまり気味になっていたこともあり、とても苦く感じた。
無意識に溜息を吐き────それに気が付いて思わず中空に視線をやる。
俺があいつらに教える技術は、『その日』をより早く近づけるためのものなのだ。
打合せから2時間後。
俺は子供達とラボのメンバーの前で、訓練スケジュールと内容の具体的な説明を始めた。
「単純ではありますが、まずはセオリー通りあれら静止目標への精密射撃演習を集中的に行います」
説明しながら俺は用意してもらったターゲットを指し示す。そのまま塀から離れて歩き出し────ある一点で止まって振り返った。
「最初はここ────50メートルの位置からです。正確に当てることを最優先とし、精度の上昇と共にシューティングの速度を上げ、標的までの距離も伸ばしていきます」
もう一度俺は移動し、再び立ち止まる。
「ここが200メートル。最終目標はここから4秒で6つのターゲットの中心付近に全弾命中させることとします」
俺はぐるっと周りを見回した。
「質問は?」
「異議がある」
ミントが言う。
「照準を合わせて命中させるのに、目標1つにつきコンマ7秒以下ということだろう」
「不服か?」
「......」
「あくまで『目標』だ。訓練期間中に達成してくれればいい」
ミントは黙っている。『不可能だ』と言うのにも抵抗があるのだろう。
やれやれ。
俺は約200メートルの位置へ移動して────そのまま、用意してあったFN57を手に取った。
「......『でざーといーぐる』は?」
ローレルの一言に苦笑する。
「あれで連射は無理だ」
破壊力が強すぎる上、反動が大きすぎて射線を維持できない。
俺は、ターゲットに向けてすっと構え────そのまま6発撃ち放った。
ミントのほうを振り返る。
「────俺でもこのくらいはできる。お前達なら難なくクリアすると思うけどな」
「......2秒、ってところね」
ジンジャーが呟いたのが聴こえた。────さっきまで塀に設置されていた目標は1つ残らず破片になっている。
「すげー......」
「発射音1つにしか聴こえなかったー!」
子供達の声。
「最初は正確に当てることに集中すればいい」
頷くミント。
「それでは、明日からお願いします」
俺はそういって、その場を締めた。
皆が解散した後、リュシュカさんが声をかけてきた。
「......すごいですね」
「大したことはないです。動く的じゃないし」
俺は苦笑する。
「それでも......やはり、話に聞くだけと実際にみせてもらうのでは全然違うんですね」
そこまで言われると妙に照れ恥ずかしい。
「......『教授』なら1秒半ですよ」
俺はさり気なく話の方向を変えた。
「『教授』?」
リュシュカさんが聞き返す。
「士官学校時代の教官です。非常に優れた技能を持った教官には、自然とそういう尊敬のこもったあだながつくものなんですよ」
ふうん、と頷くリュシュカさん。どのくらいの技術差なのか、把握しづらいのだろう。
......不意にいたずら心が起きた。
「......やってみますか?」
「はい?」
リュシュカさんが俺の顔をまじまじと見た。
「私......ですか?」
「ええ」
彼女は遠慮がちに答える。
「でも、私、銃は持っていませんから......」
俺は置いてあったFN57を手に取った。
弾倉を確認する。十分な弾数は残っていた。
「派遣元の支給品です。女性も同じモノを使用してます」
俺は銃身のほうを持ってリュシュカさんに差し出す。おずおずと、彼女は銃を受け取った。
「......重いんですね」
「そりゃあ」
思わず笑みが零れる。
「それでも、こっちに較べればかなり軽いですよ」
自分の上着の左腕脇を指差して言った。上着の下にはデザートイーグルが入っている。
俺は先ほどと同じ場所に、ターゲットを設置した。
リュシュカさんはじっと銃を持つ自分の手を見つめて────ゆっくりと射撃位置に立つ。
横から覗き込んで、軽く銃身を持って位置を修正した。......小さいな、手。
「ここが照門、これが照星。門から星を覗き込んで、その先に目標物があれば命中します。完全に中心に合わせるよりも、ほんの少し照星が下に位置するように意識して構えた方がいいです」
照準の合わせ方を説明する。
「脇はしめて」
「はい」
返事を聞いて、俺は彼女から少し離れた。
ゆっくり、丁寧に発射音が鳴る。
弾はほとんどそれて────最後の1つがかろうじてかすったのか、一番左端の目標の端が砕けた。
「ふふ。......やっぱり、ダメみたいですね」
苦笑しながらリュシュカさんは俺にFN57を返す。受け取って、俺は自分の鞄にそれをしまい込んだ。
突然鳴り出す呼出音。────リュシュカさんが胸ポケットから携帯電話を取り出して、俺に目礼したあと電話に出た。
「はい、ミラーです。......はい。......わかりました、すぐ戻ります」
短い会話のあと彼女は電話を切り、俺の方へ向いて行った。
「指揮所に連絡が来ているようなので、ちょっと行ってきますね」
「はい」
俺は軽く手を振って、駆け出すリュシュカさんの背中を見送った。
目標を片付けるため、外壁の裏に向かう。
────微弱な電子音が聞こえる。
音の出所を求め、俺は周囲を見回した。
それは程なく見つかった。────発射された弾の道筋を計測して、解析するための機械だ。俺としてはこういう機械はあまり信用できないのだが、少し気になってディスプレイを覗き込んだ。
......何だこれは。
ディスプレイに表示された結果を、俺は思わず凝視した。
恐らく先程リュシュカさんが撃った結果だろう。
『1射から5射、目標外。6射、目標至近。命中率0%』
ここまでは、先ほど見たままの内容。だが。
『弾道誤差0.01%以下。射線制御レベルS++』
『S++』......曲撃ちのレベルだぞ、それは。故障か?
俺でさえ、精密射撃時の精度は『A〜A+』がせいぜいだというのに......
しばらくディスプレイを見つめ......おもむろに機械のスイッチを切った。
何故かは分からない。
先程のリュシュカさんの苦笑が脳裏をかすめた。
扉を開けると、オペレータが『主任、こちらです』と呼びかけてきた。
そのままリュシュカはデスクに寄り、電話を取る。
「はい。......ええ......」
次の瞬間、彼女の表情が曇った。.......が、やがて笑顔を作って応える。
「......いえ。大丈夫です。毎年のことですし......はい。了解しました。では」
簡単に受け答えすると、リュシュカはそのまま受話器を置き、オペレータに『有難う』と言って指揮所を出た。
そのまま建物の裏へ行くと────溜息をつく。
電話は明日の来訪者についてのものだった。
しばらく足元を見つめ────リュシュカは軽く両手で気合を入れるように自分の頬を叩いた。
自分のトラブルは自分で解決しなければならないはずだ。
例えそれが......いわれのない内容であっても。
次の日は、ノックの音がする前に身支度は済ませてしまった。
「おはようございます」
リュシュカさんは昨日同様笑顔で入ってきたが────心なしか顔色が悪く見える。
「おはようございます。.......リュシュカさん?」
「はい?」
明るく返事をする彼女。
「......あの......大丈夫......ですか」
「え......調子悪そうに見えますか?」
手元のラップトップを操作しながら、彼女は答えた。
「昨日あまり眠れなくて......そのせいかもしれませんね。枕が変わると寝つきが変わるっていいますし」
......それくらいなら、いいのだけど。
「────そうだ、マットさん。今日、見学者が来ることになっているんです」
「......見学?」
「ええ。上の指示で......年に2回ほど、新人研修なども兼ねて二種と三種で互いの施設を視察に行くんです。今は私達三種の施設は工事のためほとんど稼動してないですから、こちらを見に来ることになったんでしょう」
笑顔のまま、説明してくれる彼女。何とも不自然な感じのする────
『彼女、他人と思っていたらどちらかというと笑顔で武装するから』
不意にアヤさんの言葉が脳裏をよぎる。
そうだ、この表情は会ったばっかりの頃の『防御』の表情────
昨日の約束通り子供達の食べ終わった皿を洗い、外へ出る。
訓練開始まであと30分。
最後の打合せをしている最中だった。
「では────」
リュシュカさんが書類に目を落とし、ふと顔を上げ......そのまま俺の顔を凝視する。
「......?」
俺は途惑い......気が付いた。────彼女が見ているのは、俺の後ろ......?
「続きを」
気付かなかった振りをして、俺はリュシュカさんを促した。
「あ、はい、すみません」
リュシュカさんは書類に視線を戻し、残りをざっと俺に説明した。
「了解しました」
「ではお願いします」
彼女はファイルを閉じ、後ろを向いて歩き出し......足を止め、一点を凝視した。
その視線の先を辿る。
線の細い、銀縁の眼鏡をかけた俺と同じか少し年上の男。そしてその隣には寄り添うように立つ銀色の髪をポニーテールにした女の子。
────やがて、リュシュカさんは振り切るように視線をそらし、指揮所の方向へ歩いていく。
男の視線は、まっすぐ彼女の背中を射続けていた。
「────全て記憶しておけ、アクセラ。いずれお前たちが滅ぼすべき『敵』だ」
男の声に少女はか細い、感情に乏しい声で応えた。
「......はい、マスター」
実の処、床面積だけで言えば使用するのは1階だけで十分だ。あえて2階に手をつけたというのは────単に自分が着替えに使える場所を確保したかった、というだけだった。
「マットー」
下から聴こえる声。あれはマロウか。
「何だー?」
大声で返事をすると、足音が階段へ近づいてきて......止まった。
「あのね、リュシィが呼んでる」
2階を覗き込む顔に向かって返事をする。
「分かった。どこに行けばいい?」
「外」
────そりゃ随分範囲が広いな。
「すぐに行く、って伝えてくれるか」
そう言うとマロウは頷いて、元来た方向へ走っていった。
バッグのファスナーを閉め立ち上がり、開け放していた窓を閉じる。そのまま軽く身体を伸ばして────俺は階段を降り、外に出た。
リュシュカさんは俺たちの宿舎からちょっと離れた位置に佇んでいた。
「お待たせしました」
子供達が宿舎の裏で駆け回ってるのが見える。
「いえ。お疲れ様です」
彼女は微笑んで......時間をちらっと確認した。
「あの......ちょっと早いんですけど時間がかかっちゃいそうなので、お昼ご飯を食べながら午後の打合せをさせていただけないかと思って」
そう言われて、俺は自分の腕時計を見た。
11時30分。確かに微妙な時間だ。
「いいですよ。────あいつらは?」
子供達のほうをちらとみると、
「メニューは前日のうちに作ってしまうんです。それを元に朝、一緒に作りおきして冷蔵庫に入れてありますから、お腹が空いたら勝手に食べると思います」
......食べ終わった後の散らかり具合を考えると少々不安がよぎったが、まぁそのときはそのときだな。
「わかりました」
「それじゃ、行きましょう」
「はい」
俺はリュシュカさんについて食堂のある棟に向かって歩きだした。
まだ人がまばらな仮設食堂の片隅で、俺は自分の分の食事を買って戻ってきた。
リュシュカさんはコーヒーだけを脇において、椅子に腰掛けている。
「ご自分の分は?」
俺が訊ねると、彼女はくすっと笑って言った。
「あともうちょっとで仕上がるから待ってくださいって」
ちょっと早すぎたということか。しかし、国が絡んでくるプロジェクトってのは何か違うよな。職員のためとはいえカフェテリアを丸ごと持ってきちまうんだから。
「......マットさん......」
リュシュカさんがコーヒーにポーションミルクを落としながら訊ねる。
「それ、どこに入るんですか」
視線の先は俺の持ってきたトレイ。俺は苦笑して答えた。
「......普通に胃に」
リュシュカさんはしばらく沈黙して、『......うらやましい』と呟いた。
思わず問い返す。
「ダイエットでもしてるんですか?」
「してませんけれど......」
「でしょうね。必要なさそうですし」
そう言うと、リュシュカさんは目を丸くして......急に吹き出した。
「やだ、マットさん。その言葉はイエローカードだと思いますよ?」
言いながら、彼女は口を抑えて、肩を震わせて笑っている。
「す、すみません」
「いえ、悪気がないのは分かりますから。でも気をつけたほうがいいですね」
ラボに限らず、オフィスでのセクシャル・ハラスメントについてのガイドラインはかなり厳しいものになってきている。......気をつけねば。
黙々とパンを消費していると、カウンターからリュシュカさんを呼ぶ声が聴こえた。
「あ、出来たみたいです。とってきますね」
「はい」
コーヒーに口をつけて......目で彼女の背中を追う。
マグカップをトレイに置いて、頬杖をついた。
「お待たせしました」
リュシュカさんがトレイに出来たての料理を載せて戻ってきた。
「さ、始めましょうか」
そのままトレイを脇に置き、書類を広げ始める。
「あの......リュシュカさん」
「はい」
「食べないんですか......?」
トレイに載っているのはチキンドリア。上にかかっているチーズがくつくつ言っている。
「ああ」
リュシュカさんがちょっと気恥ずかしそうに笑う。そして、小さな声で、答えた。
「猫舌なんです」
成程。納得。
「.......午後から子供達とスタッフに、明日から開始される訓練の具体的な説明をお願いしようと考えてます。可能なら、実際に手本を見せていただければと思うのですが」
「分かりました」
リハビリ中の身だが、毎日の射撃訓練は欠かしてはいない。デモンストレーション程度なら問題ないだろう。
「有難うございます。......それでですね」
打合せはとんとん拍子に進み────ドリアが程よく冷めた頃、休憩がてら食事を再開した。
「......リュシュカさん」
食事が終わり、彼女がコーヒーに口をつけたあたりでふと尋ねる。
「はい」
「あいつらは......最終的にはどうなるんでしょう」
リュシュカさんはしばし黙り込み────ぽつりと言った。
「USFEへ侵攻するための切り札として......戦場へ赴くことになるでしょうね」
「......」
「USFEに長距離戦略兵器を含む航空兵力が一切通用しない現状......私達はこの計画に希望を託すよりありません」
俺はリュシュカさんの言葉を聞きながら、2杯目のコーヒーに口をつけた。────それは、多少煮つまり気味になっていたこともあり、とても苦く感じた。
無意識に溜息を吐き────それに気が付いて思わず中空に視線をやる。
俺があいつらに教える技術は、『その日』をより早く近づけるためのものなのだ。
†
打合せから2時間後。
俺は子供達とラボのメンバーの前で、訓練スケジュールと内容の具体的な説明を始めた。
「単純ではありますが、まずはセオリー通りあれら静止目標への精密射撃演習を集中的に行います」
説明しながら俺は用意してもらったターゲットを指し示す。そのまま塀から離れて歩き出し────ある一点で止まって振り返った。
「最初はここ────50メートルの位置からです。正確に当てることを最優先とし、精度の上昇と共にシューティングの速度を上げ、標的までの距離も伸ばしていきます」
もう一度俺は移動し、再び立ち止まる。
「ここが200メートル。最終目標はここから4秒で6つのターゲットの中心付近に全弾命中させることとします」
俺はぐるっと周りを見回した。
「質問は?」
「異議がある」
ミントが言う。
「照準を合わせて命中させるのに、目標1つにつきコンマ7秒以下ということだろう」
「不服か?」
「......」
「あくまで『目標』だ。訓練期間中に達成してくれればいい」
ミントは黙っている。『不可能だ』と言うのにも抵抗があるのだろう。
やれやれ。
俺は約200メートルの位置へ移動して────そのまま、用意してあったFN57を手に取った。
「......『でざーといーぐる』は?」
ローレルの一言に苦笑する。
「あれで連射は無理だ」
破壊力が強すぎる上、反動が大きすぎて射線を維持できない。
俺は、ターゲットに向けてすっと構え────そのまま6発撃ち放った。
ミントのほうを振り返る。
「────俺でもこのくらいはできる。お前達なら難なくクリアすると思うけどな」
「......2秒、ってところね」
ジンジャーが呟いたのが聴こえた。────さっきまで塀に設置されていた目標は1つ残らず破片になっている。
「すげー......」
「発射音1つにしか聴こえなかったー!」
子供達の声。
「最初は正確に当てることに集中すればいい」
頷くミント。
「それでは、明日からお願いします」
俺はそういって、その場を締めた。
†
皆が解散した後、リュシュカさんが声をかけてきた。
「......すごいですね」
「大したことはないです。動く的じゃないし」
俺は苦笑する。
「それでも......やはり、話に聞くだけと実際にみせてもらうのでは全然違うんですね」
そこまで言われると妙に照れ恥ずかしい。
「......『教授』なら1秒半ですよ」
俺はさり気なく話の方向を変えた。
「『教授』?」
リュシュカさんが聞き返す。
「士官学校時代の教官です。非常に優れた技能を持った教官には、自然とそういう尊敬のこもったあだながつくものなんですよ」
ふうん、と頷くリュシュカさん。どのくらいの技術差なのか、把握しづらいのだろう。
......不意にいたずら心が起きた。
「......やってみますか?」
「はい?」
リュシュカさんが俺の顔をまじまじと見た。
「私......ですか?」
「ええ」
彼女は遠慮がちに答える。
「でも、私、銃は持っていませんから......」
俺は置いてあったFN57を手に取った。
弾倉を確認する。十分な弾数は残っていた。
「派遣元の支給品です。女性も同じモノを使用してます」
俺は銃身のほうを持ってリュシュカさんに差し出す。おずおずと、彼女は銃を受け取った。
「......重いんですね」
「そりゃあ」
思わず笑みが零れる。
「それでも、こっちに較べればかなり軽いですよ」
自分の上着の左腕脇を指差して言った。上着の下にはデザートイーグルが入っている。
俺は先ほどと同じ場所に、ターゲットを設置した。
リュシュカさんはじっと銃を持つ自分の手を見つめて────ゆっくりと射撃位置に立つ。
横から覗き込んで、軽く銃身を持って位置を修正した。......小さいな、手。
「ここが照門、これが照星。門から星を覗き込んで、その先に目標物があれば命中します。完全に中心に合わせるよりも、ほんの少し照星が下に位置するように意識して構えた方がいいです」
照準の合わせ方を説明する。
「脇はしめて」
「はい」
返事を聞いて、俺は彼女から少し離れた。
ゆっくり、丁寧に発射音が鳴る。
弾はほとんどそれて────最後の1つがかろうじてかすったのか、一番左端の目標の端が砕けた。
「ふふ。......やっぱり、ダメみたいですね」
苦笑しながらリュシュカさんは俺にFN57を返す。受け取って、俺は自分の鞄にそれをしまい込んだ。
突然鳴り出す呼出音。────リュシュカさんが胸ポケットから携帯電話を取り出して、俺に目礼したあと電話に出た。
「はい、ミラーです。......はい。......わかりました、すぐ戻ります」
短い会話のあと彼女は電話を切り、俺の方へ向いて行った。
「指揮所に連絡が来ているようなので、ちょっと行ってきますね」
「はい」
俺は軽く手を振って、駆け出すリュシュカさんの背中を見送った。
目標を片付けるため、外壁の裏に向かう。
────微弱な電子音が聞こえる。
音の出所を求め、俺は周囲を見回した。
それは程なく見つかった。────発射された弾の道筋を計測して、解析するための機械だ。俺としてはこういう機械はあまり信用できないのだが、少し気になってディスプレイを覗き込んだ。
......何だこれは。
ディスプレイに表示された結果を、俺は思わず凝視した。
恐らく先程リュシュカさんが撃った結果だろう。
『1射から5射、目標外。6射、目標至近。命中率0%』
ここまでは、先ほど見たままの内容。だが。
『弾道誤差0.01%以下。射線制御レベルS++』
『S++』......曲撃ちのレベルだぞ、それは。故障か?
俺でさえ、精密射撃時の精度は『A〜A+』がせいぜいだというのに......
しばらくディスプレイを見つめ......おもむろに機械のスイッチを切った。
何故かは分からない。
先程のリュシュカさんの苦笑が脳裏をかすめた。
†
扉を開けると、オペレータが『主任、こちらです』と呼びかけてきた。
そのままリュシュカはデスクに寄り、電話を取る。
「はい。......ええ......」
次の瞬間、彼女の表情が曇った。.......が、やがて笑顔を作って応える。
「......いえ。大丈夫です。毎年のことですし......はい。了解しました。では」
簡単に受け答えすると、リュシュカはそのまま受話器を置き、オペレータに『有難う』と言って指揮所を出た。
そのまま建物の裏へ行くと────溜息をつく。
電話は明日の来訪者についてのものだった。
しばらく足元を見つめ────リュシュカは軽く両手で気合を入れるように自分の頬を叩いた。
自分のトラブルは自分で解決しなければならないはずだ。
例えそれが......いわれのない内容であっても。
†
次の日は、ノックの音がする前に身支度は済ませてしまった。
「おはようございます」
リュシュカさんは昨日同様笑顔で入ってきたが────心なしか顔色が悪く見える。
「おはようございます。.......リュシュカさん?」
「はい?」
明るく返事をする彼女。
「......あの......大丈夫......ですか」
「え......調子悪そうに見えますか?」
手元のラップトップを操作しながら、彼女は答えた。
「昨日あまり眠れなくて......そのせいかもしれませんね。枕が変わると寝つきが変わるっていいますし」
......それくらいなら、いいのだけど。
「────そうだ、マットさん。今日、見学者が来ることになっているんです」
「......見学?」
「ええ。上の指示で......年に2回ほど、新人研修なども兼ねて二種と三種で互いの施設を視察に行くんです。今は私達三種の施設は工事のためほとんど稼動してないですから、こちらを見に来ることになったんでしょう」
笑顔のまま、説明してくれる彼女。何とも不自然な感じのする────
『彼女、他人と思っていたらどちらかというと笑顔で武装するから』
不意にアヤさんの言葉が脳裏をよぎる。
そうだ、この表情は会ったばっかりの頃の『防御』の表情────
昨日の約束通り子供達の食べ終わった皿を洗い、外へ出る。
訓練開始まであと30分。
最後の打合せをしている最中だった。
「では────」
リュシュカさんが書類に目を落とし、ふと顔を上げ......そのまま俺の顔を凝視する。
「......?」
俺は途惑い......気が付いた。────彼女が見ているのは、俺の後ろ......?
「続きを」
気付かなかった振りをして、俺はリュシュカさんを促した。
「あ、はい、すみません」
リュシュカさんは書類に視線を戻し、残りをざっと俺に説明した。
「了解しました」
「ではお願いします」
彼女はファイルを閉じ、後ろを向いて歩き出し......足を止め、一点を凝視した。
その視線の先を辿る。
線の細い、銀縁の眼鏡をかけた俺と同じか少し年上の男。そしてその隣には寄り添うように立つ銀色の髪をポニーテールにした女の子。
────やがて、リュシュカさんは振り切るように視線をそらし、指揮所の方向へ歩いていく。
男の視線は、まっすぐ彼女の背中を射続けていた。
†
「────全て記憶しておけ、アクセラ。いずれお前たちが滅ぼすべき『敵』だ」
男の声に少女はか細い、感情に乏しい声で応えた。
「......はい、マスター」