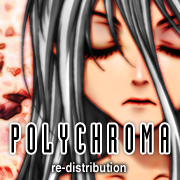打算的な、あまりに打算的な:GateOdyssey:novels|創作小説集団CRAFTWORX(クラフトワークス)
打算的な、あまりに打算的な
Rejection
一夜明けて。
本来出勤だったはずの翌日は事前に連絡があり急遽自宅待機となった。
とはいえ独り身の俺としては特に何もすることはなく、ごくごくいつも通りのリハビリ用トレーニングを行なった以外は、ただのんびりとしていただけだった。
22時30分。
インターフォンの前で待っていた俺は、いきなり扉が開いたので驚いた。
「......おはようございます」
感情のこもってない声でリュシュカさんが挨拶してきた。
思わず問い返す。
「────どうかしましたか?」
「いえ、どうもしません」
リュシュカさんは『何か』含んだ声で応えた。
扉のオートロックがかかったのを確認すると、彼女が俺の顔を見上げる。
「いつもの部屋に行く前に、局長の所へ寄ってください。それから、IDカードが出来上がっているのでそれも一緒に渡してもらえるでしょう。私、マットさんがくるまであの部屋で待ってますから」
「......? はい」
一方的にそう言うと、彼女はヒールを鳴らしてどんどん奥へ歩いていった。
局長室......確か最上階だったよな。
彼女の言葉にひっかかりを感じながらも、俺は言われた通りそこへ向かった。
「急に呼び出してすまない」
「......いえ」
扉へ入って敬礼した俺に、局長は座りたまえ、と言った。
「ひとまず、これを渡しておこう」
ソファに腰掛けた俺の前に、IDカードがすっと置かれる。
リュシュカさん達がつけているのと同じデザインのカード。名前に「Mathias Sievers」の文字が刻印されている。
俺は受け取って、それに目を通した。
ごくごく普通の、バイオメトリクスによる認証カード。しかし────
「......正......職員?」
俺の扱いは『臨時職員』だったはず。
「そうだ。君にこの部屋に立ち寄ってもらったのは、それについての話があるからだ。ミラー博士は何も言ってなかったのかね?」
「はい、特に何も......」
俺はリュシュカさんの様子を思い返しながら応えた。......彼女のあの態度はこれに関係があるのだろうか。
局長はそうか、とだけ応えて話を続けた。
「君に昨日自宅待機してもらったのは、先日の事件についての対策を上層部で検討していたからだ」
「......」
「最大の問題は、君がとった行動にある」
局長は苦味を含んだ表情で語る。
「臨時職員だったはずの君が施設内に火器を持ち込み、緊急事態の解決のためとは言え施設のセキュリティを破壊しようと目論見、なおかつそれは実行された」
「はい」
「今回の件は内裡で処理することが出来たが、このことが軍の上層部に知られれば我々は重大なペナルティを負うこととなる。......研究の継続については何とも言えんが、最悪の場合君の処遇は......」
「でしょうね」
それについては考えなかったわけでもない。......無意識に深く考えなかっただけで。
「だが君が取った行動があったからこそ、今回の事件を早急かつ最少の損害で処理できたのもまた事実だ」
俺は黙って局長の言葉を聴いていた。
今回の行動は彼らが一方的に俺を断罪したとしても文句のつけようがないことだ。だがこうやって俺を擁護する言葉を出してくると言うことは────
「交換条件があるということですか」
局長がぐっと苦しそうな表情になる。
よくこのポストにつけたもんだな......
「────ともかく」
さすがに自分の表情がまずいと思ったのか、局長はごほっと咳をしてから一方的に話を続けた。
「当初から君は正職員として雇用したことにする。給与はこの施設の職員の最低ラインだが、それでも当初支払う予定だった金額より少しは良くなるだろう。その代わりと言っては何だが......子供達に戦闘及び射撃技術の指導を行なってほしい」
「......」
考え込んだ様子を見せた俺に、局長が畳みかけるように言う。
「悪い条件じゃないと思うがね」
「少し考えさせてもらえませんか」
俺は立ち上がって、ただそう言った。
「うむ。君も心の準備と言うものが必要だろう。できれば明日────」
「......は休日を戴いてますが」
「そうか。では明後日の出勤時には、はっきりした返事を聞かせてくれたまえ」
......局長は単に俺が返事を先延ばししたものと決め付けたようだ。
その誤解を解く気分にもなれず、俺は無機質に挨拶をして局長室を退去した。
......あれ。
最上階から地下へ戻ると、部屋の中ではリュシュカさんともう1人女性が待っていた。
リュシュカさんは子供達の話相手になっている。
穏やかな笑顔だ。────彼女にとって本当にこいつらは可愛らしい存在なのだろう。
なら。『お守り』の役目を離れなくてはならなかった程の『痛み』とは......何なのだろうか。
「意外と早かったわね」
「あ、はい」
もう1人の女性のほうに声をかけられ、慌てて返事する。
黒いショートカットの長身。切れ長な瞳の、エキゾチックなタイプの美人。
「初めまして。アヤ=ツヅキです」
手を差し出され、途惑いながら軽く握り返す。
「技術部の部長とここの人事担当を兼任しています」
......技術部の所属ということは、リュシュカさんの上司にも当たる訳か。
「────マティアス=シーヴァーズです」
「ミラー博士から話は聞いてるわ」
ツヅキさんが鮮やかな笑顔で微笑む。そのまま手に持っていたファイルをめくった。リュシュカさんが俺と面談したときに使用していたあのファイルだ。
「本来なら貴方のことについてはミラー博士に一任するはずだったのだけど、事態が変わってしまったから......今日から貴方の身柄は私の管轄になります」
「......と言われても」
え、という表情で俺を見る2人。
「俺、まだ局長に『はい』とも『いいえ』とも答えてないんですが」
ツヅキさんが不思議そうな表情をする。
「『はい』としか答えようがないでしょうに」
「そうですか? 俺はそれだけのことをしたのだし......かばい立ててもらえるのは有難いですが不正には違いないでしょう」
そう言った途端、リュシュカさんの表情が硬くなった。
「リュシィ?」
子供達が不思議そうな顔で彼女の顔を覗き込む。
「......ううん、何でもないの」
彼女は子供達に取り繕うような笑顔を見せる。
「......」
ツヅキさんはそんな彼女の様子を見て......ファイルをぱたんと閉じ、俺のほうに向き直って言った。
「......折角ですから、お近づきの印に夕飯でも食べにいきましょうか」
へ?
唐突な話に俺は反応し損ねた。
「先輩......でも、まだウィークデイ」
リュシュカさんも途惑っている。ツヅキさんはにっこり笑って言った。
「どうせ皆シフト勤務なんだから、スケジュールなんてそうそう合わないわよ。それに、実験室の設備を新しく入れ替えるまでまともな仕事なんてできないでしょうし」
これまたはっきりと言う人だな。
「とは言ってもマットさんは夜間勤務だから晩御飯時だとアルコール飲めないわよね......じゃあマットさんのOFFの日に合わせましょ。マットさん、次のOFFは?」
「明日休みですけど。......元々の予定で」
「あら、ちょうどいいわね。じゃ悪いけど明日、施設の近くに出てきてくれないかしら」
有無を言わさぬ口調でお願いされてしまった。こりゃ何言っても敵いそうにない。押し切られる前に降参しておくことにする。
「わかりました。明日の何時頃ですか」
「20時よ。よろしくね」
そう言うと、アヤさんは手のひらをひらひらと振って部屋から出て行った。
「じゃ、私もいくわね」
リュシュカさんも立ち上がる。
「えー」
子供達の不満の声。......懐かれてるなあ。現役のお守り役からすると、微妙な心境だ。
「先輩の話、終わったから。またそのうち来るわ」
「約束だよー」
「うん」
そう言ってリュシュカさんも扉の向こうに消えた。
俺はようやく椅子に座って、深く息を吐く。
アヤ=ツヅキさん。名前は初めて聞いたけど、何かどこかで会ったような気がする。
どこだっただろう────?
考え始めたとき。とてとてとシナモンが寄ってきた。
「ねー、マット。この間どうやってガラス壊したのか教えてくれよー」
興味津々な瞳で俺を見つめて訊く。
「......それは話せないってこないだ言っただろう」
「えー」
ぷうっと頬を膨らますシナモン。
「大体お前、何でそんなに喧嘩好きなんだよ」
そういうと、シナモンはえっへんと胸を張った。
「関係ないもーん。壊せなさそうなものを壊すのは最強を目指す者のロマンなのだっ」
「何だそれ......」
乾いた笑いが心をよぎる。
「許してやってよ、マット。こいつ、それしか能がないから」
離れたところで冷静に言うマロウに、シナモンがくるりと廻れ右して走ってゆく。
「何だとこのやろう〜」
あ。また始まったよ。子供は元気だな......
「おい」
声と共に唐突に背後からシャツの裾を引っ張る気配。
振り返るとローレルが相変わらずの無表情で俺を見上げていた。
「『でざーといーぐる』見せて」
無機質な声でぼそっと呟く。
「今もってないよ」
「......つまんない」
ちょっと不満そうな顔。
「しょーがねーだろ、本当は中に持ち込んじゃいけないんだから」
苦笑いして言うと、ローレルは大まじめな表情で言った。
「じゃ今度内緒で持ってきて」
「駄目。俺今それで怒られてんだから」
「......『大人』でも怒られるの?」
────う。
ローレルの後ろにくっついてるタイムに訊かれ、言葉に詰まる。
「......まあ、悪いことすれば『大人』でも怒られるんだよ」
説明していて自分がイタい。
「ふうん」
不思議そうな表情で考え込んでいるタイムを見て、俺は何となく尋ねてみる。
「なあ......リュシュカさんのことは好きか?」
「リュシィ?」
そういうと、タイムはにっこり笑って言った。
「うん、好き。あまり顔に出さないけど、ここのみんなはリュシィ、大好きなの。みんなのお姉さんだから」
笑顔で語るタイムの様子は、さながら『砂糖菓子』とも形容できそうだった。そう、ナーサリー・ライムズの。
「......そっか」
それが何の保証になるわけでもないけれど。何となく俺は安心する。
────その時。タイムから返ってきたのは、地雷のような言葉だった。
「ね、マットはリュシィのこと好き?」
「......はい?」
思わず上ずった声で訊き返す。
「リュシィのこと、好き?」
え。────あの。その。
「......嫌いじゃないですよ?」
何故、丁寧語で返事してるんだ俺。
「そっかぁ。好きなんだねー」
「いや、その......」
「好きじゃないの?」
「えーとね......タイム、大人にはあまりはっきりものを言っちゃうと問題あるときがね」
反対の方向を見ながら、もごもごと。────子供相手に何必死に弁明しているんだろう。
セージがそんな俺を見て言う。
「マット、顔真っ赤だぞ」
「ううう......うるさーいっっ!」
何か俺のほうが餓鬼みたいだ。
────おかげで俺は考えていたことをすっかり忘れてしまったのだった。
本来出勤だったはずの翌日は事前に連絡があり急遽自宅待機となった。
とはいえ独り身の俺としては特に何もすることはなく、ごくごくいつも通りのリハビリ用トレーニングを行なった以外は、ただのんびりとしていただけだった。
†
22時30分。
インターフォンの前で待っていた俺は、いきなり扉が開いたので驚いた。
「......おはようございます」
感情のこもってない声でリュシュカさんが挨拶してきた。
思わず問い返す。
「────どうかしましたか?」
「いえ、どうもしません」
リュシュカさんは『何か』含んだ声で応えた。
扉のオートロックがかかったのを確認すると、彼女が俺の顔を見上げる。
「いつもの部屋に行く前に、局長の所へ寄ってください。それから、IDカードが出来上がっているのでそれも一緒に渡してもらえるでしょう。私、マットさんがくるまであの部屋で待ってますから」
「......? はい」
一方的にそう言うと、彼女はヒールを鳴らしてどんどん奥へ歩いていった。
局長室......確か最上階だったよな。
彼女の言葉にひっかかりを感じながらも、俺は言われた通りそこへ向かった。
「急に呼び出してすまない」
「......いえ」
扉へ入って敬礼した俺に、局長は座りたまえ、と言った。
「ひとまず、これを渡しておこう」
ソファに腰掛けた俺の前に、IDカードがすっと置かれる。
リュシュカさん達がつけているのと同じデザインのカード。名前に「Mathias Sievers」の文字が刻印されている。
俺は受け取って、それに目を通した。
ごくごく普通の、バイオメトリクスによる認証カード。しかし────
「......正......職員?」
俺の扱いは『臨時職員』だったはず。
「そうだ。君にこの部屋に立ち寄ってもらったのは、それについての話があるからだ。ミラー博士は何も言ってなかったのかね?」
「はい、特に何も......」
俺はリュシュカさんの様子を思い返しながら応えた。......彼女のあの態度はこれに関係があるのだろうか。
局長はそうか、とだけ応えて話を続けた。
「君に昨日自宅待機してもらったのは、先日の事件についての対策を上層部で検討していたからだ」
「......」
「最大の問題は、君がとった行動にある」
局長は苦味を含んだ表情で語る。
「臨時職員だったはずの君が施設内に火器を持ち込み、緊急事態の解決のためとは言え施設のセキュリティを破壊しようと目論見、なおかつそれは実行された」
「はい」
「今回の件は内裡で処理することが出来たが、このことが軍の上層部に知られれば我々は重大なペナルティを負うこととなる。......研究の継続については何とも言えんが、最悪の場合君の処遇は......」
「でしょうね」
それについては考えなかったわけでもない。......無意識に深く考えなかっただけで。
「だが君が取った行動があったからこそ、今回の事件を早急かつ最少の損害で処理できたのもまた事実だ」
俺は黙って局長の言葉を聴いていた。
今回の行動は彼らが一方的に俺を断罪したとしても文句のつけようがないことだ。だがこうやって俺を擁護する言葉を出してくると言うことは────
「交換条件があるということですか」
局長がぐっと苦しそうな表情になる。
よくこのポストにつけたもんだな......
「────ともかく」
さすがに自分の表情がまずいと思ったのか、局長はごほっと咳をしてから一方的に話を続けた。
「当初から君は正職員として雇用したことにする。給与はこの施設の職員の最低ラインだが、それでも当初支払う予定だった金額より少しは良くなるだろう。その代わりと言っては何だが......子供達に戦闘及び射撃技術の指導を行なってほしい」
「......」
考え込んだ様子を見せた俺に、局長が畳みかけるように言う。
「悪い条件じゃないと思うがね」
「少し考えさせてもらえませんか」
俺は立ち上がって、ただそう言った。
「うむ。君も心の準備と言うものが必要だろう。できれば明日────」
「......は休日を戴いてますが」
「そうか。では明後日の出勤時には、はっきりした返事を聞かせてくれたまえ」
......局長は単に俺が返事を先延ばししたものと決め付けたようだ。
その誤解を解く気分にもなれず、俺は無機質に挨拶をして局長室を退去した。
†
......あれ。
最上階から地下へ戻ると、部屋の中ではリュシュカさんともう1人女性が待っていた。
リュシュカさんは子供達の話相手になっている。
穏やかな笑顔だ。────彼女にとって本当にこいつらは可愛らしい存在なのだろう。
なら。『お守り』の役目を離れなくてはならなかった程の『痛み』とは......何なのだろうか。
「意外と早かったわね」
「あ、はい」
もう1人の女性のほうに声をかけられ、慌てて返事する。
黒いショートカットの長身。切れ長な瞳の、エキゾチックなタイプの美人。
「初めまして。アヤ=ツヅキです」
手を差し出され、途惑いながら軽く握り返す。
「技術部の部長とここの人事担当を兼任しています」
......技術部の所属ということは、リュシュカさんの上司にも当たる訳か。
「────マティアス=シーヴァーズです」
「ミラー博士から話は聞いてるわ」
ツヅキさんが鮮やかな笑顔で微笑む。そのまま手に持っていたファイルをめくった。リュシュカさんが俺と面談したときに使用していたあのファイルだ。
「本来なら貴方のことについてはミラー博士に一任するはずだったのだけど、事態が変わってしまったから......今日から貴方の身柄は私の管轄になります」
「......と言われても」
え、という表情で俺を見る2人。
「俺、まだ局長に『はい』とも『いいえ』とも答えてないんですが」
ツヅキさんが不思議そうな表情をする。
「『はい』としか答えようがないでしょうに」
「そうですか? 俺はそれだけのことをしたのだし......かばい立ててもらえるのは有難いですが不正には違いないでしょう」
そう言った途端、リュシュカさんの表情が硬くなった。
「リュシィ?」
子供達が不思議そうな顔で彼女の顔を覗き込む。
「......ううん、何でもないの」
彼女は子供達に取り繕うような笑顔を見せる。
「......」
ツヅキさんはそんな彼女の様子を見て......ファイルをぱたんと閉じ、俺のほうに向き直って言った。
「......折角ですから、お近づきの印に夕飯でも食べにいきましょうか」
へ?
唐突な話に俺は反応し損ねた。
「先輩......でも、まだウィークデイ」
リュシュカさんも途惑っている。ツヅキさんはにっこり笑って言った。
「どうせ皆シフト勤務なんだから、スケジュールなんてそうそう合わないわよ。それに、実験室の設備を新しく入れ替えるまでまともな仕事なんてできないでしょうし」
これまたはっきりと言う人だな。
「とは言ってもマットさんは夜間勤務だから晩御飯時だとアルコール飲めないわよね......じゃあマットさんのOFFの日に合わせましょ。マットさん、次のOFFは?」
「明日休みですけど。......元々の予定で」
「あら、ちょうどいいわね。じゃ悪いけど明日、施設の近くに出てきてくれないかしら」
有無を言わさぬ口調でお願いされてしまった。こりゃ何言っても敵いそうにない。押し切られる前に降参しておくことにする。
「わかりました。明日の何時頃ですか」
「20時よ。よろしくね」
そう言うと、アヤさんは手のひらをひらひらと振って部屋から出て行った。
「じゃ、私もいくわね」
リュシュカさんも立ち上がる。
「えー」
子供達の不満の声。......懐かれてるなあ。現役のお守り役からすると、微妙な心境だ。
「先輩の話、終わったから。またそのうち来るわ」
「約束だよー」
「うん」
そう言ってリュシュカさんも扉の向こうに消えた。
俺はようやく椅子に座って、深く息を吐く。
アヤ=ツヅキさん。名前は初めて聞いたけど、何かどこかで会ったような気がする。
どこだっただろう────?
考え始めたとき。とてとてとシナモンが寄ってきた。
「ねー、マット。この間どうやってガラス壊したのか教えてくれよー」
興味津々な瞳で俺を見つめて訊く。
「......それは話せないってこないだ言っただろう」
「えー」
ぷうっと頬を膨らますシナモン。
「大体お前、何でそんなに喧嘩好きなんだよ」
そういうと、シナモンはえっへんと胸を張った。
「関係ないもーん。壊せなさそうなものを壊すのは最強を目指す者のロマンなのだっ」
「何だそれ......」
乾いた笑いが心をよぎる。
「許してやってよ、マット。こいつ、それしか能がないから」
離れたところで冷静に言うマロウに、シナモンがくるりと廻れ右して走ってゆく。
「何だとこのやろう〜」
あ。また始まったよ。子供は元気だな......
「おい」
声と共に唐突に背後からシャツの裾を引っ張る気配。
振り返るとローレルが相変わらずの無表情で俺を見上げていた。
「『でざーといーぐる』見せて」
無機質な声でぼそっと呟く。
「今もってないよ」
「......つまんない」
ちょっと不満そうな顔。
「しょーがねーだろ、本当は中に持ち込んじゃいけないんだから」
苦笑いして言うと、ローレルは大まじめな表情で言った。
「じゃ今度内緒で持ってきて」
「駄目。俺今それで怒られてんだから」
「......『大人』でも怒られるの?」
────う。
ローレルの後ろにくっついてるタイムに訊かれ、言葉に詰まる。
「......まあ、悪いことすれば『大人』でも怒られるんだよ」
説明していて自分がイタい。
「ふうん」
不思議そうな表情で考え込んでいるタイムを見て、俺は何となく尋ねてみる。
「なあ......リュシュカさんのことは好きか?」
「リュシィ?」
そういうと、タイムはにっこり笑って言った。
「うん、好き。あまり顔に出さないけど、ここのみんなはリュシィ、大好きなの。みんなのお姉さんだから」
笑顔で語るタイムの様子は、さながら『砂糖菓子』とも形容できそうだった。そう、ナーサリー・ライムズの。
「......そっか」
それが何の保証になるわけでもないけれど。何となく俺は安心する。
────その時。タイムから返ってきたのは、地雷のような言葉だった。
「ね、マットはリュシィのこと好き?」
「......はい?」
思わず上ずった声で訊き返す。
「リュシィのこと、好き?」
え。────あの。その。
「......嫌いじゃないですよ?」
何故、丁寧語で返事してるんだ俺。
「そっかぁ。好きなんだねー」
「いや、その......」
「好きじゃないの?」
「えーとね......タイム、大人にはあまりはっきりものを言っちゃうと問題あるときがね」
反対の方向を見ながら、もごもごと。────子供相手に何必死に弁明しているんだろう。
セージがそんな俺を見て言う。
「マット、顔真っ赤だぞ」
「ううう......うるさーいっっ!」
何か俺のほうが餓鬼みたいだ。
────おかげで俺は考えていたことをすっかり忘れてしまったのだった。